(Natural Science), No.48 / 神奈川県立博物館研究報告
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Qt9z7703dj.Pdf
UC San Diego UC San Diego Previously Published Works Title Phylogeny and biogeography of a shallow water fish clade (Teleostei: Blenniiformes) Permalink https://escholarship.org/uc/item/9z7703dj Journal BMC Evolutionary Biology, 13(1) ISSN 1471-2148 Authors Lin, Hsiu-Chin Hastings, Philip A Publication Date 2013-09-25 DOI http://dx.doi.org/10.1186/1471-2148-13-210 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Lin and Hastings BMC Evolutionary Biology 2013, 13:210 http://www.biomedcentral.com/1471-2148/13/210 RESEARCH ARTICLE Open Access Phylogeny and biogeography of a shallow water fish clade (Teleostei: Blenniiformes) Hsiu-Chin Lin1,2* and Philip A Hastings1 Abstract Background: The Blenniiformes comprises six families, 151 genera and nearly 900 species of small teleost fishes closely associated with coastal benthic habitats. They provide an unparalleled opportunity for studying marine biogeography because they include the globally distributed families Tripterygiidae (triplefin blennies) and Blenniidae (combtooth blennies), the temperate Clinidae (kelp blennies), and three largely Neotropical families (Labrisomidae, Chaenopsidae, and Dactyloscopidae). However, interpretation of these distributional patterns has been hindered by largely unresolved inter-familial relationships and the lack of evidence of monophyly of the Labrisomidae. Results: We explored the phylogenetic relationships of the Blenniiformes based on one mitochondrial (COI) and four nuclear (TMO-4C4, RAG1, Rhodopsin, and Histone H3) loci for 150 blenniiform species, and representative outgroups (Gobiesocidae, Opistognathidae and Grammatidae). According to the consensus of Bayesian Inference, Maximum Likelihood, and Maximum Parsimony analyses, the monophyly of the Blenniiformes and the Tripterygiidae, Blenniidae, Clinidae, and Dactyloscopidae is supported. -

Habitat Determinants of Chaetodon Butterflyfish and Fishery-Targeted Coral Reef Fish Assemblages in the Central Philippines
ResearchOnline@JCU This file is part of the following reference: Leahy, Susannah Marie (2016) Habitat determinants of Chaetodon butterflyfish and fishery-targeted coral reef fish assemblages in the central Philippines. PhD thesis, James Cook University. Access to this file is available from: http://researchonline.jcu.edu.au/46299/ The author has certified to JCU that they have made a reasonable effort to gain permission and acknowledge the owner of any third party copyright material included in this document. If you believe that this is not the case, please contact [email protected] and quote http://researchonline.jcu.edu.au/46299/ Habitat determinants of Chaetodon butterflyfish and fishery-targeted coral reef fish assemblages in the central Philippines Thesis submitted by Susannah Marie Leahy (BSc, MAppSci) on 8 February 2016 for the degree of Doctor of Philosophy in the College of Marine and Environmental Sciences, the Centre for Tropical and Environmental Sustainability Science, and the Centre of Excellence for Coral Reef Studies James Cook University Cairns, Queensland, Australia This page is intentionally left blank. ii Acknowledgements I would first like to thank my supervisors: Garry Russ, Rene Abesamis, and Mike Kingsford. Garry, for his guidance and advice, and for his trust in me. Rene, for teaching me how to function in the Philippines. Mike, for being such a source of wisdom when I felt out of my depth. I would also like to thank the organisations who funded my work, including the Graduate Research School at James Cook University for a Postgraduate Research Scholarship and for two research grants, as well as the Australian Society for Fish Biology for the Michael Hall Student Innovation Award. -

The Japanese Experience in Integrated Urban Flood Risk Management Knowledge Note 2: Planning and Prioritizing Urban Flood Risk Management Investments Ii
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Learning from Japan’s Experience in Integrated Urban Flood Risk Management: A Series of Knowledge Notes Public Disclosure Authorized Knowledge Note 2: Planning and Prioritizing Urban Flood Risk Management Investments ©2019 The World Bank International Bank for Reconstruction and Development The World Bank Group 1818 H Street NW, Washington, DC 20433 USA October 2019 DISCLAIMER This work is a product of the staff of The World Bank with external contributions. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. The report reflects information available up to June 30, 2019. RIGHTS AND PERMISSIONS The material in this work is subject to copyright. Because The World Bank encourages dissemination of its knowledge, this work may be reproduced, in whole or in part, for noncommercial purposes as long as full attribution to this work is given. Any queries on rights and licenses, including subsidiary rights, should be addressed to World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; e-mail: [email protected]. CITATION Please cite this series of knowledge notes and/or its individual elements as follows: World Bank. -

Universidade Tiradentes Programa De Pós - Graduação Em Saúde E Ambiente
UNIVERSIDADE TIRADENTES PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM SAÚDE E AMBIENTE ASPECTOS PARASITOLÓGICOS DE RAIAS DO GÊNERO Hypanus (MYLIOBATIFORMES: DASYATIDAE) NO NORDESTE DO BRASIL MARINA GOMES LEONARDO Aracaju Maio/2018 UNIVERSIDADE TIRADENTES PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM SAÚDE E AMBIENTE ASPECTOS PARASITOLÓGICOS DE RAIAS DO GÊNERO Hypanus (MYLIOBATIFORMES: DASYATIDAE) NO NORDESTE DO BRASIL Dissertação de Mestrado submetida à banca examinadora para a obtenção do título de Mestre em Saúde e Ambiente, na área de concentração Saúde e Ambiente. MARINA GOMES LEONARDO Orientadores Prof. Dr. Ricardo Massato Takemoto Prof. Dr. Rubens Riscala Madi Aracaju/SE 2018 Leonardo, Marina Gomes L581a Aspectos parasitológicos de raias do gênero hypanus (Myliobatiformes: Dasyatidae) no nordeste do Brasil / Marina Gomes Leonardo ; orientação [de] Prof. Dr. Ricardo Massato Takemoto, Prof. Dr. Rubens Riscala Madi– Aracaju: UNIT, 2018. 51f. : 30 cm Dissertação (Mestrado em Saúde e Ambiente) - Universidade Tiradentes, 2018 Inclui bibliografia. 1. Fauna parasitária. 2.Raia de Pedra. 3. Raia Lixa. 4. Zoonose. 5. Sergipe I. Leonardo, Marina Gomes. II. Takemoto, Ricardo Massato (orient.). III. Madi, Rubens Riscala (oriente.) IV. Universidade Tiradentes. V. Título. CDU: 591. 69: 597. 317.7 ASPECTOS PARASITOLÓGICOS DE RAIAS DO GÊNERO Hypanus (MYLIOBATIFORMES: DASYATIDAE) NO NORDESTE DO BRASIL Marina Gomes Leonardo Dissertação de mestrado apresentada à banca examinadora para do título de Mestre em Saúde e Ambiente, na de concentração Saúde e Ambiente. Aprovada por: Dr. Ricardo Massato Takemoto Dr. Rubens Riscala Madi Dra. Verônica de Lourdes Sierpe Geraldo Universidade Tiradentes Dra. Maria Lúcia Góes de Araújo Universidade Federal de Sergipe “Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé e SONHO em realidade.” Autor desconhecido Agradecimentos Sendo clichê e realista, gostaria de agradecer primeiramente a Deus, pois sem ele e minha fé, provavelmente não teria superado nem metade das adversidades por quais passei nesses dois anos e 3 meses. -

Chinese Red Swimming Crab (Portunus Haanii) Fishery Improvement Project (FIP) in Dongshan, China (August-December 2018)
Chinese Red Swimming Crab (Portunus haanii) Fishery Improvement Project (FIP) in Dongshan, China (August-December 2018) Prepared by Min Liu & Bai-an Lin Fish Biology Laboratory College of Ocean and Earth Sciences, Xiamen University March 2019 Contents 1. Introduction........................................................................................................ 5 2. Materials and Methods ...................................................................................... 6 2.1. Study site and survey frequency .................................................................... 6 2.2. Sample collection .......................................................................................... 7 2.3. Species identification................................................................................... 10 2.4. Sample measurement ................................................................................... 11 2.5. Interviews.................................................................................................... 13 2.6. Estimation of annual capture volume of Portunus haanii ............................. 15 3. Results .............................................................................................................. 15 3.1. Species diversity.......................................................................................... 15 3.1.1. Species composition .............................................................................. 15 3.1.2. ETP species ......................................................................................... -

Neoclinus Chihiroe (Perciformes: Chaenopsidae) from Dokdo, East Sea, Korea
142KOREAN Se JOURNAL Hun Myoung, OF ICHTHYOLOGY Won-Gi Min, Min-Su, Vol. Woo,33, No. Yun-Bae 2, 142-147, Kim, JinJune Yong 2021 Shin and Joo Myun Park Received: December 31, 2020 ISSN: 1225-8598 (Print), 2288-3371 (Online). DOI: https://doi.org/10.35399/ISK.33.2.10 Revised: February 22, 2021 Accepted: March 23, 2021 New Record of Neoclinus chihiroe (Perciformes: Chaenopsidae) from Dokdo, East Sea, Korea By Se Hun Myoung, Won-Gi Min1, Min-Su Woo1, Yun-Bae Kim1, Jin Yong Shin1 and Joo Myun Park* Dokdo Research Center, Korea Institute of Ocean Science and Technology, Uljin 36315, Republic of Korea 1Ulleungdo-Dokdo Ocean Science Station, Korea Institute of Ocean Science and Technology, Ulleung 40205, Republic of Korea ABSTRACT A single specimen (52.5 mm SL) of Neoclinus chihiroe, belonging to the family Chaen opsidae, was firstly collected from Dokdo, East Sea of Korea on 9 December 2020. This species was characterized by a black spot between the first and the second dorsal spines, and a black spot on upper part of opercular membrane. The species was morphologically similar to N. okazakii, but distinctly distinguished by pectoral fin base without a black dot. This study documents the first record of N. chihiroe in Korean waters and suggests the new Korean name ‘Donghaebineulbedolachi’ for the species. Key words: Neoclinus chihiroe, Chaenopsidae, new record, Dokdo, East Sea INTRODUCTION list of IUCN (Williams and Craig, 2014). This species is expected to live all over Japan waters constituting a popu- The family Chaenopsidae (Perciformes) comprises 96 lation. -
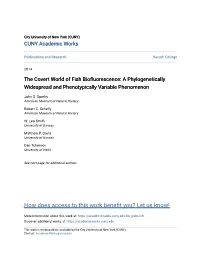
The Covert World of Fish Biofluorescence: a Phylogenetically Widespread and Phenotypically Variable Phenomenon
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works Publications and Research Baruch College 2014 The Covert World of Fish Biofluorescence: A Phylogenetically Widespread and Phenotypically Variable Phenomenon John S. Sparks American Museum of Natural History Robert C. Schelly American Museum of Natural History W. Leo Smith University of Kansas Matthew P. Davis University of Kansas Dan Tchernov University of Haifa See next page for additional authors How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/bb_pubs/29 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] Authors John S. Sparks, Robert C. Schelly, W. Leo Smith, Matthew P. Davis, Dan Tchernov, Vincent A. Pieribone, and David F. Gruber This article is available at CUNY Academic Works: https://academicworks.cuny.edu/bb_pubs/29 The Covert World of Fish Biofluorescence: A Phylogenetically Widespread and Phenotypically Variable Phenomenon John S. Sparks1,2*., Robert C. Schelly1,2, W. Leo Smith3, Matthew P. Davis3, Dan Tchernov4, Vincent A. Pieribone1,5, David F. Gruber2,6*. 1 Department of Ichthyology, American Museum of Natural History, Division of Vertebrate Zoology, New York, New York United States of America, 2 Sackler Institute for Comparative Genomics, American Museum of Natural History, New York, New York, United States of America, 3 Biodiversity Institute, University of Kansas, Lawrence, Kansas, United States of America, 4 Marine Biology Department, The Leon H. Charney School of Marine Sciences, University of Haifa, Mount Carmel, Haifa, Israel, 5 Department of Cellular and Molecular Physiology, The John B. -

Pdf:605.05Kb
Minoji The Minoji is a road that connects Miyajuku (present day Nagoya City, Atstuta Ward) along the old Tokaido Road to Taruijuku(present day Fuwagun in Gifu Prefecture) along the Nakasendo Road (old mountain pass route). This Minoji passed through seven lodging towns of Nagoya, Kiyosu, Inaba, Hagiwara, Okoshi, Sunomata, and Ogaki. Such alternate side routes of the Tokaido and Nakasendo among five roads radiating from Edo were placed under the control of the Edo Shogunate’s road magistrate. The Minoji was greatly used to allow bypassing the sea traffic between Kuwana and Miya along the waterway route Akasaka Nakasendo Goudo Tarui Kano known as Shichiri no Watashi. Mieji In addition, use of the road expanded by many shogun of the Western part of Japan who proceeded on to the capital Kyoto, Ogaki Ibi River Nagara River Gifukaido Kasamatsu and also the road was used for the Edo Period system of Sunomata Sakai River minoji Kiso River Okoshi Sankinkoutai, or alternate attendance, whereby all feudal lords Hagiwara minoji Ichinomiya in the Edo Period were burdened with full travel expenses to Inaba spend every other year in residence in Edo. Other uses of the Kiyosu Junkenkaido Nagoya road were for Korean envoys and the Ryukyu (Okinawa) Tsushima Uwakaido mission to Edo, transport of earthenware pots for storing tea Sanri no Watashi Syonai River Iwatsuka Kamori Manba and also ivory that were offered as gifts, and for various people Saya traveling along the road. Tokaido Yokkaichi Kuwana Sayaji Miya Shichiri no Watashi 11 Site of Okoshi Juku Waki Honjin ▲Garden at the site of the (Historical Site designated by Ichinomiya City) Okoshi Juku Waki Honjin Okoshi Juku Okoshi Juku is currently located near Ichinomiya City and a bustling center for amphibious transport as the lodging town of the Kiso River Okoshi ferry. -

An Investigation Into Australian Freshwater Zooplankton with Particular Reference to Ceriodaphnia Species (Cladocera: Daphniidae)
An investigation into Australian freshwater zooplankton with particular reference to Ceriodaphnia species (Cladocera: Daphniidae) Pranay Sharma School of Earth and Environmental Sciences July 2014 Supervisors Dr Frederick Recknagel Dr John Jennings Dr Russell Shiel Dr Scott Mills Table of Contents Abstract ...................................................................................................................................... 3 Declaration ................................................................................................................................. 5 Acknowledgements .................................................................................................................... 6 Chapter 1: General Introduction .......................................................................................... 10 Molecular Taxonomy ..................................................................................................... 12 Cytochrome C Oxidase subunit I ................................................................................... 16 Traditional taxonomy and cataloguing biodiversity ....................................................... 20 Integrated taxonomy ....................................................................................................... 21 Taxonomic status of zooplankton in Australia ............................................................... 22 Thesis Aims/objectives .................................................................................................. -

Geomorphological Environment for Inundation Attacks: a Comparative Research
立命館地理学 第 30 号(2018)61-75 Geomorphological Environment for Inundation Attacks: A Comparative Research NUKATA Masahiro* The author compares different inundation I. Introduction attacks selected through geomorphological con- There were various tactics to assault castles siderations of them. The research started from and forts in Medieval Japan, including frontal, making landform classification maps of the fire, inundation, hole, starvation and surprise plains concerned based on the observation attacks. Usually multiple modes of attacks were using 1/10,000 areal photos. Archives, old pic- combined. For inundation attacks, the army torial maps and old geomorphological maps started with frontal attack, closing in on an were also surveyed. Geomorphology of inunda- enemy castle from all sides and then built an tion related remains were studied by observing embankment around the castle and introduced ruins and geological formations at the excava- water from the river to flood or isolate the tion sites as much as possible and by reviewing castle. the past excavation reports. There are four well-known inundation attacks in Japan: Bicchu Takamatsu Castle where II. Inundation attack of Bicchu Hideyoshi Toyotomi was involved, Owari Takamatsu Castle Takegahana Castle, Musashi Oshi Castle and Kii Ohda Castle (Figure 1). The author has a 1. Chugoku-no-eki (war) and inundation different idea from common view that Kii Ohda attack of Takamatsu Castle Castle was attacked with 5 km-long embank- The attack against Takamatsu Castle 2) took ment built around the castle located on the place in May and June 1582 during the last Holocene river terrace and therefore reviewed period of Chugoku-no-eki. -

The Kagoshima University Museum No
Bulletin of the Kagoshima University Museum No. 9 A total of 1,277 species, including 129 species that represent the first reliable records from the island on the basis of Annotated Checklist of Marine and Freshwater Fishes Yaku-shima Island ISSN-L 2188-9074 collected specimens and/or underwater photographs, are listed with citation of literature, registration numbers, sizes, ANNOTATED CHECKLIST OF MARINE AND FRESHWATER FISHES OF localities in the island, and nomenclatural, taxonomic, and ecological remarks. Color photographs of all the 129 YAKU-SHIMA ISLAND IN THE OSUMI ISLANDS, species newly recorded from the island are provided. KAGOSHIMA, SOUTHERN JAPAN, WITH 129 NEW RECORDS HIROYUKI MOTOMURA AND SHIGERU HARAZAKI Hiroyuki Motomura • Shigeru Harazaki February 2017 The Kagoshima University Museum Cover photograph: Cephalopholis sonnerati in a wreck off Isso, Yaku-shima island. Photo by S. Harazaki Back cover photograph: Males of Pseudanthias hypselosoma at 15 m depth off Isso, Yaku-shima island. Photo by S. Harazaki Bulletin of the Kagoshima University Museum No. 9 ISSN-L 2188-9074 Annotated checklist of marine and freshwater fishes of Yaku-shima island in the Osumi Islands, Kagoshima, southern Japan, with 129 new records Hiroyuki Motomura1, 3 and Shigeru Harazaki2 1The Kagoshima University Museum, 1–21–30 Korimoto, Kagoshima 890–0065, Japan E-mail: [email protected] 2Yakushima Diving Service “Mori to Umi”, 2473–294 Miyanoura, Yakushima, Kumage, Kagoshima 891–4205, Japan 3Corresponding author Abstract The second edition of an annotated checklist of marine and freshwater fishes of Yaku-shima island in the Osumi Group, Kagoshima Prefecture, southern Japan, was compiled from specimen and literature surveys. -

Hermaphroditism in Fish
Tesis doctoral Evolutionary transitions, environmental correlates and life-history traits associated with the distribution of the different forms of hermaphroditism in fish Susanna Pla Quirante Tesi presentada per a optar al títol de Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona, programa de doctorat en Aqüicultura, del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i Ecologia. Director: Tutor: Dr. Francesc Piferrer Circuns Dr. Lluís Tort Bardolet Departament de Recursos Marins Renovables Departament de Biologia Cel·lular, Institut de Ciències del Mar Fisiologia i Immunologia Consell Superior d’Investigacions Científiques Universitat Autònoma de Barcelona La doctoranda: Susanna Pla Quirante Barcelona, Setembre de 2019 To my mother Agraïments / Acknowledgements / Agradecimientos Vull agrair a totes aquelles persones que han aportat els seus coneixements i dedicació a fer possible aquesta tesi, tant a nivell professional com personal. Per començar, vull agrair al meu director de tesi, el Dr. Francesc Piferrer, per haver-me donat aquesta oportunitat i per haver confiat en mi des del principi. Sempre admiraré i recordaré el teu entusiasme en la ciència i de la contínua formació rebuda, tant a nivell científic com personal. Des del primer dia, a través dels teus consells i coneixements, he experimentat un continu aprenentatge que sens dubte ha derivat a una gran evolució personal. Principalment he après a identificar les meves capacitats i les meves limitacions, i a ser resolutiva davant de qualsevol adversitat. Per tant, el meu més sincer agraïment, que mai oblidaré. During the thesis, I was able to meet incredible people from the scientific world. During my stay at the University of Manchester, where I learned the techniques of phylogenetic analysis, I had one of the best professional experiences with Dr.