第86冊 2020年(令和2年)03月31日発行
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
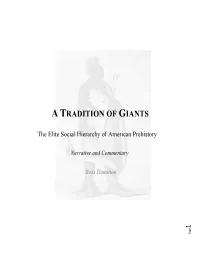
Atradition of Giants
A TRADITION OF GIANTS The Elite Social Hierarchy of American Prehistory Narrative and Commentary Ross Hamilton 1 1 Page Copyright © 2007 by Ross Hamilton: All rights reserved. No portion of this book, except for brief review, may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise—without written permission of the publisher. For information contact Ross Hamilton, 4202 Sibley Avenue, Silverton, Ohio—45236 Cover art courtesy of the Library of Congress; book design by Ross Hamilton. Title of work: A Tradition of Giants Alternative title: The Elite Social Hierarchy of American Prehistory Library of Congress registration number: TXu 1-608-346 Effective date of registration: November 19, 2007 Amendments and additions added 9-16-2012 2 2 Page The Great Peacemaker, Passaconeway Believed by some as perhaps the greatest Sachem who ever lived, Passaconeway was the last of the great kingly chiefs of old. He was a giant among men, physically and spiritually, believed to have stood at least seven feet in height. A powerful medicine man and chieftain of the Penacook tribe, Passaconeway was elected bashaba (emperor) of a confederation of tribes united to stem an aggressive Mohawk nation. In his twilight years this great man traveled in the Maine-New Hampshire-Massachusetts region where he was revered as the mouthpiece of the Great Spirit by both Native and European folk alike. Tradition stays that Passaconeway was a genius, gifted with magical or divine powers employed in his peacemaking efforts. His true power, however, lay in his ability to kindle the fire of peace and brotherly love in the hearts of all irrespective of race or tribal restrictions. -

A Comparison of Shovel Testing and Surface Collection As Archaeological Site Discovery Methods: a Case Study Using Mississippian Farmsteads
University of Mississippi eGrove Electronic Theses and Dissertations Graduate School 2016 A Comparison Of Shovel Testing And Surface Collection As Archaeological Site Discovery Methods: A Case Study Using Mississippian Farmsteads Cameron Smith Howell University of Mississippi Follow this and additional works at: https://egrove.olemiss.edu/etd Part of the Archaeological Anthropology Commons Recommended Citation Howell, Cameron Smith, "A Comparison Of Shovel Testing And Surface Collection As Archaeological Site Discovery Methods: A Case Study Using Mississippian Farmsteads" (2016). Electronic Theses and Dissertations. 337. https://egrove.olemiss.edu/etd/337 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at eGrove. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of eGrove. For more information, please contact [email protected]. A COMPARISON OF SHOVEL TESTING AND SURFACE COLLECTION AS ARCHAEOLOGICAL SITE DISCOVERY METHODS: A CASE STUDY USING MISSISSIPPIAN FARMSTEADS A Thesis presented in partial fulfillment of requirements for the degree of Master of Arts in the Department of Sociology and Anthropology The University of Mississippi By CAMERON SMITH HOWELL May 2016 Copyright Cameron Smith Howell 2016 ALL RIGHTS RESERVED ABSTRACT Shovel testing and controlled surface collection are common methods of archaeological site investigation that are generally approved by state and federal agencies as well as the academic community for cultural resource management projects and research. While both techniques are equally utilized, little research has been conducted on how equivalent these techniques are in terms of their efficacy for finding site. This thesis seeks to find a way to compare these techniques by creating Mathematical Models to describe how well the methods behave when tested on known datasets generated from Mississippian period farmsteads. -

Atradition of Giants
A TRADITION OF GIANTS The Elite Social Hierarchy of American Prehistory Narrative and Commentary Ross Hamilton 1 Page Copyright © 2007 by Ross Hamilton: All rights reserved. No portion of this book, except for brief review, may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise—without written permission of the publisher. For information contact Ross Hamilton, 4202 Sibley Avenue, Silverton, Ohio—45236 Cover art courtesy of the Library of Congress; book design by Ross Hamilton. Title of work: A Tradition of Giants Alternative title: The Elite Social Hierarchy of American Prehistory Library of Congress registration number: TXu 1-608-346 Effective date of registration: November 19, 2007 Amendments and additions added 9-16-2012 2 Page The Great Peacemaker, Passaconeway Believed by some as perhaps the greatest Sachem who ever lived, Passaconeway was the last of the great kingly chiefs of old. He was a giant among men, physically and spiritually, believed to have stood at least seven feet in height. A powerful medicine man and chieftain of the Penacook tribe, Passaconeway was elected bashaba (emperor) of a confederation of tribes united to stem an aggressive Mohawk nation. In his twilight years this great man traveled in the Maine-New Hampshire-Massachusetts region where he was revered as the mouthpiece of the Great Spirit by both Native and European folk alike. Tradition stays that Passaconeway was a genius, gifted with magical or divine powers employed in his peacemaking efforts. His true power, however, lay in his ability to kindle the fire of peace and brotherly love in the hearts of all irrespective of race or tribal restrictions. -

Crafting and Consuming an American Sonoran Desert: Global Visions, Regional Nature and National Meaning
Crafting and Consuming an American Sonoran Desert: Global Visions, Regional Nature and National Meaning Item Type text; Electronic Dissertation Authors Burtner, Marcus Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 02/10/2021 04:13:17 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/268613 CRAFTING AND CONSUMING AN AMERICAN SONORAN DESERT: GLOBAL VISIONS, REGIONAL NATURE AND NATIONAL MEANING by Marcus Alexander Burtner ____________________________________ copyright © Marcus Alexander Burtner 2012 A Dissertation Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF HISTORY In Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2012 2 THE UNIVERSITY OF ARIZONA GRADUATE COLLEGE As members of the Dissertation Committee, we certify that we have read the dissertation prepared by Marcus A. Burtner entitled “Crafting and Consuming an American Sonoran Desert: Global Visions, Regional Nature, and National Meaning.” and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation requirement for the Degree of Doctor of Philosophy ____________________________________________________________Date: 1/7/13 Katherine Morrissey ____________________________________________________________Date: 1/7/13 Douglas Weiner ____________________________________________________________Date: 1/7/13 Jeremy Vetter ____________________________________________________________Date: 1/7/13 Jack C. Mutchler Final approval and acceptance of this dissertation is contingent upon the candidate's submission of the final copies of the dissertation to the Graduate College. I hereby certify that I have read this dissertation prepared under my direction and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation requirement. -

AN HISTORICAL ANALYSIS of the MUTABLE PERSPECTIVES on INTERPRETATIONS of MISSISSIPPIAN PERIOD ICONOGRAPHY by E
A HALLOWED PATH: AN HISTORICAL ANALYSIS OF THE MUTABLE PERSPECTIVES ON INTERPRETATIONS OF MISSISSIPPIAN PERIOD ICONOGRAPHY By ERIC DAVID SINGLETON Bachelor of Arts/Science in History The University of Oklahoma Norman, Oklahoma 2003 Master of Arts/Science in Museum Studies The University of Oklahoma Norman, Oklahoma 2008 Submitted to the Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY May, 2017 A HALLOWED PATH: AN HISTORICAL ANALYSIS OF THE MUTABLE PERSPECTIVES ON INTERPRETIONS OF MISSISSIPPIAN PERIOD ICONOGRAPHY Dissertation Approved: Dr. L.G. Moses Dr. William S. Bryans Dr. Michael M. Smith Dr. F. Kent Reilly, III Dr. Stephen M. Perkins ii ACKNOWLEDGEMENTS It is true that nothing in this world is done alone. I would like to thank my family and friends for all their love and support. My grandparents, parents, sister, cousin, aunts and uncles. They were the foundation of everything that has shaped my life and allowed me the strength to complete this while working full-time. And, to my fiancée Kimberly. I mention her separately, not because she is not included above, but because she is the one person who diligently edited, listened, and gracefully sat by giving up years of vacations, holidays, and parties as I spent countless nights quietly writing. I would also give the most heartfelt thank you to Dr. Moses, Dr. McCoy, and Dr. Smith. Each of you made me the historian I am today. As Dr. James Ronda told me once, pick your professors, not the school—they will shape everything. -

An Analysis of Accession 16082, the Ohio Hopewell Site Collection at the Milwaukee Public Museum
University of Wisconsin Milwaukee UWM Digital Commons Theses and Dissertations May 2020 A Collection Divided: an Analysis of Accession 16082, the Ohio Hopewell Site Collection at the Milwaukee Public Museum Katrina N. Schmitz University of Wisconsin-Milwaukee Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/etd Part of the Archaeological Anthropology Commons, and the Library and Information Science Commons Recommended Citation Schmitz, Katrina N., "A Collection Divided: an Analysis of Accession 16082, the Ohio Hopewell Site Collection at the Milwaukee Public Museum" (2020). Theses and Dissertations. 2419. https://dc.uwm.edu/etd/2419 This Thesis is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. A COLLECTION DIVIDED: AN ANALYSIS OF ACCESSION 16082, THE OHIO HOPEWELL SITE COLLECTION AT THE MILWAUKEE PUBLIC MUSEUM by Katrina N. Schmitz A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Anthropology at The University of Wisconsin-Milwaukee May 2020 ABSTRACT A COLLECTION DIVIDED: AN ANALYSIS OF ACCESSION 16082, THE OHIO HOPEWELL SITE COLLECTION AT THE MILWAUKEE PUBLIC MUSEUM by By Katrina N. Schmitz The University of Wisconsin-Milwaukee, 2020 Under the Direction of Dr. Patricia B. Richards This thesis investigates and documents sixty-one Ohio Hopewellian objects that form a collection currently housed at the Milwaukee Public Museum (MPM). The objects were excavated from the Hopewell site of Ross County, Ohio which lends its name to a renowned and geographically expansive archaeological cultural horizon. -

Landscape As Monument
A Publication of the Foundation for Landscape Studies A Journal of Place Volume vı | Number ı | Fall 2010 Essays: Landscape as Monument, Monuments in the Landscape 2 David Sloane: Memory and Landscape: Nature and the History of the American Cemetery Elizabeth Barlow Rogers: An Island Named Roosevelt: Presidential Monument and Planned Community John H. Stubbs and Stefan Yarabek: Lednice-Valtice: A Monumental Liechtenstein Landscape within the Prague-Vienna Greenway Place Marker 16 Elizabeth Barlow Rogers: Theodore Roosevelt and the Native American Patrimony Book Reviews 17 Elihu Rubin: Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places By Sharon Zukin Cynthia Zaitzevsky: The Collected Writings of Beatrix Farrand: American Landscape Gardener, 1872–1959 Edited by Carmen Pearson Beatrix Farrand: Private Gardens, Public Landscapes By Judith B. Tankard Tour 23 Contributors 23 Letter from the Editor n this issue of Site/Lines we mark places as monuments Here, however, is a pre- is fostering protection of an moving forward. My article dents to other important have chosen to focus on or place monuments in liminary exploration of a entire regional landscape as is based on conversations aspects of the nation’s archi- monuments – monuments landscapes. Indeed, it would special genre of place mak- a scenic monument with with proponents about its tectural and landscape patri- in landscape settings and take a book – and several ing. We begin with cemeter- recreational, cultural, and history, planning, and archi- mony. landscapes themselves as have in fact been written – to ies, monumental landscapes educational uses. Its crown tecture. I also interviewed We would like to draw Imonuments. -

Book Reviews 431 Study. but It Was Not Until He
Book Reviews 431 study. But it was not until he changed his approach in the form of a more detailed study of a limited area that he was able to gain the recognition that the science of the study of man has now attained. The reviewer is only posing this prob- lem that if social history, such as is found in this monograph, is to be of real importance in the understanding of human be- havior, past or present, those who write it must develop a more precise method. Dr. Bardolph writes with a zeal for the subject and many of his phrases and quotations show a liveliness that make for interesting reading. The monograph is free of errors, is well edited and shows an immense amount of accuracy in dates and references; it literally bristles with footnotes and there is appended an excellent bibliography of prominent American horticultural writers in the period to 1870. Northern Illinois State Teachers College Earl W. Hayter Kaskaskia under the French Regime. By Natalia M. Belting. Volume XXIX, No. 3, Illinois Studies in the Social Sci- ences. (Urbana, Illinois, University of Illinois Press, 1948, pp. 140. Illustrations, appendix, and index. $2.50 clothbound, $1.50 paperbound.) The social history of the French villages in the Illinois country during the eighteenth century, with particular atten- tion to Kaskaskia, is told in this number of the lllinois Studies in the Social Sciences. The other villages are Fort de Char- tres, St. Philippe, Prairie du Rocher, Cahokia, and Ste. Gene- vieve. Kaskaskia was founded when the Kaskaskia Indians left the vicinity of La Salle’s Fort St. -

Archaeologist Volume 2G-J3 £ No
OHIO ARCHAEOLOGIST VOLUME 2G-J3 £ NO. 1 WINTER 1986 Published by THE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY OF OHIO The Archaeological Society of Ohio TERM Gordon Hart, 760 N Main St., Bluffton, Indiana 46714 EXPIRES O.A.S. OFFICERS David J Snyder. P O Box 388, Luckey, Ohio 43443 1986 President Don Gehlbach. 3435 Sciotangy Dr., Columbus, Dr Phillip R Shriver. Miami University, Oxford. Ohio 45056 Ohio 43221 -Tele: Home 459-0808, Bus. 888-3572 Robert Harter, 1961 Buttermilk Hill. Delaware. Ohm 1986 Vice President Scott Haskins, 2160 Fitzroy Dr., Apt A-6, Associate Editor. Martha P Otto, Ohio Historical Society, Columbus, Ohio 43224-Tele: Home 476-4843 Columbus. Ohio Jill Carskaddon, 960 Eastward Circle. Colony North 1986 Exec Sect. Martha Otto, 2200 E. Powell Rd., Westerville, Zanosville. Ohio 43701 Ohio 43081 -Tele: Home 846-7640, Bus. 466-1500 Ext. 256 1986 Treasurer Donald W. Foster, 54-E West Park St., Westerville, All articles, reviews and comments on the Ohio ArchaeOlQQiit should hi; gent tO the Editor Memberships. reQUestl for back Ohio 43081-Tele: Home 891-7417 issues, changes of address, and other matter should be sent I" 1986 Recording Sect. Barbara Motts, 7050 Refugee Rd., Canal the business office Winchester, Ohio 43110-Tele: Home 837-4862 1986 Immediate Past President Mike Kish, 39 Parkview Ave., PLEASE NOTIFY BUSINESS OFFICE IMMEDIATELY OF AD Westerville, Ohio 43081 -Tele: Home 882-4176, DRESS CHANGES. BY POSTAL REGULATIONS SOCIETY MAIL Bus 890-3000 Ext. 107 CANNOT BE FORWARDED. 1986 Editor Robert N. Converse, 199 Converse Dr. Plain City, Ohio 43064-Tele: Home 873-5471, Bus. 873-4664 Editorial Office TRUSTEES 199 Converse Drive, Plain City. -
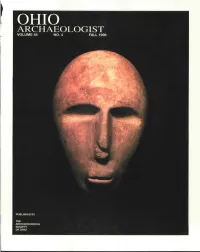
Archaeologist Volume 48 No
OHIO ARCHAEOLOGIST VOLUME 48 NO. 4 FALL 1998 PUBLISHED BY THE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY I I^^^^B & -^r"^"."^^" ?ifi™,.iTauH OF OHIO The Archaeological Society of Ohio MEMBERSHIP AND DUES Annual dues to the Archaeological Society of Ohio are payable on the first of January as follows: Regular membership $17.50; husband and wife (one TERM copy of publication) $18.50; Individual Life Membership $300. Husband and EXPIRES A.S.O. OFFICERS wife Life Membership $500. Subscription to the Ohio Archaeologist, pub 2000 President Jeb Bowen, 1982 Velma Avenue, Columbus, OH lished quarterly, is included in the membership dues. The Archaeological 43224, (419)-585-2571. Society of Ohio is an incorporated non-profit organization. 2000 Vice-President William Pickard, 1003 Carlisle Ave., BACK ISSUES Columbus, OH 43224, (614)-262-9516. Publications and back issues of the Ohio Archaeologist: 2000 Executive Secretary Charles Fulk, 2122 Cottage Street, Ash Ohio Flint Types, by Robert N. Converse $40.00 add $4.50 P-H land, OH 44805, (419)-289-8313. Ohio Stone Tools, by Robert N. Converse $ 8.00 add $1.50 P-H 2000 Recording Secretary Laurie Pahdopony, 4667 Refugee Rd., Ohio Slate Types, by Robert N. Converse $15.00 add $1.50 P-H Columbus, OH 43232. (614)-759-6344. The Glacial Kame Indians, by Robert N. Converse.$20.00 add $1.50 P-H 2000 Treasurer Gary Kapusta, 3294 Herriff Rd., Ravenna, OH 44266, 1980's& 1990's $ 6.00 add $1.50 P-H 1970's $ 8.00 add $1.50 P-H (330) 296-2287. 2006 Editor Robert N. -

An Exploration and Comparative Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public Museum Collections Kirsten Marie Mottl University of Wisconsin-Milwaukee
University of Wisconsin Milwaukee UWM Digital Commons Theses and Dissertations May 2015 Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public Museum Collections Kirsten Marie Mottl University of Wisconsin-Milwaukee Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/etd Part of the Archaeological Anthropology Commons, and the Library and Information Science Commons Recommended Citation Mottl, Kirsten Marie, "Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public Museum Collections" (2015). Theses and Dissertations. 822. https://dc.uwm.edu/etd/822 This Thesis is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. RE-EXAMINED AND RE-DEFINED: AN EXPLORATION AND COMPARATIVE ANALYSIS OF MOCHE CERAMIC VESSELS IN THE MILWAUKEE PUBLIC MUSEUM COLLECTIONS by Kirsten M. Mottl A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Anthropology at The University of Wisconsin-Milwaukee May 2015 ABSTRACT RE-EXAMINED AND RE-DEFINED: AN EXPLORATION AND COMPARATIVE ANALYSIS OF MOCHE CERAMIC VESSELS IN THE MILWAUKEE PUBLIC MUSEUM COLLECTIONS by Kirsten M. Mottl The University of Wisconsin-Milwaukee, 2015 Under the Supervision of Professor Jean Hudson For this thesis, I studied Moche ceramic vessel collections from three museums, the Milwaukee Public Museum (MPM), the Field Museum in Chicago, and the Logan Museum of Anthropology at Beloit College in Beloit, Wisconsin. -

Title 古墳時代考古学の国際化 Author(S) 佐々木,憲一 Citation 明治
Title 古墳時代考古学の国際化 Author(s) 佐々木,憲一 Citation 明治大学人文科学研究所紀要, 86: 197-228 URL http://hdl.handle.net/10291/21007 Rights Issue Date 2020-03-31 Text version publisher Type Departmental Bulletin Paper DOI https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/ Meiji University 明治大学人文科学研究所紀要 第86冊 (2020年3月31日)197-228 古墳時代考古学の国際化 佐々木 憲 一 198 ― Abstract ― Archaeology of Kofun Period Japan in the World Context SASAKI Ken’ichi The Kofun Period of proto-historic Japan(middle third to early seventh centuries, A.D.)is characterized by the widespread distribution of highly-standardized keyhole-shaped, monumental- scale mound tombs all over Japan except for Hokkaido and Ryukyu. The purposes of this paper are 1)to put the Kofun culture into the world context of mound building cultures and 2)to put the methodology of the Kofun Period archaeology into the broader perspectives of world archaeologies. To achieve the fi rst goal, the author has visited mound sites of the Hopewell and Mississippian cultures of the prehistoric North America and of the Hallstatt and La Tène cultures of Iron Age Germany. To achieve the second goal, the author has presented in English in the United States, Germany and England the results of author’s investigations into mound tombs of eastern Japan. As a result of comparison of the Kofun Period mound tombs with mound tombs in North America and Germany, the Kofun Period mound tombs should be distinguished because these monumental tombs were dedicated to a single chief or very small number of elite family. While mound tombs of a monumental scale were built in Iron Age Germany, they were results of burying a large number of individuals.