Pdf (2012 年 7 月 29 日にアクセス)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
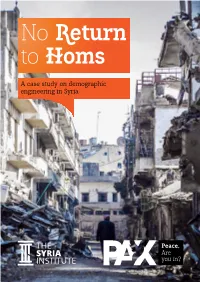
A Case Study on Demographic Engineering in Syria No Return to Homs a Case Study on Demographic Engineering in Syria
No Return to Homs A case study on demographic engineering in Syria No Return to Homs A case study on demographic engineering in Syria Colophon ISBN/EAN: 978-94-92487-09-4 NUR 689 PAX serial number: PAX/2017/01 Cover photo: Bab Hood, Homs, 21 December 2013 by Young Homsi Lens About PAX PAX works with committed citizens and partners to protect civilians against acts of war, to end armed violence, and to build just peace. PAX operates independently of political interests. www.paxforpeace.nl / P.O. Box 19318 / 3501 DH Utrecht, The Netherlands / [email protected] About TSI The Syria Institute (TSI) is an independent, non-profit, non-partisan research organization based in Washington, DC. TSI seeks to address the information and understanding gaps that to hinder effective policymaking and drive public reaction to the ongoing Syria crisis. We do this by producing timely, high quality, accessible, data-driven research, analysis, and policy options that empower decision-makers and advance the public’s understanding. To learn more visit www.syriainstitute.org or contact TSI at [email protected]. Executive Summary 8 Table of Contents Introduction 12 Methodology 13 Challenges 14 Homs 16 Country Context 16 Pre-War Homs 17 Protest & Violence 20 Displacement 24 Population Transfers 27 The Aftermath 30 The UN, Rehabilitation, and the Rights of the Displaced 32 Discussion 34 Legal and Bureaucratic Justifications 38 On Returning 39 International Law 47 Conclusion 48 Recommendations 49 Index of Maps & Graphics Map 1: Syria 17 Map 2: Homs city at the start of 2012 22 Map 3: Homs city depopulation patterns in mid-2012 25 Map 4: Stages of the siege of Homs city, 2012-2014 27 Map 5: Damage assessment showing targeted destruction of Homs city, 2014 31 Graphic 1: Key Events from 2011-2012 21 Graphic 2: Key Events from 2012-2014 26 This report was prepared by The Syria Institute with support from the PAX team. -
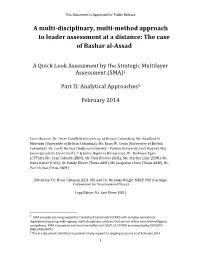
"Al-Assad" and "Al Qaeda" (Day of CBS Interview)
This Document is Approved for Public Release A multi-disciplinary, multi-method approach to leader assessment at a distance: The case of Bashar al-Assad A Quick Look Assessment by the Strategic Multilayer Assessment (SMA)1 Part II: Analytical Approaches2 February 2014 Contributors: Dr. Peter Suedfeld (University of British Columbia), Mr. Bradford H. Morrison (University of British Columbia), Mr. Ryan W. Cross (University of British Columbia) Dr. Larry Kuznar (Indiana University – Purdue University, Fort Wayne), Maj Jason Spitaletta (Joint Staff J-7 & Johns Hopkins University), Dr. Kathleen Egan (CTTSO), Mr. Sean Colbath (BBN), Mr. Paul Brewer (SDL), Ms. Martha Lillie (BBN), Mr. Dana Rafter (CSIS), Dr. Randy Kluver (Texas A&M), Ms. Jacquelyn Chinn (Texas A&M), Mr. Patrick Issa (Texas A&M) Edited by: Dr. Hriar Cabayan (JS/J-38) and Dr. Nicholas Wright, MRCP PhD (Carnegie Endowment for International Peace) Copy Editor: Mr. Sam Rhem (SRC) 1 SMA provides planning support to Combatant Commands (CCMD) with complex operational imperatives requiring multi-agency, multi-disciplinary solutions that are not within core Service/Agency competency. SMA is accepted and synchronized by Joint Staff, J3, DDSAO and executed by OSD/ASD (R&E)/RSD/RRTO. 2 This is a document submitted to provide timely support to ongoing concerns as of February 2014. 1 This Document is Approved for Public Release 1 ABSTRACT This report suggests potential types of actions and messages most likely to influence and deter Bashar al-Assad from using force in the ongoing Syrian civil war. This study is based on multidisciplinary analyses of Bashar al-Assad’s speeches, and how he reacts to real events and verbal messages from external sources. -

Safe Havens in Syria: Missions and Requirements for an Air Campaign
SSP Working Paper July 2012 Safe Havens in Syria: Missions and Requirements for an Air Campaign Brian T. Haggerty Security Studies Program Department of Political Science Massachusetts Institute of Technology [email protected] Copyright © July 15, 2012 by Brian T. Haggerty. This working paper is in draft form and intended for the purposes of discussion and comment. It may not be reproduced without permission of the copyright holder. Copies are available from the author at [email protected]. Thanks to Noel Anderson, Mark Bell, Christopher Clary, Owen Cote, Col. Phil Haun, USAF, Col. Lance A. Kildron, USAF, Barry Posen, Lt. Col. Karl Schloer, USAF, Sidharth Shah, Josh Itzkowitz Shifrinson, Alec Worsnop and members of MIT’s Strategic Use of Force Working Group for their comments and suggestions. All errors are my own. This is a working draft: comments and suggestions are welcome. Introduction Air power remains the arm of choice for Western policymakers contemplating humanitarian military intervention. Although the early 1990s witnessed ground forces deployed to northern Iraq, Somalia, and Haiti to protect civilians and ensure the provision of humanitarian aid, interveners soon embraced air power for humanitarian contingencies. In Bosnia, the North Atlantic Treaty Organization’s (NATO’s) success in combining air power with local ground forces to coerce the Serbs to the negotiating table at Dayton in 1995 suggested air power could help provide an effective response to humanitarian crises that minimized the risks of armed intervention.1 And though NATO’s -

Intra State Conflict and Violence Against Civilians
Centre for Peace Studies (CPS) Intra State Conflict and Violence Against Civilians A Study of the Syrian Civil War and the Violence Committed by the Assad Regime Against the Syrian People — Jo Myhren Rosseland Master’s thesis in Peace and Conflict Transformation… May 2017 Intra State Conflict and Violence against Civilians - A Study of the Syrian Civil War and the Violence committed by the Assad Regime against the Syrian Population. *** By Jo Myhren Rosseland Peace and Conflict Transformation 2016-2017 I Table of Contents 1 INTRODUCTION 1 1.1 AIMS AND QUESTION OF STUDY 3 1.2 RELEVANCE TO PEACE AND CONFLICT TRANSFORMATION AND MOTIVATION 4 1.3 THESIS OUTLINE 6 2 METHODS AND SOURCES 7 2.1 CASE STUDY 8 2.2 VALIDITY AND RELIABILITY 10 2.3 SCENARIO ANALYSIS AND PROCESS TRACING 10 3 THEORY AND CONTEXT 14 3.1 CONFLICT AND CONFLICT THEORY 14 3.2 CIVILIANS IN WARZONES 18 3.3 CONTEXT 20 3.4 WAR IN THE 21ST CENTURY 21 3.5 INTRA-STATE WAR 23 3.6 SYRIA AND THE ARAB SPRING 24 3.7 ETHNIC COMPOSITION OF SYRIA AND SECTARIANISM 26 4 EMPIRICAL CASE STUDY 27 PHASES OF THE SYRIAN CIVIL WAR AND ANALYTICAL PARAMETERS 30 4.1 I. DISPERSED CIVIL REVOLT - MARCH 28TH – MEDIO JUNE, 2011 31 RATIONALE 32 ACTOR TYPES 33 STRATEGIES AND TACTICS 34 RELEVANT MILITARY CAPABILITIES 34 OUTCOME 36 4.2 II. COUNTRY-WIDE CIVIL REVOLT - JUNE 2011 – MARCH 2012 37 RATIONALE 37 STRATEGIES AND TACTICS 38 RELEVANT MILITARY CAPABILITIES 39 OUTCOME 40 4.3 III. FULLY FLEDGED CIVIL WAR - MARCH 2012 – NOVEMBER 2013 40 RATIONALE 40 STRATEGIES AND TACTICS 40 RELEVANT MILITARY CAPABILITIES 42 OUTCOME 43 4.4 IV. -

The Impact of Social and Digital Media on Traditional Agenda Setting
Florida International University FIU Digital Commons FIU Graduate Research University Graduate School 2018 The mpI act of Social and Digital Media on Traditional Agenda Setting Theory in Relation to The Arab Spring Revolutions Arianna Khan Florida International University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fiu.edu/graduate-research Part of the Journalism Studies Commons, and the Mass Communication Commons Recommended Citation Khan, Arianna, "The mpI act of Social and Digital Media on Traditional Agenda Setting Theory in Relation to The Arab Spring Revolutions" (2018). FIU Graduate Research. 1. https://digitalcommons.fiu.edu/graduate-research/1 This work is brought to you for free and open access by the University Graduate School at FIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in FIU Graduate Research by an authorized administrator of FIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. THE IMPACT OF SOCIAL AND DIGITAL MEDIA ON AGENDA SETTING 1 THE IMPACT OF SOCIAL AND DIGITAL MEDIA ON TRADITIONAL AGENDA SETTING THEORY IN RELATION TO THE ARAB SPRING REVOLUTIONS By Arianna Khan Chair: Professor Jessica Matias Committee Member: Dr. Maria Elena Villar Committee Member: Aileen Izquierdo A PROFESSIONAL PROJECT PRESENTED TO THE SCHOOL OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION OF FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY [Spring 2018] THE IMPACT OF SOCIAL AND DIGITAL MEDIA ON AGENDA SETTING 2 Table of Contents 1. Abstract 2. Introduction 3. Literature Review a. The Arab Spring b. Citizen Journalists c. Gatekeepers d. Framing e. -

Shiite Foreign Militias in Syria
Shiite Foreign Militias in Syria Iran's role in the Syrian conflict and the ISIS fight By Aaron Hesse- Research Fellow August 2015 Introduction: This paper seeks to identify and elucidate the role that Iran-backed Shiite foreign fighters play in Syria and to compare how often they target the Islamic State in Iraq and Sham (ISIS) and the Syrian opposition. Shiite foreign fighters inside Syria present a major problem for the Syrian opposition forces due to their generally superior morale and fighting abilities. They also pose a long-term threat to American and Western interests due to their role in expanding the Syrian conflict and increasing its sectarian content. Many of these militias arose in Syria for the stated purpose of protecting Shiite religious shrines.i When ISIS burst onto the scene in summer 2014, the goal of fighting ISIS brutality was added on as a second ostensible purpose of the militias. However, contrary to the prevailing narrative that is based mainly on Iraq, the Iran-backed Shiite militias have been of extremely limited value in the ISIS fight in Syria. This paper will attempt to show that these groups work and perform military duties on behalf of the government of Bashar al-Assad and their benefactors in Iran almost exclusively to target the Syrian rebels. The Iran-backed militias have no real interest in fighting ISIS in Syria. This makes Assad, as well as Iran, unreliable partners in the fight to destroy ISIS. Metrics: This paper will focus on the outsized role that Iran-backed Shiite foreign fighters are playing in Syria. -

Siege Damascus: Role of Syrian Armed Forces in Its Civil
CAPS In Focus 09 Dec 2015 www.capsindia.org SIEGE DAMASCUS ROLE OF SYRIAN ARMED FORCES IN ITS CIVIL WAR Gp Capt Tanmay Sharma Senior Fellow, CAPS The civil war raging in Syria for the last Force came to play a bigger role, gradually becoming the primary military force of the four years has attained major limelight due to the Syrian state. From the early stages, the Syrian large scale deaths and human rights violations government received technical, financial, military which have forced all major countries in the and political support from Russia, Iran and Iraq. world including US, UK, France, Saudi Arabia, In 2013, Iran-backed Hezbollah entered the war Jordan, Lebanon, Iraq, Turkey and Russia to take in support of the Syrian Army1. In September up active military roles in the conflict. As per the 2015, Russia, Iraq, Iran and Syria set up a joint latest estimates, more than 250,000 Syrians have operation room (information centre) in Baghdad lost their lives and another 11 million have been to coordinate their activity in Syria. On 30 displaced from their homes as forces loyal to September 2015, Russia started its own air President Bashar al-Assad and those opposed campaign on the side and at the request of the battle each other, as well as jihadist militants government of Syria. from Islamic State. The unrest which began in the early spring of 2011 along with the Arab Syrian Arab Army Spring revolution with nationwide protests In the year 2010, International Institute for against President Bashar al-Assad's government, Strategic Studies, London estimated the army’s gradually morphed to an armed rebellion after strength at 220,000, with an additional 280,000 months of military sieges. -

Syria and the UN Security Council Dr
Global Centre for the Responsibility to Protect Occasional Paper Series No. 5, March 2015 Failure to Protect: Syria and the UN Security Council Dr. Simon Adams The Global Centre for the Responsibility to Protect was established in February 2008 as a catalyst to promote and apply the norm of the “Responsibility to Protect” populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. Through its programs and publications, the Global Centre for the Responsibility to Protect is a resource for governments, international institutions and civil society on prevention and early action to halt mass atrocity crimes. ABOUT THE AUTHOR: Dr. Simon Adams is Executive Director of the Global Centre for the Responsibility to Protect. Dr. Adams has worked extensively with governments and civil society organizations in South Africa, East Timor, Rwanda and elsewhere. Between 1994 and 2002 Dr. Adams worked with Sinn Féin and former IRA prisoners in support of the Northern Ireland peace process. He is also a former anti-apartheid activist and member of the African National Congress. Dr. Adams has written on the Responsibility to Protect as well as the ongoing conflict in Syria for the New York Times, International Herald Tribune and many other publications. Dr. Adams has also appeared as an expert commentator on Al-Jazeera, BBC, ARD (Germany), Chinese Central Television and numerous other media. He has written four books and numerous articles on issues of political conflict and mass atrocity prevention. Dr. Adams previously served as Pro Vice Chancellor at Monash University in Australia and as Vice President of its South African campus. -

Hereafter Syria Or Al-Sham Came Under the Attention of the Muslims Lead by the Prophet (Saw) Himself
1 “The [US] administration has figured out that if they don’t start doing something, the war will be over and they won’t have any influence over the combat forces on the ground. They may have some influence with various political groups and factions, but they won’t have influence with the fighters, and the fighters will control the territory.” Jeffrey White, former Defense Intelligence Agency intelligence officer and specialist on the Syrian military1 “Sunni rebels appear poised for victory. It’s vitally important for the Obama administration to discourage a new Syrian government from supplanting the secular dictatorship with a more dangerous regime based on Islamic law. Another Islamic state in the Middle East could threaten regional residents with more religious tyranny, perpetual war with neighbours and another caliphate.” Fred Gedrich, the Washington Times2 2 Content 1. Introduction………………………………………………………4 2. The Geopolitics of Syria…………………………………………7 3. Islam and Ash-Sham……………………………………………..11 4. Syria’s and the Alawi’s……………...………..………………….16 5. Syria, The Arab spring and Foreign interference…………….…..22 6. CASE STUDY: Syria’s chemical weapons…………………..….30 7. Assad’s survival strategy………………………………………...33 8. CASE STUDY: Homs siege……………………………………..38 9. The end game in Syria…………………………………………...40 10. CASE STUDY: The battle for Aleppo…………………………..48 11. Syria – the next day……………………………………………..50 12. Conclusions……………………………………………………...56 13. Notes…………………………………………………………….59 3 Introduction Russia’s deputy foreign minister Mikhail Bogdanov, admitted on December 13th 2012, what many have known for some time. Russia’s official admitted that that the Syrian government may be defeated by opposition forces as al-Assad's forces were “losing more and more control and territory.”3 The death toll in the country is now approaching 70,000 people since the conflict began.4 The revolution in Syria is has now been raging for two years. -

Hope College Abstracts: 14Th Annual Celebration of Undergraduate Research and Creative Performance Hope College
Hope College Digital Commons @ Hope College 14th Annual Celebration for Undergraduate Celebration for Undergraduate Research and Research and Creative Performance (2015) Creative Performance 4-10-2015 Hope College Abstracts: 14th Annual Celebration of Undergraduate Research and Creative Performance Hope College Follow this and additional works at: http://digitalcommons.hope.edu/curcp_14 Recommended Citation Repository citation: Hope College, "Hope College Abstracts: 14th Annual Celebration of Undergraduate Research and Creative Performance" (2015). 14th Annual Celebration for Undergraduate Research and Creative Performance (2015). Paper 1. http://digitalcommons.hope.edu/curcp_14/1 April 10, 2015. Copyright © 2015 Hope College, Holland, Michigan. This Book is brought to you for free and open access by the Celebration for Undergraduate Research and Creative Performance at Digital Commons @ Hope College. It has been accepted for inclusion in 14th Annual Celebration for Undergraduate Research and Creative Performance (2015) by an authorized administrator of Digital Commons @ Hope College. For more information, please contact [email protected]. ABSTRACTS Hope College 14th Annual Celebration of Undergraduate Research & Creative Performance 2014-2015 Arts and Humanities Welcome from the Provost 6 Art and Art History Student Presenters 7 English Abstracts 8 History Acknowledgements 13 Modern & Classical Languages 16 Music 17 Theatre Interdisciplinary 19 Mellon Scholars 26 Phelps Scholars Natural & Applied Sciences 29 Biochemistry 30 Biology 37 Chemistry 46 Computer Science 47 Engineering 51 Geological & Environmental Sciences 54 Mathematics 56 Neuroscience 57 Nursing 66 Physics Social Sciences 71 Communication 74 Economics and Business 78 Education 81 Kinesiology 88 Political Science 89 Psychology 100 Sociology April 30, 2015 DEAR FRIENDS, We were pleased to welcome more than 370 students and many, many guests to the Fourteenth Annual Celebration of Undergraduate Research and Creative Performance at Hope College. -
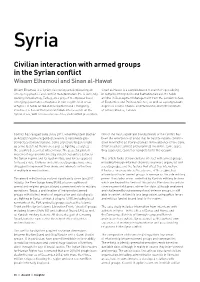
Civilian Interaction with Armed Groups in the Syrian Conflict Wisam Elhamoui and Sinan Al-Hawat
Syria Civilian interaction with armed groups in the Syrian conflict Wisam Elhamoui and Sinan al-Hawat Wisam Elhamoui is a Syrian civil society activist focusing on Sinan al-Hawat is a London-based researcher specialising emergency practice and conflict transformation. He is currently in complex emergencies and humanitarian aid. He holds working in Gaziantep, Turkey, on a project to empower local an MSc in Development Management from the London School emerging governance structures in non-regime held areas of Economics and Political Science, as well as a postgraduate of Syria. He holds an MA in Development and Emergency degree in Islamic Studies and Humanities from the Institute Practice. He has written and contributed to research on the of Ismaili Studies, London. Syrian crisis, with a focus on ceasefires and conflict prevention. Conflict has ravaged Syria since 2011, when President Bashar One of the most significant developments of the conflict has al-Assad’s regime responded severely to nationwide pro- been the emergence of areas that lie outside regime control – democracy demonstrations. Some protestors began to take often referred to as liberated areas. In the absence of the state, up arms to defend themselves and, as fighting escalated, different actors, armed and unarmed, live in the same space; the country descended into civil war. The peaceful protest they cooperate, coexist or compete to fill the vacuum. movement was overwhelmed by violent encounters between the Syrian regime and its loyal militias, and forces opposed This article looks at how civilians interact with armed groups, to Assad’s rule. Civilians and civil society groups have since including through informal channels and more organised civil struggled to represent their views and interests in the face society groups, and the factors that affect this interaction. -

SYRIA's SALAFI INSURGENTS: the Rise of the Syrian Islamic Front
Occasional #17 MARCH 2013 PUBLISHED BY THE SWEDISH INSTITUTE UIpapers OF INTERNATIONAL AFFAIRS. WWW.UI.SE SYRIA’S SALAFI INSURGENTS: THE RISE OF THE SYRIAN ISLAMIC FRONT In December 2012, eleven Syrian militant groups joined to form the Syrian Islamic Front, a powerful Islamist alliance. This report examines the structure of the Syrian insurgency, and the growing role of salafi factions within it. REPORT BY ARON LUND INDEX Introduction ...........................................................................................................3 Terminology ..........................................................................................................4 PART ONE: ISLAMISM IN SYRIA BEFORE THE UPRISING Salafism and salafi-jihadism .............................................................................5 Islamism in Syria before the uprising .............................................................7 Sectarian divisions in the Syrian revolution .................................................8 Social factors promoting the rise of salafism ..............................................9 Salafism as a response to the uprising .........................................................9 Structure of the Syrian insurgency .............................................................. 10 The rise and fall of the Free Syrian Army ...................................................11 Post-FSA bloc formation within the insurgency ...................................... 12 Salafi armed groups in Syria ........................................................................