No.13 2018 2018 目次 1 Contents
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Read an Excerpt
The Artist Alive: Explorations in Music, Art & Theology, by Christopher Pramuk (Winona, MN: Anselm Academic, 2019). Copyright © 2019 by Christopher Pramuk. All rights reserved. www.anselmacademic.org. Introduction Seeds of Awareness This book is inspired by an undergraduate course called “Music, Art, and Theology,” one of the most popular classes I teach and probably the course I’ve most enjoyed teaching. The reasons for this may be as straightforward as they are worthy of lament. In an era when study of the arts has become a practical afterthought, a “luxury” squeezed out of tight education budgets and shrinking liberal arts curricula, people intuitively yearn for spaces where they can explore together the landscape of the human heart opened up by music and, more generally, the arts. All kinds of people are attracted to the arts, but I have found that young adults especially, seeking something deeper and more worthy of their questions than what they find in highly quantitative and STEM-oriented curricula, are drawn into the horizon of the ineffable where the arts take us. Across some twenty-five years in the classroom, over and over again it has been my experience that young people of diverse religious, racial, and economic backgrounds, when given the opportunity, are eager to plumb the wellsprings of spirit where art commingles with the divine-human drama of faith. From my childhood to the present day, my own spirituality1 or way of being in the world has been profoundly shaped by music, not least its capacity to carry me beyond myself and into communion with the mysterious, transcendent dimension of reality. -
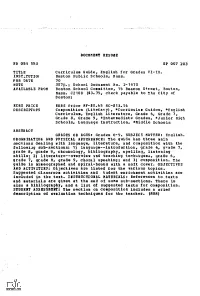
Following Sub-Sections: 1) Languageintroduction, Grade 6
DOCUMENT RESUME ED 051 153 SP 007 203 TITLE Curriculum Guide, English for Grades VI-IX. INST:aUTIO/ Boston Public Schools, Mass. PUB DATE 70 NOTE 307p.; School Document No 2-1970 AVAILABLE FROM Boston School Committee, 15 Beacon Street, Boston, Mass. 02108 ($3.75, check payable to The City of Boston) EtRS PRICE EDRS Price MF-$0.65 HC-$13.16 DESCRIPTORS Composition (Literary), *Curriculum Guides, *English Curriculum, English Literature, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, *Intermediate Grades, *Junior High Schools, Language Instruction, *Middle Schools ABSTRACT GRADES OR AGES: Grades 6-9. SUBJECT MATTER: English. ORGANIZATION AND PHYSICAL APPEARANCE: The guide has three main sections dealing with language, literature, and composition with the following sub-sections: 1) languageintroduction, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, chronology, bibliography, spelling, listening skills; 2) literature -- overview and teaching techuiguez, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, choral speaking; and 3) composition. The guide is mimeographed and spiral-bound with a soft cover. OBJECTIVES AND ACTIVITIES: Objectives are listed for the various topics. Suggested classroom activities andtudent enrichment activities are included in the text. INSTRUCTIONAL MATERIALS: References to texts and materials are given at the end of sone sub-sections. There is also a bibliography, and a list of suggested texts for composition. STUDENT ASSESSMENT: The section on composition includes a oriel description of evaluation techniques for the teacher. (MBM) .=r II PERSYSSieN TO PCPROOVCE THIS IVINP 1111111111 MATERIAL HAS BEEN GRAMM BY kg-21c.y 4-097:. elyzAre__,__ TO ERIC AND ORGANIZATIONS OPYRATING UNDER AGREEMENTS Was THE ,u$ OffiCE OF EDUCATIONFOP r'R REPFOPUCTION OUTSIDE THE ERIC ,a.'ENI REQUIRES PER MISSION CIF THE COPYRIGHT OWNER School Document No. -

5713 Theme Ideas
5713 THEME IDEAS & 1573 Bulldogs, no two are the same & counting 2B part of something > U & more 2 can play that game & then... 2 good 2 b 4 gotten ? 2 good 2 forget ! 2 in one + 2 sides, same story * 2 sides to every story “ 20/20 vision # 21 and counting / 21 and older > 21 and playing with a full deck ... 24/7 1 and 2 make 12 25 old, 25 new 1 in a crowd 25 years and still soaring 1+1=2 decades 25 years of magic 10 minutes makes a difference 2010verland 10 reasons why 2013 a week at a time 10 things I Hart 2013 and ticking 10 things we knew 2013 at a time 10 times better 2013 degrees and rising 10 times more 2013 horsepower 10 times the ________ 2013 memories 12 words 2013 pieces 15 seconds of fame 2013 possibilities 17 reasons to be a Warrior 2013 reasons to howl 18 and counting 2013 ways to be a Leopard 18 and older 2 million minutes 100 plus you 20 million thoughts 100 reasons to celebrate 3D 100 years and counting Third time’s a charm 100 years in the making 3 dimensional 100 years of Bulldogs 3 is a crowd 100 years to get it right 3 of a kind 100% Dodger 3 to 1 100% genuine 3’s company 100% natural 30 years of impossible things 101 and only 360° 140 traditions CXL 4 all it’s worth 150 years of tradition 4 all to see (176) days of La Quinta 4 the last time 176 days and counting 4 way stop 180 days, no two are the same 4ming 180 days to leave your mark 40 years of colorful memories 180° The big 4-0 1,000 strong and growing XL (40) 1 Herff Jones 5713 Theme Ideas 404,830 (seconds from start to A close look A little bit more finish) A closer look A little bit of everything (except 5-star A colorful life girls) 5 ways A Comet’s journey A little bit of Sol V (as in five) A common ground A little give and take 5.4.3.2.1. -

Nonverbal Dictionary
The The NONVERBAL DICTIONARY of GESTURES, SIGNS & BODY LANGUAGE CUES From Adam's-Apple-Jump to Zygomatic Smile By David B. Givens © 2002 (Spokane, Washington: Center for Nonverbal Studies Press) Items in this Dictionary have been researched by anthropologists, archaeologists, biologists, linguists, psychiatrists, psychologists, semioticians, and others who have studied human communication from a scientific point of view. Every effort has been made to cite their work in the text. Definitions, meanings, and interpretations left uncredited are those of the author. Gestures and consumer products with http://members.aol.com/nonverbal2/diction1.htm (1 of 2) [27/04/02 05:54:42] The current trademark registrations are identified with the ® symbol. Entries in The Dictionary. There have been many who, not knowing how to mingle the useful and the pleasing in the right proportions, have had all their toil and pains for nothing . --Cervantes (Don Quixote) Dedication "A masterful piece of work" --American Library Association "Highly recommended" --New Scientist "Very interesting reading" --The Houston Chronicle "Monumental" --Yahoo! Picks of the Week "Site of the Day Award" --WWW Virtual Library WWW Virtual Library "Best" Site © 2002 by David B. Givens, Ph.D. Center for Nonverbal Studies http://members.aol.com/nonverbal2/diction1.htm (2 of 2) [27/04/02 05:54:42] adajum ADAM'S-APPLE-JUMP Body movement. 1. A conspicuous up-and-down motion of the Adam's apple. 2. A movement of the throat visible while gulping or swallowing, as in nervousness. Usage: The Adam's-apple-jump is an unconscious sign of emotional anxiety, embarrassment, or stress. -

Lista Ofrecida Por Mashe De Forobeta. Visita Mi Blog Como Agradecimiento :P Y Pon E Me Gusta En Forobeta!
Lista ofrecida por mashe de forobeta. Visita mi blog como agradecimiento :P Y pon e Me Gusta en Forobeta! http://mashet.com/ Seguime en Twitter si queres tambien y avisame que sos de Forobeta y voy a evalu ar si te sigo o no.. >>@mashet NO ABUSEN Y SIGAN LOS CONSEJOS DEL THREAD! http://blog.newsarama.com/2009/04/09/supernaturalcrimefightinghasanewname anditssolomonstone/ http://htmlgiant.com/?p=7408 http://mootools.net/blog/2009/04/01/anewnameformootools/ http://freemovement.wordpress.com/2009/02/11/rlctochangename/ http://www.mattheaton.com/?p=14 http://www.webhostingsearch.com/blog/noavailabledomainnames068 http://findportablesolarpower.com/updatesandnews/worldresponsesearthhour2009 / http://www.neuescurriculum.org/nc/?p=12 http://www.ybointeractive.com/blog/2008/09/18/thewrongwaytochooseadomain name/ http://www.marcozehe.de/2008/02/29/easyariatip1usingariarequired/ http://www.universetoday.com/2009/03/16/europesclimatesatellitefailstoleave pad/ http://blogs.sjr.com/editor/index.php/2009/03/27/touchinganerveresponsesto acolumn/ http://blog.privcom.gc.ca/index.php/2008/03/18/yourcreativejuicesrequired/ http://www.taiaiake.com/27 http://www.deadmilkmen.com/2007/08/24/leaveusaloan/ http://www.techgadgets.in/household/2007/06/roboamassagingchairresponsesto yourvoice/ http://blog.swishzone.com/?p=1095 http://www.lorenzogil.com/blog/2009/01/18/mappinginheritancetoardbmswithst ormandlazrdelegates/ http://www.venganza.org/about/openletter/responses/ http://www.middleclassforum.org/?p=405 http://flavio.castelli.name/qjson_qt_json_library http://www.razorit.com/designers_central/howtochooseadomainnameforapree -

Barrington Bunny: Case of the Curious Clouds a Narrative Picture Book for Symbolic Play and STEM Curriculum
Bank Street College of Education Educate Graduate Student Independent Studies Spring 4-23-2020 Barrington Bunny: case of the curious clouds a narrative picture book for symbolic play and STEM curriculum Claudia Chung Bank Street College of Education, [email protected] Follow this and additional works at: https://educate.bankstreet.edu/independent-studies Part of the Curriculum and Instruction Commons, Early Childhood Education Commons, and the Educational Methods Commons Recommended Citation Chung, C. (2020). Barrington Bunny: case of the curious clouds a narrative picture book for symbolic play and STEM curriculum. New York : Bank Street College of Education. Retrieved from https://educate.bankstreet.edu/independent-studies/253 This Thesis is brought to you for free and open access by Educate. It has been accepted for inclusion in Graduate Student Independent Studies by an authorized administrator of Educate. For more information, please contact [email protected]. 1 Barrington Bunny: Case of the Curious Clouds A Narrative Picture Book for Symbolic Play And STEM Curriculum By Claudia Chung Early Childhood and Childhood General Education Faculty Mentor: Stan Chu Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of Masters of Science in Education Bank Street Graduate School of Education 2020 2 “I believe that at five we reach a point not to be achieved again and from whichever, after we at best keep and most often go down from. And so at 2 and 13, at 20 & 30 & 21 & 18 — each year has the newness of its own awareness to one alive. Alive- and life. “ — Margaret Wise Brown 3 Abstract Adults constantly use their imagination to help them visualize, problem-solve, enjoy a book, empathize, and think creatively. -

Exercise Sncos Selected for the Program Will Be Staff Sergeants and Gunnery Sergeants
HAWAIIVoluntary payment for delivery to MCASMARINE housing/$1 per four week period VOL. 10' NO. 5 KANEOHE BAY, HAWAII, FEBRUARY 4, 1981 TWENTY PAGES Fighter becomes bird of paradise No 4% ge44"1 The air station's newest Since its commissioning in MARTD's at Olathe, Kan., Dallas, to MCAS Kaneohe Bay. The memorial to Marine Corps January 1960 as an F8U -2, many Texas, and Atlanta, Ga. Chinook and its crew are assigned aviation, an F8K Crusader, bureau stations, ships and squadrons saw to the 147th Aviation Battalion, number 146973, was dedicated the F8 in their complement of After being stricken from the 25th Infantry Division, which is Commandant meets hostages Friday by Col Mel Sautter, air fighter aircraft. Among them were: "active duty" rolls in July 1974, the stationed at NAS Barbers Point station commanding officer. the Thunderbolts of Marine F8K spent five years and six and commanded by Army Maj WASHINGTON, D.C. - The commandant of the Marine The F8K, flown by Sautter at Fighter Squadron-251, at Naval months on display at NAS Barbers Dennis Cross. Corps met privately with the nine Marine returnees Jan. 27 Marine Air Reserve Training Air Station, Cubi Point in the Point's main gate, before it was and said he was pleased with their conduct. Detachment, Naval Air Station, Philippines and at Naval Air replaced by a P2V Neptune Since its arrival at MCAS "Based on preliminary official reports, I can only conclude Dallas, Texas, was assigned to Station, Atsugi, Japan; the Ghost aircraft. Kaneohe Bay, the F8K has that the discipline, leadership and professionalism of you Marine Corps and Navy Riders of Fighter Squadron-142, undergone a complete facelift. -

Pornography: Men Possessing Women
BY THESAMEAUTHORNONFICTION Woman Hating Our Blood: Prophecies and Discourses on Sexual Politics ' Right-wing Women Intercourse Letters from a War Zone: Writings 1976—1989 Pornography and Civil Rights (with Catharine A. MacKinnon) FICTION the new womans broken heart: short stories Ice and Fire PLUME Published by the Penguin G roup Penguin Books USA Inc, 375 Hudson Street, New York, New York 10014, U . S. A. Penguin Books Ltd, 27 W rights Lane, London W8 5TZ, England Penguin Books Australia Ltd, Ringwood, Victoria, Australia Penguin Books Canada Ltd, 10 Alcorn Avenue, Toronto, Ontario, Canada, M4V 3B2 Penguin Books (N. Z. ) Ltd, 182-190 W airau Road, Auckland 10, New Z e a la n d Penguin Books Ltd, Registered Offices: Harm ondsw orth, M iddlesex, England Published by Plum e, an im print of Dutton Signet, a division of Penguin Books USA Inc. This paperback edition of Pornography first published in 1989 by Dutton, an im print of Dutton Signet, a division of Penguin Books USA Inc. Published simultaneously in Canada by Fitzhenry and W hiteside, Lim ited, Toronto. Copyright © 1979, 1980, 1981 by Andrea Dworkin Introduction copyright © 1989 by Andrea Dworkin All rights reserved. Printed in the U . S. A. No part of this publication may be reproduced or transm itted in any form or by any m eans, electronic or m echanical, including photocopy, recording, or any inform ation storage and retrieval system now known or to be invented, w ithout perm ission in w riting from the publisher, except by a reviewer who wishes to quote brief passages in connection with a review written for inclusion in a magazine, newspaper, or b r o a d c a s t. -

ACCS/ACAS/IICJ 2016 Art Center Kobe, Japan Official Conference Proceedings Iafor ISSN: 2187 - 4751
The International Academic Forum ACCS/ACAS/IICJ 2016 Art Center Kobe, Japan Official Conference Proceedings iafor ISSN: 2187 - 4751 “To Open Minds, To Educate Intelligence, To Inform Decisions” The International Academic Forum provides new perspectives to the thought-leaders and decision-makers of today and tomorrow by offering constructive environments for dialogue and interchange at the intersections of nation, culture, and discipline. Headquartered in Nagoya, Japan, and registered as a Non-Profit Organization 一般社( 団法人) , IAFOR is an independent think tank committed to the deeper understanding of contemporary geo-political transformation, particularly in the Asia Pacific Region. INTERNATIONAL INTERCULTURAL INTERDISCIPLINARY iafor The Executive Council of the International Advisory Board IAB Chair: Professor Stuart D.B. Picken Mr Mitsumasa Aoyama Professor June Henton Professor Baden Offord Director, The Yufuku Gallery, Tokyo, Japan Dean, College of Human Sciences, Auburn University, Professor of Cultural Studies and Human Rights & Co- USA Director of the Centre for Peace and Social Justice Professor Tien-Hui Chiang Southern Cross University, Australia Professor and Chair, Department of Education Professor Michael Hudson National University of Tainan, Taiwan/Chinese Taipei President of The Institute for the Study of Long-Term Professor Frank S. Ravitch Economic Trends (ISLET) Professor of Law & Walter H. Stowers Chair in Law Professor Don Brash Distinguished Research Professor of Economics, The and Religion, Michigan State University College of Law Former Governor of the Reserve Bank, New Zealand University of Missouri, Kansas City Former Leader of the New National Party, New Professor Richard Roth Zealand Professor Koichi Iwabuchi Senior Associate Dean, Medill School of Journalism, Adjunct Professor, AUT, New Zealand & La Trobe Professor of Media and Cultural Studies & Director of Northwestern University, Qatar University, Australia the Monash Asia Institute, Monash University, Australia Professor Monty P. -

A Selectively Annotated Bibliography of William S
ANYTHING BUT ROUTINE: A Selectively Annotated Bibliography of William S. Burroughs v. 1.0 by Brian E. C. Schottlaender The Audrey Geisel University Librarian UC SAN DIEGO LIBRARIES 2008 ii INTRODUCTION The bibliography of William S. Burroughs is as challenging as the man was himself. He wrote voluminously and kaleidoscopically. He rearranged, recycled, and reiterated obsessively. He produced across five decades and four continents. He was a novelist, a poet, an essayist, and a correspondent at home in all media. He never met a ―little magazine‖ or an interviewer he wouldn‘t share with. There have been a few attempts at documenting the range of Burroughs‘ prodigious output over the years—some better than others. I initially conceived of this bibliography as an update of Joe Maynard‘s and Barry Miles‘ definitive William S. Burroughs: A Bibliography, 195373: Unlocking Inspector Lee‘s Word Hoard (University of Virginia, 1978). Readers familiar with Maynard and Miles (referred to herein as M&M) will know that this bibliography differs somewhat from that in scope, as it does in organization and in the kind and quantity of detail in- or excluded. These differences notwithstanding, my hope is that the two will be found to complement one another, to which end I have made a systematic effort to explicitly link the entries in Maynard and Miles to those in my own bibliography when such entries appear in both. For verification purposes, I have personally examined the great majority of items described in the bibliography. In a few instances, I have gotten by with a little help from my friends: booksellers, collectors, and librarians. -

A Study of Japanese Aesthetics in Six Parts by Robert Wilson
Dedicated to Sasa Vasic and the late Dr. Michael Marra A Study of Japanese Aesthetics in Six Parts by Robert Wilson Table of Contents Part 1: The Importance of Ma .......................................................p. 2-20 Reprinted from Simply Haiku, Winter 2011, Vol. 8, No. 3. Part 2: Reinventing The Wheel: The Fly Who Thought He Was a Carabaop.................................................................................................p. 21-74 Reprinted from Simply Haiku, Vol. 9. No. 1, Spring 2011 Part 3: To Kigo or Not to Kigo: Hanging From a Marmot’s Mouth ....................................................................................................................p. 75-110 Reprinted from Simply Haiku Summer 2011 Part 4: Is Haiku Dying?....................................................................p. 111-166 Reprinted from Simply Haiku Autumn 2011?Winter 2012 Part 5: The Colonization of JapaneseHaiku .........................p. 167-197 Reprinted from Simply Haiku Summer 2012. Part 6: To Be Or Not To Be: An Experiment Gone Awry....p 198-243 Republished from Simple Haiku, Spring-Summer 2013. Conclusion—What Is and Isn't: A Butterfly Wearing Tennis Shoes ..................................................................................................................p. 244-265 Republished from Simply Haiku Winter 2013. Study of Japanese Aesthetics: Part I The Importance of Ma by Robert Wilson "The man who has no imagination has no wings." - Muhammad Ali Every day I read haiku and tanka online in journals and see people -

Proverbs: the Power of Words Big Idea: Our Words Have the Power Of
Proverbs: The Power of Words Big Idea: Our words have the power of life or death. Purpose: To challenge people to use their words to build up & not tear down. Passage: Proverbs 16:21-28 Verse: Proverbs 18:21 Opening The words that changed the face of a nation -In 1960 Abraham Lincoln was the Republican candidate for president. At the time he was clean-shaven. That year he received a letter from an 11-year old girl named Grace Bedell. She offered him some unsolicited advice. Here is part of the letter she sent him: Dear Sir, My father has just [come] home from the fair and brought home your picture...I am a little girl only 11 years old, but want you should be President of the United States very much so I hope you won’t think me very bold to write to such a great man as you are. Have you any little girls about as large as I am if so give them my love and tell her to write to me if you cannot answer this letter. I have got 4 brother’s and part of them will vote for you any way and if you will let your whiskers grow I will try and get the rest of them to vote for you. You would look a great deal better for your face is so thin. All the ladies like whiskers and they would tease their husbands to vote for you…I will try and get everyone one to vote for you that I can…I have got a little baby sister she is nine weeks old and is just as cunning as can be.