Journals 2015.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
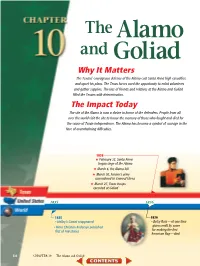
Chapter 10: the Alamo and Goliad
The Alamo and Goliad Why It Matters The Texans’ courageous defense of the Alamo cost Santa Anna high casualties and upset his plans. The Texas forces used the opportunity to enlist volunteers and gather supplies. The loss of friends and relatives at the Alamo and Goliad filled the Texans with determination. The Impact Today The site of the Alamo is now a shrine in honor of the defenders. People from all over the world visit the site to honor the memory of those who fought and died for the cause of Texan independence. The Alamo has become a symbol of courage in the face of overwhelming difficulties. 1836 ★ February 23, Santa Anna began siege of the Alamo ★ March 6, the Alamo fell ★ March 20, Fannin’s army surrendered to General Urrea ★ March 27, Texas troops executed at Goliad 1835 1836 1835 1836 • Halley’s Comet reappeared • Betsy Ross—at one time • Hans Christian Andersen published given credit by some first of 168 stories for making the first American flag—died 222 CHAPTER 10 The Alamo and Goliad Compare-Contrast Study Foldable Make this foldable to help you compare and contrast the Alamo and Goliad—two important turning points in Texas independence. Step 1 Fold a sheet of paper in half from side to side. Fold it so the left edge lays about 1 2 inch from the right edge. Step 2 Turn the paper and fold it into thirds. Step 3 Unfold and cut the top layer only along both folds. This will make three tabs. Step 4 Label as shown. -

David Crockett: the Lion of the West Rev
Rev. April 2016 OSU-Tulsa Library archives Michael Wallis papers David Crockett: The Lion of the West Rev. April 2016 1:1 Wallis’s handwritten preliminary notes, references, etc. 110 pieces. 1:2 “A Day-to-Day Account of the Life of David Crockett during the Creek Indian War. Wallis’s typed chronology, 10p. 1:3-4 “A Day-to-Day Account of the Life of David Crockett at Shoal Creek, Lawrence County.” Wallis’s typed chronology, 211p. 1:5 “A Day-to-Day Account of the Life of David Crockett at Obion River, at first in Carroll, later in Gibson and Weakly County.” Wallis’s typed chronology, 28p. 1:6 “A Day-to-Day Account of the Life of David Crockett during his time in the Congress.” Wallis’s typed chronology, 23p. 1:7 David Crockett book [proposal]. Typescript in 3 versions. 1:8 David Crockett book outline. Typescript with handwritten notations, addressed to James Fitzgerald, 5p; plus another copy of same with attached note which reads, “Yes!” addressed to James Fitzgerald, 11 Sept 2007. Version 1 1:9 Typescript of an early draft with handwritten revisions, additions, and editorial marks and comments; p1-57. 1:10 p58-113. 1:11 p114-170. Version 2 1:12 Photocopied typescript of chapters 16-28, with extensive handwritten revisions and corrections. Version 3 1:13 “Davey Crockett: The Lion of the West.” Typed cover memo by Phil Marino (W.W. Norton) with additional handwritten comments, written to an unidentified recipient, p1-4. Typed comments by Phil Marino written to Michael Wallis, p5, followed by an unedited copy of p10-144. -

Política E Identidade Norte-Americana No Filme O Álamo, De John Wayne
BRENO GIROTTO CAMPOS A Vitória dos Vencidos: Política e identidade norte-americana no filme O Álamo, de John Wayne. ASSIS 2019 BRENO GIROTTO CAMPOS A Vitória dos Vencidos: Política e identidade norte-americana no filme O Álamo, de John Wayne. Dissertação apresentada à Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Letras, Assis, para a obtenção do título de Mestre em História (Área de Conhecimento: História e Sociedade) Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Sampaio Barbosa Bolsista: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (Capes) – Código de Financiamento 001 ASSIS 2019 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Biblioteca da F.C.L. – Assis – Unesp C198v Campos, Breno Girotto A Vitória dos Vencidos : Política e identidade norte- americana no filme O Álamo, de John Wayne / Breno Girotto Campos. -- Assis, 2019 119 p. : il., tabs. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências e Letras, Assis Orientador: Carlos Alberto Sampaio Barbosa 1. Cinema. 2. História. 3. Estados Unidos. 4. Década de 1960. 5. Guerra Fria. I. Título. Agradecimentos Neste processo árduo que é a produção acadêmica não teria conseguido chegar onde cheguei sem as instituições e pessoas que quero agradecer aqui. Em primeiro lugar quero agradecer ao professor Carlos Alberto Sampaio Barbosa, que me acompanha desde a ideia inicial desta pesquisa em 2014 e que as sugestões e correções são inestimáveis para meu crescimento como pesquisador. Em seguida gostaria de agradecer aos professores Mary Anne Junqueira e José Luis Bendicho Beired, cujas leituras, correções e sugestões também foram de importância ímpar para minha pesquisa e para mim como indivíduo. -

"James Bowie", a Hero of the Alamo
F 390 .B85 Copy 1 Jli Willi m^ ^*'i?j^-^ '''' ' ,(>', V'. > ^^/* ':''<^^^":'>^' ^60 JAMES BOWIE "JAMES BOWIE" A HERO OF THE ALAMO BY EVELYN BROGAN AUTHOR OF ••The Old Spanish Trail." SAN ANTONIO. TEXAS Theodore Kunzman"<,^^»l Printer & Publisher 1922 COPYRIGHT 1922 BY EVELYN BROGAN ALL RIGHTS RESERVED FEB 14 72 ©C1A656775 TO The Heroes of the Alamo. PREFACE. James Bowie, a hero of the Alamo, and one of the most noted characters not only of Texas but of the United States, was born in South Carolina in 1805 of pioneer American parents. While still a child they moved to New Orleans and there James Bowie grew to manhood. The famous "Bowie Knife" received its name from James Bowie. He or his brother (Rezin Bowie) was the inventor of it. Love of adventure, so strong in youths of the pioneer age, mani- fested itself in James Bowie and he came to Texas, then a Mexican state, about 1828. He spent much fruitless time in searching for the famous silver mine chronicled in the old Spanish Records, as being located near the site of the former San Saba Mission. Failing to find the mine, he settled in San Antonio de Bexar, where he mar- ried Miss Ursula de Veramendi^ the daughter of Vice Governor Juan Martin de Veramendi, of Texas. Their beautiful home, the Vera- mendi Palace located on Soledad Street, was the center of Spanish hospitality and culture in the early days of San Antonio. The fam- ous old Veramendi Palace has since been torn down to make room for a modern building much to the regret of tourists and loyal citi- zens of old San Antonio. -

Farmer Finds Niche
LOCAL ELECTRIC COOPERATIVE EDITION MARCH 2010 COUNT ME IN! BUILDING SAND CASTLES SEEDSSEEDS ofof CHANGECHANGE FARMER FINDS NICHE March 2010 VOLUME 67 NUMBER 9 FEATURES 6 Count Me In! By Staci Semrad 2010 census data will determine how more than $400 billion per year in federal funding is distrib- uted to local and state governments. 10 Seeds of Change FARMER FINDS NICHE Story and Photos by Jody Horton Part two in our three-part series about Texas farm families 16 Sand Dollars By Eileen Mattei Photos by Brad Doherty Sand Castle Days on South Padre Island and Texas SandFest in Port 10 Aransas lure champion sand sculp- tors from across the United States. FAVORITES Footnotes by Clay Coppedge Moses Rose 31 Recipe Roundup A Guide to Cooking Greener 32 Focus on Texas Backyard Gardens 43 Around Texas Local Events Listings 44 31Hit the Road by Camille Wheeler El Camino del Rio 46 31 32 46 16 TEXAS ELECTRIC COOPERATIVES BOARD OF DIRECTORS: Darren Schauer, Chair, Gonzales; Kendall Montgomery, Vice Chair, Olney; Rick Haile, Secretary-Treasurer, McGregor; Steve Louder, Hereford; Billy Marricle, Bellville; Mark Stubbs, Greenville; Larry Warren, San Augustine PRESIDENT/CEO: Mike Williams, Austin Texas Co-op Power is published by your STRATEGIC COMMUNICATIONS ADVISORY COMMITTEE: Bill Harbin, Chair, Floydada; Gary Nietsche, La Grange; electric cooperative to enhance the qual- Roy Griffin, Edna; Bryan Lightfoot, Bartlett; Melody Pinnell, Crockett; Anne Vaden, Corinth; William “Buff” Whitten, Eldorado ity of life of its member-customers in an COMMUNICATIONS STAFF: Martin Bevins, Sales Director; Carol Moczygemba, Executive Editor; Kaye Northcott, Editor; Charles Boisseau, Associate Editor; Suzi Sands, Art Director; Karen Nejtek, Production Manager; Ashley Clary, Field Editor; Andy educational and entertaining format. -

Moses Rose of Texas
Traditional & Folk Songs with lyrics & midi music www.traditionalmusic.co.uk Moses Rose of Texas Moses Rose of Texas (Stephen L. Suffet; music trad) He's Moses Rose of Texas, And today nobody knows, He's the one who left the Alamo, The night before the foe, Came storming up across the walls, And killed the men inside, But Moses Rose of Texas, Is the one who never died. When gallant Colonel Travis, Drew a line down in the sand, Everyone stepped over, But one solitary man. They called him Rose the Coward, And they called him Yellow Rose, But it takes bravery to stand alone, As God Almighty knows. He said, "I'm not a coward, I just think it isn't right, For me to throw my life away, In someone else's fight. I have no quarrel with Mexicans, Nor with the Texans, too." So Moses Rose of Texas, He bade the men adieu. Whenever you are up against, Pressure from your peers, Or a challenge to your manhood, Or frightened by the jeers, Remember that discretion, Is valor's better part, And let the life of Moses Rose, Put courage in your heart. So shed a tear for Travis, And Davy Crockett, too, And cry for old Jim Bowie, Visit www.traditionalmusic.co.uk for more songs. They saw the battle through. But when you're finished weeping, And you're finished with your wail, Then give a grin for Moses Rose, Who lived to tell the tale! This song tells the true story of the one man at the Alamo who left the night before the final battle. -

Congressional Record United States Th of America PROCEEDINGS and DEBATES of the 111 CONGRESS, FIRST SESSION
E PL UR UM IB N U U S Congressional Record United States th of America PROCEEDINGS AND DEBATES OF THE 111 CONGRESS, FIRST SESSION Vol. 155 WASHINGTON, THURSDAY, MARCH 5, 2009 No. 39 House of Representatives The House met at 10 a.m. and was Pursuant to clause 1, rule I, the Jour- impact that women have on our coun- called to order by the Speaker pro tem- nal stands approved. try. pore (Mr. PASTOR of Arizona). f Over the last century, we have made f considerable progress. However, our PLEDGE OF ALLEGIANCE work to ensure that women have equal DESIGNATION OF THE SPEAKER The SPEAKER pro tempore. Will the rights and protection from assault and PRO TEMPORE gentlewoman from California (Ms. LO- abuse are not over. Today, women con- The SPEAKER pro tempore laid be- RETTA SANCHEZ) come forward and lead tinue to bring home smaller paychecks fore the House the following commu- the House in the Pledge of Allegiance. than men do for doing the same job. nication from the Speaker: Ms. LORETTA SANCHEZ of Cali- However, I am proud that this Congress passed and President Obama recently WASHINGTON, DC, fornia led the Pledge of Allegiance as March 5, 2009. follows: signed the Lilly Ledbetter Fair Pay I hereby appoint the Honorable ED PASTOR I pledge allegiance to the Flag of the Act of 2009 to help end pay discrimina- to act as Speaker pro tempore on this day. United States of America, and to the Repub- tion against women. NANCY PELOSI, lic for which it stands, one nation under God, Currently, there are an estimated Speaker of the House of Representatives. -

K-8 Alamo and Texas Revolution Bibliography
THE ALAMO AND THE TEXAS REVOLUTION An Annotated Bibliography for Parents and Teachers Kindergarten through Grade 8 Compiled by Charles Tucker, Reference Librarian Daughters of the Republic of Texas Library at the Alamo San Antonio, Texas Revised February 2010 This bibliography is intended to be a guide for parents and teachers who are teaching the history of the Alamo and the Texas Revolution. Books are the only media contained in the list, and most of them were published between 1995 and 2004. Currently available, in-print books are the focus of the bibliography; out-of-print books are included when a topic is not covered by an in-print equivalent. Features that may be of use to teachers are indicated and points that may distract from the study of history are mentioned. Fiction Beller, Susan Provost, The Siege of the Alamo: Soldiering in the Texas Revolution (Soldiers on the Battlefront). Minnesota: Twenty-First Century Books., c2008. 112p: hardcover library binding ISBN 0-8225-6782-2 $33.26. Reading level ages 9-12 Only three weeks after U.S. soldier Jim Bowie wrote these words, Mexican president and general Antonio Lopez de Santa Anna and his six thousand troops arrived at the fort known as the Alamo to assert their control over the Texan colonists who had settled in Mexican territory. About 260 colonists had holed up to fight for independence from Mexico. Author Susan Provost Beller brings the conflict of these to groups to life with first-person accounts and stories that detail what conditions were like at the fort and what happened on March 6, when the Mexicans attacked. -

Remembering Davy Crockett: an Unabridged Play Written & Revised by David Joseph Marcou
©2013 COPYRIGHT FOR THIS WORK IS HELD BY DAVID J. MARCOU CREDIT MUST BE GIVEN TO DAVID J. MARCOU AS AUTHOR AND PLAYWRIGHT Remembering Davy Crockett: An Unabridged Play Written & Revised by David Joseph Marcou. Copyright 2007-2013+, David Joseph Marcou. The World-Debut of DJM's Abridged Version of RDC Was Performed as a Community Event by the Mercury Matthews Players, Fri.-Sat., April 20-21, 2012, 7 PM, Aquinas Schools' Campbell Theatre, La Crosse, WI. For our troupe's extended family & audiences, & the memory of Davy Crockett & Charlie Casberg. Starring: Steve Kiedrowski as Davy's Old-Friend. Playwright, Director, & Producer: David Joseph Marcou (CEO, Mercury Matthews Players). Narrator & Assistant Director: Rourke Decker. Newsboy: Danny Skifton. Sally: Katherine Gentner. Singers: Claire Olson & Nina Newton. Script-Consultants: Steve Kiedrowski & Rourke Decker. Lighting and Sound Technician: Paul McGettigan. Set Design: Mark, Jean, & Bobbie Smith, & Steve & Deborah Olson. Costume Design: Steve & Deborah Olson, Steve Kiedrowski, & Cast. Aquinas Schools (AS) Principal: Ted Knutson. AS Custodial Staff: Craig Lysne & Dan Kammel. AS Admin. Staff, Especially Kurt Nelson, Rudy Nigl, Stephen Murray, & Christine Gongaware. AS Theatre Director: Peter Bosgraaf. AS Technology Teacher: Paul Callan. Production Assistants: Mary & Kate Temp, & the Decker Family. Business Advisers: David A. and Rose C. Marcou. Poster/Program Printing: Insty-Prints of La Crosse, WI. Books' Printing & Binding: DigiCOPY of La Crosse, WI. Sponsors: Bp. William Callahan & the La Crosse Diocese; Patrick Stephens & Irishfest-La Crosse; Rev. Roger Scheckel; Matthew A. Marcou, Jessica Amarnek; Dennis A. Marcou & Polly Smith; Dan & Vicki Marcou; Tom & Joy Marcou; Diane & Robert “Rocky” Skifton; Lynn Marcou & Tyler Sattler; Mary & Kate Temp & Paul Frederick; Charles & Christine Freiberg; Prof. -

ETHJ Vol-25 No-1
East Texas Historical Journal Volume 25 Issue 1 Article 1 3-1987 ETHJ Vol-25 No-1 Follow this and additional works at: https://scholarworks.sfasu.edu/ethj Part of the United States History Commons Tell us how this article helped you. Recommended Citation (1987) "ETHJ Vol-25 No-1," East Texas Historical Journal: Vol. 25 : Iss. 1 , Article 1. Available at: https://scholarworks.sfasu.edu/ethj/vol25/iss1/1 This Full Issue is brought to you for free and open access by the History at SFA ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in East Texas Historical Journal by an authorized editor of SFA ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. VOLUME XXV 1987 NUMBER 1 EA TTEXA . HISTORICAL JOURNAL EAST TEXAS HISTORICAL ASSOCIATION OFFICERS Joe L. White President Mrs. Virginia Long First Vice President Gwin Morris Second Vice President Ms. Tommie Jan Lowery Treasurer DIRECTORS Melvin Mason Huntsville 1987 Ms. Marilyn Rhinehart Houston 1988 Ron Hufford Lufkin 1988 Lincoln King , ..Gary 1988 Mike Kingston Dallas 1988 Bill O'Neal Carthage 1989 Naaman Woodland Beaumont 1989 Gladys Meisenheimer Jefferson 1989 Jewel Cates Dallas .ex-President William J. Brophy Nacogdoches ex-President F. Lee Lawrence Tyler Director Emeritus William R. Johnson Nacogdoches ex-officio James V. Reese Nacogdoches ex-officio EDITORIAL BOARD Valentine J. Belfiglio Garland Bob Bowman Lufkin Gama L. Christian Houston Ouida Dean Nacogdoches Patricia A. Gajda Tyler Robert L. Glover Tyler Bobby H. Johnson Nacogdoches Patricia Kell Baytown Max S. Lale , Fort Worth Irvin M. May, Jr Bryan Bill O'Neal " Carthage Chuck Parsons South Wayne, WI Fred Tarpley Commerce Archie P. -

ETHJ Vol-10 No-1
East Texas Historical Journal Volume 10 Issue 1 Article 1 3-1972 ETHJ Vol-10 No-1 Follow this and additional works at: https://scholarworks.sfasu.edu/ethj Part of the United States History Commons Tell us how this article helped you. Recommended Citation (1972) "ETHJ Vol-10 No-1," East Texas Historical Journal: Vol. 10 : Iss. 1 , Article 1. Available at: https://scholarworks.sfasu.edu/ethj/vol10/iss1/1 This Full Issue is brought to you for free and open access by the History at SFA ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in East Texas Historical Journal by an authorized editor of SFA ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. EAST TEXAS HISTORICAL ASSOCIATION OFFICERS Robert Co Cotner. President .N acol;doche~ MI'!l. W. S. Terry, Fif'il Vice·Prcsident Jeffer:son Rnlf 000<1\\ in. Second Vice-Prc~idenl .Austin Mr-.. Tommie Jan lowery.• cretary Lufl.in DIREOTORS Term Expire., Mrs. E. H. las..eler ... Henderson .......1971 R"lph Sleen ...Nacogdo hee; 1971 Robert C. Cotnel ............Austin ........... _.... .1972 Ron.ald Elli..on ............._ Beuumont ..........._.... ... 197::! Mallry Darst .. .......................,Galveston .. ..........................1972 Lce Lawrence Tyler .. .. __ .1973 F. 1. Tucker Nacogdoches . __ __ 1973 Mrs. W. H. Hridp:e'l Roganville .... __ . 1973 • EDITORIAL BOARD Archie P. McDonald. Editor·in·Chief Nacogdoche<.; Ralph Goodwin . ... Commerce Jame!l L. Nichol... .. ...Nacogdoches f\lrs. ("harlc.. lartin Kirbyville John Payne. Jr. Huntsville L. Ralph A Woo<,tcr Beaumonl ; FAlITORIAL ADVISORY BOARD \lIan Ashcluft Bryan Kobert Glover ... Tyler Franl.. Jacbon . Commerce MEMBERS" ••' PATRONS contribute to the work of the A~..ociation ~IOO or more, payable if def\ll'ed ~er a penIXI of five years. -

ETHJ Vol-9 No-2
East Texas Historical Journal Volume 9 Issue 2 Article 1 10-1971 ETHJ Vol-9 No-2 Follow this and additional works at: https://scholarworks.sfasu.edu/ethj Part of the United States History Commons Tell us how this article helped you. Recommended Citation (1971) "ETHJ Vol-9 No-2," East Texas Historical Journal: Vol. 9 : Iss. 2 , Article 1. Available at: https://scholarworks.sfasu.edu/ethj/vol9/iss2/1 This Full Issue is brought to you for free and open access by the History at SFA ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in East Texas Historical Journal by an authorized editor of SFA ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. VOLUME IX 1971 NUMBER II EAST TEXAS HISTORICAL ASSOCIATIO Oll'FlCEB8 James L. Nichols, Pre5ident . Nacogdoches Mrs. W. S. Terry, First Vice·Pre!iident Jefrerson Robert C. Cotner, Second Vice-President _...Austin Mrs. Tommie Jan Lowcry, Secretary __ _ _._ .._ Lulkin DIBDJTOII8 T~rm Expiru Mrs. E. H. Lasset.r H.nd.rson 1971 R.lph 5 n _ _ N.cogdoches ...........•............•.........1971 Robert C. Cotner .. ..•..................•.......Austin ...•......_..............................•... 1972 Ronald Ellison __ . ._ _._.._ 8eaumont _ _ _ _._._.1972 Maury Darst _ _._ __ ..GalYeston ..•.............__ _ 1972 Lee Lawrence _ Tyier _.._._1973 F. J. Tuck.r ...........•......_.._ N.cogdoch.s _._ 1973 MI'. W. H. Brid Roa.nviJI. 1973 C. K. Chamberlain, Editor-in-Chief _..__.._ . acoldocbes Ralph Goodwin _ _ __ __ _.._ Commerce J&JneI L. Nicbols _ Nacogdoches Mn.