Iso/Iec Jtc1の構成
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
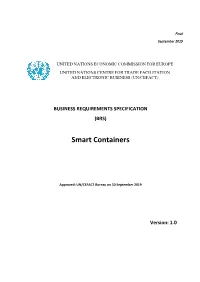
Smart Container Business Requirements Specifications (BRS)
Final September 2019 UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE UNITED NATIONS CENTRE FOR TRADE FACILITATION AND ELECTRONIC BUSINESS (UN/CEFACT) BUSINESS REQUIREMENTS SPECIFICATION (BRS) Smart Containers Approved: UN/CEFACT Bureau on 30 September 2019 Version: 1.0 1. Introduction The aim of this document is to define the data elements required for a Smart Container Solution. First, we will detail use cases to share a common understanding of the potential of the Smart Container Solutions and then derive the data elements. We will use the existing data elements of the UN/CEFACT Core Components Library (CCL), in particular, the Multi-Modal Transport (MMT) subset, a.k.a. the MMT Reference Data Model. Whenever new data elements are needed, they will be included in the CCL and the MMT subset. Depending on the use case, a different set of data elements may need to be transmitted to satisfy its Smart Container Solution. The use cases are prioritized and organized accordingly. The sum of all data elements for all use cases would provide all data that may be required in any message format used within the context of Smart Container Information Exchanges. The aim of this work is to define only WHAT may be exchanged among stakeholders and not the HOW this information may be exchanged (e.g. EDI, API, EPCIS). The message exchanged will contain only a subset of “the sum of all data elements”. Data governance and roles/credentials-based access to the smart containers’ data elements are part of the terms of contracts in place between the smart containers’ service providers and the logistic chain stakeholders. -

Definition of Object-Oriented FRBR
FRBR object-oriented definition and mapping from FRBRER, FRAD and FRSAD Document Type: Current Editorial Status: In Progress since [5/4/2017] Version 3.0 September 2017 International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation Supported by Delos NoE Editors: Chryssoula Bekiari Martin Doerr Patrick Le Bœuf Pat Riva Contributors: Trond Aalberg, Jérôme Barthélémy, Chryssoula Bekiari, Guillaume Boutard, Martin Doerr, Günther Görz, Dolores Iorizzo, Max Jacob, Carlos Lamsfus, Patrick Le Bœuf, Mika Nyman, João Oliveira, Christian Emil Ore, Allen H. Renear, Pat Riva, Richard Smiraglia, Stephen Stead, Maja Žumer, and others November 2015 Index INDEX ............................................................................................................................................... 2 FOREWORD ................................................................................................................................. 109 1. INTRODUCTION ..................................................................................................................... 1110 1.1. Purposes .................................................................................................................................................... 1110 1.1.1. A Common View of Cultural Heritage Information .......................................................................... 1211 1.1.2. A Verification of FRBR’s Internal Consistency ................................................................................ 1211 1.1.3. An Enablement of Information -

Intelligent Transport Systems — Freight Land Conveyance Content Identification and Communication — Part 2: Application Interface Profiles
This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-915851 INTERNATIONAL ISO STANDARD 26683-2 First edition 2013-02-15 Intelligent transport systems — Freight land conveyance content identification and communication — Part 2: Application interface profiles Systèmes intelligents de transport — Identification et communication du contenu des marchandises transportées par voie terrestre — Partie 2: Profils d’interface d’application Reference number ISO 26683-2:2013(E) © ISO 2013 This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-915851 ISO 26683-2:2013(E) COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT © ISO 2013 All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form orthe by requester. any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of ISOTel. copyright+ 41 22 749 office 01 11 CaseFax + postale 41 22 749 56 •09 CH-1211 47 Geneva 20 Web www.iso.org E-mail [email protected] Published in Switzerland ii © ISO 2013 – All rights reserved This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-915851 ISO 26683-2:2013(E) Contents Page Foreword ........................................................................................................................................................................................................................................iv -

Though There Are Some Standards Listed Below Available for Free, Many of the Documents in This List Are Addenda, Erratum Or Corrigenda
Though there are some standards listed below available for free, many of the documents in this list are addenda, erratum or corrigenda. Title Abstract AAMI Standards Program National and Internation NONE Guidance for ANSI/AAMI/ISO 11607, Packaging for terminally sterilized medic Amendment 1 to ANSI/AAMI EC53:1995, AmericanNONE N Enteral feeding set adapters and connectors Specifies safety requireme Erratum- Active implantable medical devices - Electromagnetic compatibility - Underground dielectric optical fiber cable [T Especifica os requisitos m Educational Information About Carbon Monoxide This technical information Certified Ratings Program - Product Rating Manual The program applies to aco Certified Ratings Program Operating Manual (Rev. The purpose of the AMCA In Laboratory Accreditation Program The purpose of the AMCA La Certified Ratings Program - Product Rating ManualThe purpose of this manual Certified Ratings Program - Product Rating Man The purpose of the program Certified Ratings Program - Product Rating Manua The purpose of this manual Certified Ratings Program - Product Rating ManualThis publication is an exte The Financial Impact of Cyber Security - Questio <p><i>The Financial Impac The Financial Management of Cyber Risk: An Imp <p><i> The Financial Mana IDSP Workshop Report: Identity Verification Identity Verification, a wo IDSP Workshop Report: Measuring Identity Theft Measuring Identity Theft, Forced-Circulation Air-Cooling and Air-Heating Coils - Addendum 1 Erratum - American National Standard Technical InfNONE Technical -
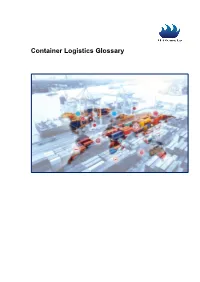
Container Logistics Glossary
Container Logistics Glossary J&S Maritime Ltd J&S Maritime provide generic and bespoke training to stakeholders in the container terminal sector. They offer a unique blend of industry experience, applied knowledge and conceptual insight supported by academic rigour. Excelling in interactive classroom delivery and engaging eLearning courses through NowLearn.net they deliver best in class training content that engages attendees whether they are new to the industry or have decades of experience. Dr Jeff Martin Jeffrey Martin graduated with a BSc Honours degree in Maritime Studies and was awarded a PhD from the University of Wales for his research on strategic relationships in container terminal communities. He has over 25 years of international experience in the industry including periods in export shipping, project finance, software development and business consultancy. Jeffrey has a particular interest in terminal automation and in the education of port workers and frontline managers. He works with many global companies in the container sector delivering operational, management and executive training on behalf of terminal operators, technology providers and consultancy firms. For further details, visit: linkedin.com/in/jeffreymartin Dr Sally Martin Sally Martin is a co-founder of J&S Maritime Ltd and is a Professor at the Department of International Logistics, Chung-Ang University, Korea specializing in land transport and logistics. On graduating with a BSc Honours degree in International Transport she undertook at a PhD at the University of Wales assessing the potential for rail freight in the UK. Following 15 years in industry where she became Chief of Staff to a major UK engineering company supplying the offshore oil and gas sector she returned to academia in 2011. -

ISO 9897 Chassis Standard
© ISO 2014 – All rights reserved ISO/TC 104/SC 04 Date: 2014-08-5 ISO/DIS 9897-5 ISO/TC 104/SC 04/WG 03 Secretariat: ANSI Freight containers — Container equipment data exchange (CEDEX) — Part 5: General communictaion codes for chassis Conteneurs pour le transport de merchandises — Échange de données sur les équipements de conteneurs (CEDEX) — Partie 5: Codes des communications générales pour châssis Warning This document is not an ISO International Standard. It is distributed for review and comment. It is subject to change without notice and may not be referred to as an International Standard. Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation. Document type: International Standard Document subtype: Document stage: (40) Enquiry Document language: E H:\Abteilungs Archiv\Geschichtsakte FAKRA-Normen\Normen_05001-10000\09897\Part 5\03_DIS und FDIS\ISO_9897-5_(E) 2014-08-05.doc STD Version 2.5a ISO/DIS 9897-5 Copyright notice This ISO document is a Draft International Standard and is copyright-protected by ISO. Except as permitted under the applicable laws of the user's country, neither this ISO draft nor any extract from it may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission being secured. Requests for permission to reproduce should be addressed to either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester. ISO copyright office Case postale 56 CH-1211 Geneva 20 Tel. -

ISO 9897:1997 9D60e4ac5163/Iso-9897-1997
INTERNATIONAL ISO STANDARD 9897 First edition 1997-12-15 Freight containers — Container equipment data exchange (CEDEX) — General communication codes É Conteneurs pour le transport de marchandises — change de données sur les équipements de conteneurs (CEDEX) — Codes des communications iTeh SgénéralesTANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai) ISO 9897:1997 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d219e043-3e7d-476f-9c77- 9d60e4ac5163/iso-9897-1997 r A Reference numbe ISO 9897:1997(E) ISO 9897:1997(E) Contents Page 1 Scope................................................................................ 1 2 Normative references ................................................................ 1 3 Principle..................................................................................... 1 4 Data elements and codes............................................................ 2 Annexes A Codes — Message types ............................................................ 4 B Codes — Structural condition, repair condition, outside coating, inside coating, full/empty indicator................................................ 5 C Codes — Damage location.......................................................... 6 D Codes — Damage typesi .............................................................Teh STANDARD PRE14VIEW E Codes — Material types ..............................................................(standards.iteh.a17i) F Codes — Repair type ................................................................... 19 ISO 9897:1997 G Codes — Measure -

Container Equipment Data Exchange (CEDEX) — Part 1: General Communication Codes for General Purpose Containers
© ISO 2014 – All rights reserved ISO/TC 104/SC 04 Date: 2014-08-05 ISO/DIS 9897-1 ISO/TC 104/SC 04/WG 03 Secretariat: ANSI Freight containers — Container equipment data exchange (CEDEX) — Part 1: General communication codes for general purpose containers Conteneurs pour le transport de merchandises — Échange de données sur les équipements de conteneurs (CEDEX) — Partie 1: Codes des communications générales Warning This document is not an ISO International Standard. It is distributed for review and comment. It is subject to change without notice and may not be referred to as an International Standard. Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation. Document type: International Standard Document subtype: Document stage: (40) Enquiry Document language: E H:\Abteilungs Archiv\Geschichtsakte FAKRA-Normen\Normen_05001-10000\09897\Part 1\03_DIS und FDIS\ISO_DIS 9897-1_(E) 2014-08-05.doc STD Version 2.5a ISO/DIS 9897-1 Copyright notice This ISO document is a Draft International Standard and is copyright-protected by ISO. Except as permitted under the applicable laws of the user's country, neither this ISO draft nor any extract from it may be repro- duced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission being secured. Requests for permission to reproduce should be addressed to either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester. ISO copyright office Case postale 56 CH-1211 Geneva 20 Tel. -

Design of a Two Story Iso Shipping Container Building
DESIGN OF A TWO STORY ISO SHIPPING CONTAINER BUILDING By Mohammad Ataei B.Eng, IAUTCB, Tehran, Iran 2016 A MRP presented to Ryerson University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Engineering in the program of Civil Engineering Toronto, Ontario, Canada, 2019 © Mohammad Ataei, 2019 Author's Declaration I hereby declare that I am the sole author of this MRP. This is a true copy of the MRP, including any required final revisions. I authorize Ryerson University to lend this MRP to other institutions or individuals for the purpose of scholarly research. I further authorize Ryerson University to reproduce this MRP by photocopying or by other means, in total or in part, at the request of other institutions or individuals for the purpose of scholarly research. I understand that my MRP may be made electronically available to the public. ii Abstract DESIGN OF A TWO STORY ISO SHIPPING CONTAINER BUILDING by Mohammad Ataei Master of Engineering Civil Engineering Ryerson University, Toronto, Canada 2019 A container home offers a fast, green, and sustainable approach to building because of its standardized and reliable factory-controlled manufacturing. In this regards, this report investigates the data available in the literature and the strength assessment of ISO shipping container and then goes into the application evaluation of ISO container for temporary and permanent housing options. Real project as a case study has been investigated and all the detailing sheets have been performed. Finally, the conclusion chapter highlights the overall opinion of the author, some suggestions for the ISO container designers and the design challenges which any designer could be faced with. -

E-STUDIO556/656/756/856 1 Ver10 08 Setting Mode
e-STUDIO556/656/756/856 Sub- Default Acceptable Proc 05/08 Mode Element Sub Element Item Subitem Code Details RAM Contents ServiceUI Code value value edure 08 Setting ProcessFuser 2002Fuser unit counter 0 0~29M 0: No error 1: C411 2: C412 3: C443 4: - 5: 1 mode C445/465 6: C446/466 7: C447/467 8: C468 9: C449 10: C475 11: C471 12: C472 13: C473 14: C481 15: C480 16: C474 17: C490 18: C468 19: C449 20: C468 21: C449 22: C449 23: C449 24: C447/C467 25: C449 26: C468 27: C449 28: C468 29: C449 08 Setting Process Fuser 2009Fuser roller temperature at Refer to 0~14M 0: 140°C 1: 145°C 2: 150°C 3: 155°C 4: 160°C 5: 1 mode ready status contents 165°C 6: 170°C 7: 175°C 8: 180°C 9: 185°C 10: 190°C 11:195°C 12: 200°C 13:205°C 14: 210°C <Default value> e-STUDIO556 UC, EUR: 12 e-STUDIO656 JPC: 9 UC, EUR: 12 e-STUDIO756/856 JPC: 12 UC, EUR: 12 08 Setting Process Fuser 2010Fuser roller temperature 120~14M 0: 140°C 1: 145°C 2: 150°C 3: 155°C 4: 160°C 5: 1 mode during printing(Plain paper) 165°C 6: 170°C 7: 175°C 8: 180°C 9: 185°C 10: 190°C 11:195°C 12: 200°C 13:205°C 14: 210°C 08 Setting Process Fuser 2028Fuser roller temperature 120~14M 0: 140°C 1: 145°C 2: 150°C 3: 155°C 4: 160°C 5: 1 mode during printing(Thick paper 165°C 6: 170°C 7: 175°C 8: 180°C 9: 185°C 10: 3) 190°C 11:195°C 12: 200°C 13:205°C 14: 210°C 08 Setting Process Fuser 2031Pre-running time for first 0 0~15M 0: Invalid 1: 1 sec. -
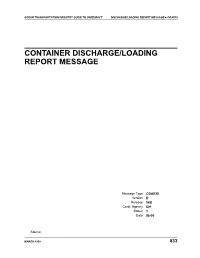
Ocean Transportation Industry Guide to Un/Edifact Discharge/Loading Report Message • Coarri
OCEAN TRANSPORTATION INDUSTRY GUIDE TO UN/EDIFACT DISCHARGE/LOADING REPORT MESSAGE • COARRI CONTAINER DISCHARGE/LOADING REPORTCOARRICONTAINER • CONTAINER DISCHARGE/LOADING DISCHARGE/LOADING REPORT MESSAGE REPORT MESSAGE • COARRI MESSAGE This message is used by container terminals and stevedores to report to ocean carriers or their agents that the specified containers have been loaded or discharged from a vessel as ordered. Also overlanded and/or shortlanded containers are reported through this message. Message Type COARRI Version D Release 98B Contr. Agency UN Status 1 Date 98-09 Source MARCH 1999 833 DISCHARGE/LOADING REPORT MESSAGE • COARRI OCEAN TRANSPORTATION INDUSTRY GUIDE TO UN/EDIFACT 834 MARCH 1999 OCEAN TRANSPORTATION INDUSTRY GUIDE TO UN/EDIFACT DISCHARGE/LOADING REPORT MESSAGE • COARRI 98OCENCONTAINERJA NUARY • COARRI14, DISCHARGE/LOADING 1999 REPORT MESSAGE COARRI Container discharge/loading report message Comments 1. This message is used by container terminals and stevedores to report to ocean carriers or their agents that the specified containers have been loaded or discharged from a vessel as ordered. Also overlanded and/or shortlanded containers are reported through this message. 2. The implementation is basically as per SMDG recommendation but modified to comply with the ITIGG Principles & Rules. Table 1 USAGE PAGE # SEG. ID NAME REQ. DES. MAX USE GROUP REPEAT M 837 UNH Message header M1 M 838 BGM Beginning of message M1 R 840 DTM Date/time/period C9 O 841 FTX Free text C9 O SEGMENT GROUP - 1 - RFF-DTM C9 M 843 RFF Reference -

Florens EDI Transmission Guidelines (April 2008)
Florens EDI Transmission Guidelines (April 2008) EDI is a standard communication protocol for system-to-system integration of Florens with depots. In container leasing or related transportation industry, depots can set up EDI with their customers to submit and receive container movement and MNR information electronically. Standard EDI Messages Florens accepts a standardized EDI integration process. We support CEDEX and UN/EDIFACT message standards. Message Formats Florens' EDI message format are widely adopted market standard (UN/EDIFACT and CEDEX) for system-to-system integration for container Gate-In, Gate-Out and MNR estimate details. Other message formats which acceptable by Florens system include customized flat file provided by depots. Transmission Protocols The Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is the email communication protocol which Florens uses for capturing EDI messages directly from depots as email attachments. Methods of sending EDI files to Florens (1) Prepare your EDI files The EDI file extension must be in either one of below listed 3 types. It should be generated by Win Bridge or depots’ in-house system. • txt • imp •exp For CEDEX flat file format, there may be maximum FOUR attachments in one email, the GATEIN, GATEOUT, WESTIM and WESTIMDT. The file name format has to be renamed as below convention. GATEIN: DDDDDD GATEIN XXXXXXXX•EXP GATEOUT: DDDDDD_GATEOUT_XXXXXXXX•EXP WESTIM: DDDDDD_WESTIM_XXXXXXXX•EXP WESTIMDT: DDDDDD_WESTIMDT_XXXXXXXX•EXP Where DDDDDD is the depot code assigned by Florens, XXXXXXXX is depot’s own reference for the file name. For examples: GATE IN: USNYC1_GATEIN_XYZABC . EXP GATEOUT: USNYC1_GATEOUT_XYZABC . EXP WESTIM: USNYC1_WESTIM_XYZABC . EXP WESTIMDT: USNYC1 _WESTIMDT_XYZABC . EXP For EDIFACT format, the file name format has to be renamed as below convention.