Table of Contents はじめに
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Moogerfooger® MF-107 Freqbox™
Understanding and Using your moogerfooger® MF-107 FreqBox™ TABLE OF CONTENTS Introduction.................................................2 Getting Started Right Away!.......................4 Basic Applications......................................6 FreqBox Theory........................................10 FreqBox Functions....................................16 Advanced Applications.............................21 Technical Information...............................24 Limited Warranty......................................25 MF-107 Specifications..............................26 1 Welcome to the world of moogerfooger® Analog Effects Modules. Your Model MF-107 FreqBox™ is a rugged, professional-quality instrument, designed to be equally at home on stage or in the studio. Its great sound comes from the state-of-the- art analog circuitry, designed and built by the folks at Moog Music in Asheville, NC. Your MF-107 FreqBox is a direct descendent of the original modular Moog® synthesizers. It contains several complete modular synth functions: a voltage-controlled oscillator (VCO) with variable waveshape, capable of being hard synced and frequency modulated by the audio input, and an envelope follower which allows the dynamics of the input signal to modulate the frequency of the VCO. In addition the amplitude of the VCO is controlled by the dynamics of the input signal, and the VCO can be mixed with the audio input. All performance parameters are voltage-controllable, which means that you can use expression pedals, MIDI-to-CV converter, or any other source of control voltages to 'play' your MF-107. Control voltage outputs mean that the MF-107 can be used with other moogerfoogers or voltage controlled devices like the Minimoog Voyager® or Little Phatty® synthesizers. While you can use it on the floor as a conventional effects box, your MF-107 FreqBox is much more versatile and its sound quality is higher than the single fixed function "stomp boxes" that you may be accustomed to. -

El Padre Del Sinte Y, Quizá, El Hombre Más Influyente En La
Pioneros FM BOB MOOG La gente corriente conoce muy pocos nombres de creadores de instrumentos –Stradivarius, Hammond, Wurlitzer, Fender, Gibson… y por supuesto, Moog OB MOOG, en una revista de electrónica. EL padre del De repente, en plena adolescencia, sintetizador y, “El padre del sinte y, ya estaba haciendo y vendiendo kits con quizá, el hombre su pequeña empresa R.A. Moog Co. más influyente quizá, el hombre más En 1961, siendo todavía un estudiante, en la música publicó un diseño de theremin a durante las transistores del cual vendió más de mil últimas cinco influyente en la música unidades, bien como kits de montaje Bdécadas, murió el pasado 21 de Agosto. de los últimos 50 años” o como instrumentos finalizados. Tenía 71 años –una edad respetable para A partir de entonces, conoció muchos, pero no para él. Cualquiera al pionero de la música electrónica que haya podido compartir algún Raymond Scott, quien producía jingles momento con el entrañable Bob antes para importantes cadenas de TV de que le diagnosticaran un tumor cerebral en disfrutar durante unas horas de su inspiradora, con su enorme muro de equipos electrónicos. Abril de este mismo año, te confirmará que carismática y entrañable compañía. Es posible que aquello le inspirase, porque estaba lleno de energía, humor y vitalidad, así Por no molestar, Moog prefería viajar en tren a principios de los 60, Moog presentó, que es una auténtica pena que no haya podido o en autobús antes que aceptar el ofrecimiento de posiblemente, la mayor revolución de la música seguir algunas décadas más entre nosotros. -

Line 6 POD Go Owner's Manual
® 16C Two–Plus Decades ACTION 1 VIEW Heir Stereo FX Cali Q Apparent Loop Graphic Twin Transistor Particle WAH EXP 1 PAGE PAGE Harmony Tape Verb VOL EXP 2 Time Feedback Wow/Fluttr Scale Spread C D MODE EDIT / EXIT TAP A B TUNER 1.10 OWNER'S MANUAL 40-00-0568 Rev B (For use with POD Go Firmware 1.10) ©2020 Yamaha Guitar Group, Inc. All rights reserved. 0•1 Contents Welcome to POD Go 3 The Blocks 13 Global EQ 31 Common Terminology 3 Input and Output 13 Resetting Global EQ 31 Updating POD Go to the Latest Firmware 3 Amp/Preamp 13 Global Settings 32 Top Panel 4 Cab/IR 15 Rear Panel 6 Effects 17 Restoring All Global Settings 32 Global Settings > Ins/Outs 32 Quick Start 7 Looper 22 Preset EQ 23 Global Settings > Preferences 33 Hooking It All Up 7 Wah/Volume 24 Global Settings > Switches/Pedals 33 Play View 8 FX Loop 24 Global Settings > MIDI/Tempo 34 Edit View 9 U.S. Registered Trademarks 25 USB Audio/MIDI 35 Selecting Blocks/Adjusting Parameters 9 Choosing a Block's Model 10 Snapshots 26 Hardware Monitoring vs. DAW Software Monitoring 35 Moving Blocks 10 Using Snapshots 26 DI Recording and Re-amping 35 Copying/Pasting a Block 10 Saving Snapshots 27 Core Audio Driver Settings (macOS only) 37 Preset List 11 Tips for Creative Snapshot Use 27 ASIO Driver Settings (Windows only) 37 Setlist and Preset Recall via MIDI 38 Saving/Naming a Preset 11 Bypass/Control 28 TAP Tempo 12 Snapshot Recall via MIDI 38 The Tuner 12 Quick Bypass Assign 28 MIDI CC 39 Quick Controller Assign 28 Additional Resources 40 Manual Bypass/Control Assignment 29 Clearing a Block's Assignments 29 Clearing All Assignments 30 Swapping Stomp Footswitches 30 ©2020 Yamaha Guitar Group, Inc. -

Rack Mount Edition by R.Stephen Dunnington
USER’s MANUAL for the Rack Mount Edition By R.Stephen Dunnington Here it is – the Minimoog Voyager Rack Mount Edition®. Moog Music has put more than 30 years of experience with analog synthesizer technology into the design of this instrument to bring you the fattest lead synthesizer since the minimoog was introduced in 1970. We’ve done away with the things that made 30-year- old analog synthesizers difficult – the tuning instability, the lack of patch memory, and the lack of compatibility with MIDI gear. We’ve kept the good parts – the rugged construction, the fun of changing a sound with knobs in real time, and the amazing, warm, fat, pleasing analog sound. The Voyager is our invitation to you to explore analog synthesis and express yourself. It doesn’t matter what style of music you play – the Voyager is here to help you tear it up in the studio, on stage, or in the privacy of your own home. Have fun! Acknowledgements – Thanks to Bob Moog for designing yet another fantastic music making machine! Thanks are also due to the Moog Music Team, Rudi Linhard of Lintronics for his amazing software, Brian Kehew, Nigel Hopkins, and all the great folks who contributed design ideas, and of course, you – the Moog Music customer. TABLE OF CONTENTS: I. Getting Started……………………………………………………... 2 II. The Basics of Analog Synthesis…………………………………… 5 III. Basic MIDI................................................................................ 12 IV. The Voyager’s Features…………………………………………… 13 V. The Voyager’s Components A. Mixer……………………………………………………………... 17 B. Oscillators……………………………………………………….. 19 C. Filters…………………………………………………………….. 22 D. Envelope Generators………………………………………….. 26 E. Audio Outputs…………………………………………………… 28 F. -

Il Sintetizzatore Analogico Modelli, Caratteristiche E Possibilità Dal Neo-Analogico Al Vintage
Roberto Raineri-Seith Il sintetizzatore analogico Modelli, caratteristiche e possibilità dal neo-analogico al vintage Prima edizione ottobre 1993 Seconda edizione riveduta e aggiornata 2012 E' permessa la riproduzione per estratti unicamente a scopi didattico-divulgativi non commerciali e con citazione della fonte © Prolitteris 2012 2 Sommario Introduzione 5 Filosofia della musica elettronica Il suono analogico Il sintetizzatore analogico 8 I moduli principali: VCO, VCF, VCA, ADSR, LFO, modulatore ad anello, Sample&Hold, Noise Generator, Frequency shifter, Fixed Filter Bank, Analog sequencer, moduli ausiliari Tecniche di musica elettronica sperimentale 15 Caratteristiche dei principali strumenti vintage 17 I classici: Moog, Arp, Oberheim, Sequential Circuits Inc., Roland, Korg,Yamaha, EMS, Serge Tcherepnin, Buchla, EMU Systems Di tutto, di piu' Processori esterni Drum machines Il ritorno dei morti viventi 32 L'analogico virtuale I sintetizzatori neo-analogici Neo-analogico o vintage? Guida all'acquisto Un'alternativa all'acquisto: il DIY Referenze 43 Discografia, videografia e bibliografia essenziale Nota sull'autore 3 "Per musica elettronica si deve intendere non soltanto un generico ricorso a strumenti il cui suono viene prodotto elettronicamente, bensi quell'esperienza compositiva che, muovendo dalle virtualità materiche intrinseche ai nuovi mezzi, ha realmente allargato e approfondito l'area delle possibilità foniche unitamente ai processi operazionali di composizione e ai moduli costruttivi" (Armando Gentilucci) "La sintesi analogica -

Synthesizer-Guide 2018
Synthesizer 1 Guide 2018 Guide Nr. 9 Guide Nr. Synthesizer Sonnenstraße 15 Tel: 0049/(0)89/55146-116 D-80331 München www.hieber-lindberg.de www.hieber-lindberg.de [email protected] www.hieber-lindberg.de [email protected] Vorwort Novation PEAK Seite 4 Liebe Synthesizer-Freunde! 2 8-stimmiger Hybrid-Synthesizer 3 Jedes Jahr scheint ein neuer, überraschender Höhepunkt im Synthesizer-Sektor Roland SH-01A Seite 8 erreicht. Überraschend insofern, als man eine Sättigung des Marktes annehmen Analoger Klassiker im Boutique Format könnte. Gibt es nicht schon genug monophone Analogsynthesizer? (Nein.) Sind neue Eurorack-Module überhaupt noch möglich? (Ja.) Und was ist mit den poly- Arturia MatrixBrute Seite 10 phonen Analogen, sind diese endlich mal auf der Überholspur unterwegs? (Korg Paraphoner Analog-Synthesizer steigt zu DSI in den Poly-Ring: Die Überholspur ist eröffnet.) Hätte man als Musi- ker die nötigen Zeitressourcen, würde man umgehend (!) einen MatrixBrute samt Korg Prologue Seite 14 einiger der neuen Eurorack-Module ins Studio holen, dazu noch einen Peak und 8- bzw. 16-stimmiger Analog-Synthesizer einen Prologue. Dann Türe zu und genüssliches Klang-Forschen - für mindestens Roland/Studio Electronics SE-02 Seite 16 drei Jahre (oder mehr). Das Potenzial dazu hätten alle genannten Instrumente. Monophoner Analog-Synthesizer Doch natürlich sieht das wahre Leben anders aus. Hier heißt es Entscheidungen Hieber Lindberg Shop Seite 19 treffen - für dieses oder für jenes Instrument. Neuer „Polyphonic Eurorack Syn- Preisliste Synthesizer / Modularsysteme / Module thesizer“ von Doepfer gefällig, zusammen mit Vermonas randomRHYTHM- und twinCussion-Modul - alles im Arturia RackBrute-System verbunden mit dem Mini- Hieber Lindberg News Seite 26 Brute 2? Klingt nicht schlecht. -

11C Software 1034-1187
Section11c PHOTO - VIDEO - PRO AUDIO Computer Software Ableton.........................................1036-1038 Arturia ...................................................1039 Antares .........................................1040-1044 Arkaos ....................................................1045 Bias ...............................................1046-1051 Bitheadz .......................................1052-1059 Bomb Factory ..............................1060-1063 Celemony ..............................................1064 Chicken Systems...................................1065 Eastwest/Quantum Leap ............1066-1069 IK Multimedia .............................1070-1078 Mackie/UA ...................................1079-1081 McDSP ..........................................1082-1085 Metric Halo..................................1086-1088 Native Instruments .....................1089-1103 Propellerhead ..............................1104-1108 Prosoniq .......................................1109-1111 Serato............................................1112-1113 Sonic Foundry .............................1114-1127 Spectrasonics ...............................1128-1130 Syntrillium ............................................1131 Tascam..........................................1132-1147 TC Works .....................................1148-1157 Ultimate Soundbank ..................1158-1159 Universal Audio ..........................1160-1161 Wave Mechanics..........................1162-1165 Waves ...........................................1166-1185 -

Bomb Factory Plug-Ins
Bomb Factory Plug-ins Version 7.3 Copyright © 2007 Digidesign, a division of Avid Technology, Inc. All rights reserved. This guide may not be duplicated in whole or in part without the express written consent of Digidesign. AudioSuite, Avid, Avid DNA, Avid Xpress, Digidesign, Pro Tools, Pro Tools Academic, Pro Tools HD, Pro Tools LE, Pro Tools M-Powered, RTAS, and VENUE are either trademarks or registered trademarks of Avid Technology, Inc. in the US and other countries. All other trademarks contained herein are the property of their respective owners. Product features, specifications, system requirements, and availability are subject to change without notice. “bombfactory,” “Bomb Factory,” BF76, BF2A, BF3A, “Digital Done Right,” “Classic Compressors,” “BF Essentials,” “Fairchild,” “Cosmonaut Voice,” “Plutonium Pack,” “Slightly Rude Compressor,” and “Tel-Ray” are trademarks of Digidesign, a division of Avid Technology, Inc. “JOEMEEK” trademarks owned by PMI Audio LTD, used under license. “Moogerfooger” trademarks owned by Moog Music, Inc., used under license. “SansAmp” and “SansAmp PSA-1” trademarks owned by Tech 21, Inc., used under license. “Voce” trademarks owned by Amels and Alonso Electronic Design, used under license. “Funk Logic” and “Mastererizer” trademarks owned by Derek Choice dba Funk Logic, used under license. “Purple Audio” and “MC-77” trademarks owned by Purple Audio, used under license. All other trademarks are property of their respective owners. Names of sample settings are intended for descriptive purposes only and should not be construed as an endorsement by or affiliation with any company, product, song title, or artist. Product features, specifications, system requirements and availability are subject to change without notice. -
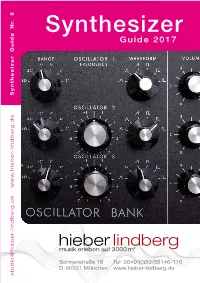
Synthesizer 1 Guide 2017 Guide Nr
Synthesizer 1 Guide 2017 Guide Nr. 8 Synthesizer Sonnenstraße 15 Tel: 0049/(0)89/55146-116 D-80331 München www.hieber-lindberg.de www.hieber-lindberg.de [email protected] www.hieber-lindberg.de Vorwort MOOG Seite 4_ Liebe Synthesizer-Freunde! MINIMOOG 3 Qualität hält wieder Einzug in den Synthesizer-Markt! Nicht nur klanglich, vor Modular / Semi-Modular / Performance Seite 8_ allem aber auch betreffend Haptik und „innerer Werte“. Nachdem „Instrumente Kilpatrick Audio – Carbon mit Knöpfen“ bereits seit Jahren wieder in großen Mengen und von vielen An- Make Noise – 0-Coast bietern gebaut werden, erscheinen seit einiger Zeit besonders hochwertig Doepfer – A-110-6 (Thru Zero VCO) verarbeitete (und herausragend konzipierte) Modelle, wie etwa der Vermona Endorphin.es – Grand Terminal ’14 Analogsynthesizer, Moog Minimoog, der GRP A2 oder die Instrumente der Radikal Technologies – Swarm Oscillator britischen Firma Modal Electronics. Ganz abgesehen von edlen Lamborghinis XAOC – Belgrad (Dual State Variable VCF) à la Hartmann 20 oder dem Schmidt Synthesizer (Deluxe-Designer-Stücke, die allerdings nicht für den großen Markt vorgesehen sind). Was alle Synthesizer Hieber Lindberg Shop Seite 20 eint: Es sind handgefertigte Instrumente „Made in Europe“ (Ausnahme Mini- Synthesizer Preisliste moog – „Made in USA“). Die Handarbeit erklärt ein entsprechend realistisches Preisniveau (Schnäppchen sucht man hier vergebens), garantiert aber auch Hieber Lindberg News Seite 26 nachhaltige Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Instrumente. Schmidt „White“, Hartmann 20, Korg – microKorg S, monologue Im modularen Bereich scheint ein gewisser Zenit erreicht zu sein, was jedoch der außergewöhnlichen Popularität der Eurorack-Systeme keinen Abbruch tut. Roland Seite 31 Im Gegenteil: Immer detailliertere, speziellere Module decken alle nur erdenk- System-8 Plug-Out Synthesizer lichen Nischen musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten ab. -
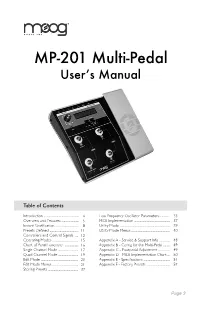
MP-201 Multi-Pedal Userʼs Manual
MP-201 Multi-Pedal Userʼs Manual Table of Contents Introduction ................................................. 4 Low Frequency Oscillator Parameters............... 33 Overview and Features ........................ 5 MIDI Implementation .................................................. 37 Instant Gratification ................................ 8 Utility Mode ...................................................................... 39 Presets Defined ........................................ 11 Utility Mode Menus ...................................................... 40 Controllers and Control Signals .... 12 Operating Modes .................................... 15 Appendix A - Service & Support Info ............... 48 Chart of Panel Functions ................... 16 Appendix B - Caring for the Multi-Pedal ......... 49 Single Channel Mode ............................ 17 Appendix C - Footpedal Adjustment ................ 49 Quad Channel Mode ............................ 19 Appendix D - MIDI Implementation Chart ... 50 Edit Mode .................................................... 20 Appendix E - Specifications ..................................... 51 Edit Mode Menus .................................... 21 Appendix F - Factory Presets ................................. 52 Storing Presets .......................................... 32 Page 3 MP-201 User’s Manual MP-201 User’s Manual Introduction Thank you and congratulations on your purchase of the MP-201 Multi-Pedal. The MP-201 Multi-Pedal is an advanced four-channel CV/MIDI footpedal controller. -

Moogerfooger®
Understanding and Using Your moogerfooger® CP-251 Control Processor Moog Music Inc. Asheville, NC USA ©2000, 2003 by Moog Music Inc. Welcome to the world of moogerfooger® Analog Effects Modules! Your Model CP251 Control Processor is a rugged, professional-quality instrument, designed to be equally at home on stage or in the studio. Its great functionality and classic effects come from its state-of-the-art all-analog circuitry, designed and built under Bob Moog's personal direction. Your CP251 is a direct descendent of the original modular Moog™ synthesizers. It contains a total of eight independent control signal generating and processing functions. Used with other moogerfoogers, voltage-controlled analog synthesizers, MIDI- to-CV converters, or other devices that produce or accept analog control signals, the CP251 enables you to create an amazing variety of dynamic synthesizer effects. The following pages will first introduce voltage control, which is the basic technical principle underlying modular analog synthesizers. Next we'll describe each of the CP251's eight functions. After that, you'll find a few typical patches, which will give you some good ideas about how you can use the CP251 with your voltage-controlled gear. At the end of this booklet you'll find technical specifications, service and warranty information, and information about Moog Music. CONTENTS BASIC THEORY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 GETTING STARTED - TOUR OF THE MODULES - 6 USING THE CP251 WITH MF-SERIES DEVICES - 15 TECHNICAL INFORMATION - - - - - - - - - - - 24 WARRANTY INFORMATION - - - - - - - - - - - 27 2 SOME BASIC THEORY When you first try out an audio processor like a ring modulator or phaser, you plug your instrument into the AUDIO IN jack, connect the AUDIO OUT jack to your amplifier, and immediately hear what it does by playing your instrument. -

Synthesizer 1 Guide 2014 Guide Nr
Synthesizer 1 Guide 2014 Guide Nr. 5 Synthesizer Sonnenstraße 15 Tel: 0049/(0)89/55146-116 D-80331 München www.hieber-lindberg.de www.hieber-lindberg.de [email protected] www.hieber-lindberg.de Vorwort Clavia Seite 4 Liebe Synthesizer-Freunde! Nord Lead 4 3 5 Jahre Synthesizer-Guide! Seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe Arturia Seite 7 2009 hat sich der Guide zu einem sehr beliebten Ratgeber rund um ak- MicroBrute tuelle Synthesizer entwickelt. Auch der Markt hilft mit und kommt dem Korg Seite 10 allgemeinen Interesse an analogen / virtuell-analogen Instrumenten MS-20 mini entgegen. So konnten wir aus einer Vielzahl von leistungsfähigen und gut gebauten Synthesizern die Testkandidaten für den Guide auswäh- Moog Seite 12 len: Von monophonen Energie-Bündeln für Rack oder Tisch - MacBeth Sub Phatty MicroMac - über kraftvolle, sehr handliche Analogkeyboards - Arturia MicroBrute, Korg MS-20 mini, Novation Bass Station II und Moog Sub- Novation Seite 16 Phatty - bis hin zu neuesten polyphonen Klassikern - Clavia NordLead Bass Station II 4 - ist das Angebot der Testberichte sehr umfassend. Abgerundet wer- Hieber Lindberg Seite 20 den die Berichte durch ein interessantes Interview mit Dieter Doepfer, 5 Jahre Synthesizer Guide dem wir nicht nur das A-100 Modularsystem, sondern auch so man- chen genialen Workshop in unserem Hause zu verdanken haben. Hieber Lindberg Seite 22 Ich hoffe, dass euch die Jubiläumsausgabe des Guides gefällt. Für Synthesizer Preisliste ausführliche Beratungen rund um Synthesizer und Studiotechnik stehe ich euch natürlich gerne jederzeit zur Verfügung. Hieber Lindberg Seite 28 News Euer Macbeth Seite 30 Martin Machwitz mit Team MicroMac Vermona Seite 35 fourMulator 4-fach LFO Interview Seite 36 Dieter Doepfer Vintage Synthesizer Ecke Seite 40 Monophone Instrumente Theo Bloderer Martin Vintage Synthesizer Ecke Seite 42 Stefan Machwitz Polyphone Instrumente Leberfinger Hieber Lindberg Synthesizer Guide Nr.