海幹校戦略研究第 10 巻第 1 号(通巻第 20 号) 2020 年 7 月 Print Edition: ISSN 2187-1868 Online Edition: ISSN 2187-1876
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Extensions of Remarks E1521 EXTENSIONS of REMARKS
July 19, 2005 CONGRESSIONAL RECORD — Extensions of Remarks E1521 EXTENSIONS OF REMARKS RETIREMENT OF ADMIRAL VERN Action Team for Desert Shield and Desert a bright light on the injustices suffered by the CLARK Storm. Admiral Clark has also served as the descendants of the transatlantic slave trade Director of both Plans and Policy (J5) and Fi- throughout the Americas, and particularly in HON. IKE SKELTON nancial Management and Analysis (J8) at the Latin America and Caribbean. The United OF MISSOURI U.S. Transportation Command; Deputy and States must join with the international commu- IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES Chief of Staff, United States Atlantic Fleet; the nity to improve the living conditions of and to Director of Operations (J3) and subsequently empower the Afro-Latino communities Tuesday, July 19, 2005 Director of the Joint Staff. throughout the Americas. Mr. SKELTON. Mr. Speaker, it gives me His tenure as Chief of Naval Operations has As a result of the slave trade and immigra- great pleasure to rise today in order to recog- been underscored by remarkable strength and tion, approximately 80,000,000 to 150,000,000 nize and honor one of Missouri’s favorite sons, a clear vision for the future. Anticipating the persons of African descent live in Latin Amer- Admiral Vern Clark, United States Navy, our tremendous challenges of the rapidly changing ica and the Caribbean, representing the larg- 27th Chief of Naval Operations, as he pre- post-Cold War strategic environment, he set a est concentration of persons of African ances- pares to turn over the helm of the United course for deep and fundamental trans- try outside of Africa. -

Senate Hearings Before the Committee on Appropriations
S. HRG. 109–130 Senate Hearings Before the Committee on Appropriations Department of Defense Appropriations Fiscal Year 2006 109th CONGRESS, FIRST SESSION H.R. 2863 DEPARTMENT OF DEFENSE NONDEPARTMENTAL WITNESSES Department of Defense Appropriations, 2006 (H.R. 2863) S. HRG. 109–130 DEPARTMENT OF DEFENSE APPROPRIATIONS FOR FISCAL YEAR 2006 HEARINGS BEFORE A SUBCOMMITTEE OF THE COMMITTEE ON APPROPRIATIONS UNITED STATES SENATE ONE HUNDRED NINTH CONGRESS FIRST SESSION ON H.R. 2863 AN ACT MAKING APPROPRIATIONS FOR THE DEPARTMENT OF DEFENSE FOR THE FISCAL YEAR ENDING SEPTEMBER 30, 2006, AND FOR OTHER PURPOSES Department of Defense Nondepartmental witnesses Printed for the use of the Committee on Appropriations ( Available via the World Wide Web: http://www.gpoaccess.gov/congress/index.html U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 99–854 PDF WASHINGTON : 2005 For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Internet: bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512–1800; DC area (202) 512–1800 Fax: (202) 512–2250 Mail: Stop SSOP, Washington, DC 20402–0001 COMMITTEE ON APPROPRIATIONS THAD COCHRAN, Mississippi, Chairman TED STEVENS, Alaska ROBERT C. BYRD, West Virginia ARLEN SPECTER, Pennsylvania DANIEL K. INOUYE, Hawaii PETE V. DOMENICI, New Mexico PATRICK J. LEAHY, Vermont CHRISTOPHER S. BOND, Missouri TOM HARKIN, Iowa MITCH MCCONNELL, Kentucky BARBARA A. MIKULSKI, Maryland CONRAD BURNS, Montana HARRY REID, Nevada RICHARD C. SHELBY, Alabama HERB KOHL, Wisconsin JUDD GREGG, New Hampshire PATTY MURRAY, Washington ROBERT F. BENNETT, Utah BYRON L. DORGAN, North Dakota LARRY CRAIG, Idaho DIANNE FEINSTEIN, California KAY BAILEY HUTCHISON, Texas RICHARD J. DURBIN, Illinois MIKE DEWINE, Ohio TIM JOHNSON, South Dakota SAM BROWNBACK, Kansas MARY L. -

The Influence of Law on Sea Power Doctrines: the New Maritime Strategy and the Future of the Global Legal Order
I The Influence of Law on Sea Power Doctrines: The New Maritime Strategy and the Future of the Global Legal Order Craig H. Allen * or much of the 2006-07 academic year, elements of the US Naval War Col Flege facilitated an elaborate process designed to provide the intellectual foun dations for the Chief of Naval Operations (CNO) and his staff to draw upon in drafting a new maritime strategy.l The process brought together experts from throughout the world to take part in workshops, strategic foundation "war" games, conferences and listening sessions.2 It was my privilege as the Charles H. Stockton Chair of International Law to selVe as legal advisor throughout the process. This article summarizes the contributions of the Naval War College International Law Department (ILD) in the process to develop and define the relationship between maritime strategy and law, particularly international law, and provides the au thor's thoughts on what course that strategy should take. Three decades have now elapsed since Daniel Patrick O'Connell challenged our thinking with his book The Influence ofLaw on Sea Power} In it, the New Zealand law of the sea expert and Chichele Professor of Public International Law argued, shortly before his death in 1979, that because the law of the sea "has become the stimulus to sea power, not its restraint,"4 future naval operations planning staffs • Charles H. Stockton Professor of International Law, US Naval War College. The Influence ofLaw on Sea Power Doctrines must acquire a thorough appreciation of the law.; In contrast to Admiral Alfred Thayer Mahan and the more recent naval historians who, while providing illumi nating analyses of the influence of sea power on history,6 mostly disregard the in fl uence of international law on sea power, Professor O'Connell forcefully argued that sea power doctrines can no longer be considered in isolation from the relevant law. -

Fense Independent Review Relat- Ing to Fort Hood
i [H.A.S.C. No. 111–115] FINDINGS OF THE DEPARTMENT OF DE- FENSE INDEPENDENT REVIEW RELAT- ING TO FORT HOOD HEARING BEFORE THE FULL COMMITTEE OF THE COMMITTEE ON ARMED SERVICES HOUSE OF REPRESENTATIVES ONE HUNDRED ELEVENTH CONGRESS SECOND SESSION HEARING HELD JANUARY 20, 2010 U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 57–664 WASHINGTON : 2010 For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Internet: bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512–1800; DC area (202) 512–1800 Fax: (202) 512–2104 Mail: Stop IDCC, Washington, DC 20402–0001 HOUSE COMMITTEE ON ARMED SERVICES ONE HUNDRED ELEVENTH CONGRESS IKE SKELTON, Missouri, Chairman JOHN SPRATT, South Carolina HOWARD P. ‘‘BUCK’’ MCKEON, California SOLOMON P. ORTIZ, Texas ROSCOE G. BARTLETT, Maryland GENE TAYLOR, Mississippi MAC THORNBERRY, Texas NEIL ABERCROMBIE, Hawaii WALTER B. JONES, North Carolina SILVESTRE REYES, Texas W. TODD AKIN, Missouri VIC SNYDER, Arkansas J. RANDY FORBES, Virginia ADAM SMITH, Washington JEFF MILLER, Florida LORETTA SANCHEZ, California JOE WILSON, South Carolina MIKE MCINTYRE, North Carolina FRANK A. LOBIONDO, New Jersey ROBERT A. BRADY, Pennsylvania ROB BISHOP, Utah ROBERT ANDREWS, New Jersey MICHAEL TURNER, Ohio SUSAN A. DAVIS, California JOHN KLINE, Minnesota JAMES R. LANGEVIN, Rhode Island MIKE ROGERS, Alabama RICK LARSEN, Washington TRENT FRANKS, Arizona JIM COOPER, Tennessee BILL SHUSTER, Pennsylvania JIM MARSHALL, Georgia CATHY MCMORRIS RODGERS, Washington MADELEINE Z. BORDALLO, Guam K. MICHAEL CONAWAY, Texas BRAD ELLSWORTH, Indiana DOUG LAMBORN, Colorado PATRICK J. MURPHY, Pennsylvania ROB WITTMAN, Virginia HANK JOHNSON, Georgia MARY FALLIN, Oklahoma CAROL SHEA-PORTER, New Hampshire DUNCAN HUNTER, California JOE COURTNEY, Connecticut JOHN C. -

Networking the Global Maritime Partnership Stephanie Hszieh
Naval War College Review Volume 65 Article 4 Number 2 Spring 2012 Networking the Global Maritime Partnership Stephanie Hszieh George Galdorisi Terry McKearney Darren Sutton Follow this and additional works at: https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review Recommended Citation Hszieh, Stephanie; Galdorisi, George; McKearney, Terry; and Sutton, Darren (2012) "Networking the Global Maritime Partnership," Naval War College Review: Vol. 65 : No. 2 , Article 4. Available at: https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol65/iss2/4 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at U.S. Naval War College Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Naval War College Review by an authorized editor of U.S. Naval War College Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Hszieh et al.: Networking the Global Maritime Partnership NETWORKING THE GLOBAL MARITIME PARTNERSHIP Stephanie Hszieh, George Galdorisi, Terry McKearney, and Darren Sutton We will be prepared to support and defend our freedom of navigation and access to the global commons. Our partners and allies are our great- est strategic asset. ADMIRAL MICHAEL MULLEN ix years after Admiral Michael Mullen, then Chief of Naval Operations, pro- Sposed his “thousand-ship navy” concept at the Seventeenth International Seapower Symposium at the U.S. Naval War College in 2005, his notion of a Global Maritime Partnership is gaining increasing currency within, between, and among navies.1 As the Chief of Naval Operations, Admiral Gary Roughead, noted in his remarks at the Nineteenth International Seapower Symposium in 2009, navies worldwide are working mightily to enhance cooperation and interoper- ability on the global commons.2 Real-world operations, especially in the Pacific Rim, have demonstrated that networking maritime forces is crucial to the effectiveness of operations that run the gamut from humanitarian operations to dealing with insurgencies, to nation-building, to state-on-state conflict. -
Vern Clark CNO 7/21/2000- 7/22/2005
THE OFFICERS AND MEMBERS OF THE ARIZONA SUBMARINE VETERANS, PERCH BASE USSVI EXTEND A WARM WELCOME TO OUR 2016ANNUALAWARDS BANQUET. COMMANDER: CHUCK EMMETT VICE COMMANDER: RICHARD KUNZE SECRETARY: MARCIA UNSER TREASURER: DAVE HEIGHWAY CHAPLAIN: MIKE OLSEN COMMUNICATIONS OFFICER: CHUCK LUNA WEB MASTER: DAN MARKS MEMBERSHIP: JIM ANDREWS COB: RICHARD KUNZE STOREKEEPER: EVENTS COORDINATOR: DON UNSER HISTORIAN: CHUCK LUNA Appetizers Cheese Platter Vegeta:bJe erudite Salod Garden Salad w/ranch or vinaigrette Entree (Selections) Grilled Petite B,eef Medallions Chicken Cordon aleUJ Grilled Fillet of Salmon Vegetables Green Beans wj onions and bacon or California Vegetable Medlew Dessel!t Chocolate cake with cherries and wlilip,pedl cream Action 1800-1900 Muster on Station (No host cocktails- Silent Auction bids) 1900-1915 Welcome, Invocation (Base Commander, Chaplain) 1915-2000 Evening Meal 2000-2010 Base Comma-nder Remarks {Commander's Awards) 2010-2020 Membership Awards (Longevity, "Early Bird" Dues Drawing) 2020-2030 Holland Club Induction 2030-2035 2015 "Sailor of the Year" Award 2035-2040 Introduction of Guest Speaker {Base Commander) 2040-2130 Guest Speaker Admiral Vern Clark CNO 7/21/2000- 7/22/2005 2130-2200 Results: Silent Auction 2200-2210 Tolling for the Boats-January 2210-2215 Remembrance, Departed Shipmates (Base Chaplain) 2215 Closing Remarks- Benediction {Base Commander- Chaplain) VERN CLARK ADMIRAL, .UNITED STATES NAVY (Retired} Admiral Clark completed a distinguished 37-year Navy career in 2005. His Navy experience spans his early days in destroyers, command of a Patrol Gunboat as a Lieutenant and conclusion in the halls of the Pentagon as the Chief of Naval Operations and a member of the Joint Chiefs of Staff. -

Organizing OPNAV (1970 - 2009)
Organizing OPNAV (1970 - 2009) Peter M. Swartz w/ Michael C. Markowitz Prepared for the U.S. Navy Naval History and Heritage Command CNO VCNO CAB D0020997.A5/2Rev January 2010 Strategic Studies is a division of CNA. This directorate conducts strategy and force assessments, analyses of security policy, regional analyses, and studies of political-military issues. CNA Strategic Studies is part of the global community of strategic studies institutes and in fact collaborates with many of them. Our strategists and military/naval operations experts have either active duty experience or have served as field analysts with operating Navy and Marine Corps commands. They are skilled at anticipating the "problem after next" as well as determining measures of effectiveness to assess ongoing initiatives. A par- ticular strength is bringing empirical methods to the evaluation of peace-time engagement and shaping activities. On the ground experience is a hallmark of our regional work. Our specialists combine in-country expe- rience, language skills, and the use of local primary-source data to produce empirically based work. All of our analysts have advanced degrees, and virtually all have lived and worked abroad. The Strategic Studies Division's charter is global. In particular, our analysts have proven expertise in the following areas: o Maritime strategy o Future national security environment and forces o Deterrence, WMD proliferation, missile defense, and arms control. o Insurgency and stabilization o The world's most important navies o The full range of Asian security issues o The full range of Middle East related security issues, especially Iran and the Arabian Gulf o European security issues, especially the Mediterranean littoral o West Africa, especially the Gulf of Guinea o Latin America The Strategic Studies Division is led by Rear Admiral Michael McDevitt, USN (Ret.), who is available at 703-824-2614 or [email protected]. -
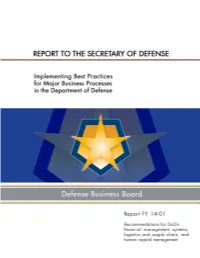
Implementing Best Practices.Pdf
Implementing Best Practices for Major Business Processes in the Department of Defense PREFACE This report is a product of the Defense Business Board (DBB). Recommendations by the DBB are offered as advice to the Department of Defense (DoD) and do not represent DoD policy. The DBB was established by the Secretary of Defense in 2002 to provide the Secretary and the Deputy Secretary of Defense with independent advice and recommendations on how “best business practices” from the private sector’s corporate management perspective might be applied to the overall management of DoD. The Board’s members, appointed by the Secretary of Defense, are corporate leaders and managers with demonstrated executive-level management and governance expertise. They possess a proven record of sound judgment in leading or governing large, complex corporations and are experienced in creating reliable solutions to complex management issues guided by best business practices. Authorized by the Federal Advisory Committee Act of 1972, the Government in Sunshine Act of 1976, and other appropriate federal regulations, the Board members are a federal advisory committee and volunteer their time to work in small groups (subcommittees) to develop recommendations and effective solutions aimed at improving DoD. Implementing Best Practices for Major Business Report FY14-01 Processes In The Department Of Defense Task Group 1 2 TABLE OF CONTENTS Executive Summary ............................................................................................................5 Terms -

Vice Admiral Henry C. Mustin Furthered the Family Reputation for Service to Country
Introduction Born into an illustrious naval family, Vice Admiral Henry C. Mustin furthered the family reputation for service to country. His grandfather, the first Henry C., is considered by many as the father of naval aviation, having established an air station at Pensacola, being the first to be catapulted off a ship, and being the first American aviator ever to take on live fire. His father, Lloyd, would have a notable career of his own as a "blackshoe," retiring as a Vice Admiral. As will be seen in the narrative, Mustin's father served as one of several life-long mentors. A detailed discussion of this family is contained in the final transcript. Graduating the Naval Academy in 1955, Mustin received orders to a Pacific Fleet destroyer followed by a tour as C.O. on a Mayport-based mine hunter and quickly honed his seamanship skills that prepared him to for a remarkable and varied career in the Navy during the Cold War. There are several areas of note in this oral history. First and foremost, Mustin was a naval warrior who helped bring on line new weapon systems and developed tactics and training methods for their employment. As a Lieutenant, he assisted creating early AAW doctrine; as a Vice Admiral he developed components of the Maritime Strategy. He had a hand in training evolutions such as Damage Control Olympics, NavTag, Surface Training Week, and pierside workups. During the Vietnam War, Mustin had a Pug Henry "Winds of War" experience, witnessing the conflict from Saigon, the Mekong Delta, as an aide to CinCPac, and as C.O. -

Strategic Readiness Review Following the Recent Tragic Incidents Involving U.S
1 2 3 December 2017 From: The Honorable Michael Bayer Admiral Gary Roughead, U.S. Navy (Retired) To: Secretary of the Navy Mr. Secretary: This report responds to your direction to conduct a Strategic Readiness Review following the recent tragic incidents involving U.S. 7th Fleet ships that resulted in significant loss of life and injury. The attached report contains specific recommendations for your consideration as you determine the way ahead for our nation’s Navy. We assembled a team of senior civilian executives and former senior military officers to conduct the review. The team examined issues of governance, accountability, operations, organizational structure, and manning and training over the past three plus decades to identify trends and contributing factors that have compromised performance and readiness of the fleet. We considered stresses on the force over time, significant changes to training, risk management processes, and how Navy culture has evolved. Our team reviewed past incidents and accidents and conducted numerous interviews with subject matter experts from across the government and with relevant leaders from the private sector in our areas of interest. The team specifically sought experts who have dealt with and responded to similar operational circumstances and events. Our Strategic Review examined the findings of the CNO’s Comprehensive Review and we largely concur with its recommendations, however our assessments, judgments and recommendations are independent of that work. ____________________ ______________________ -

Extensions of Remarks E1521 EXTENSIONS of REMARKS
July 19, 2005 CONGRESSIONAL RECORD — Extensions of Remarks E1521 EXTENSIONS OF REMARKS RETIREMENT OF ADMIRAL VERN Action Team for Desert Shield and Desert a bright light on the injustices suffered by the CLARK Storm. Admiral Clark has also served as the descendants of the transatlantic slave trade Director of both Plans and Policy (J5) and Fi- throughout the Americas, and particularly in HON. IKE SKELTON nancial Management and Analysis (J8) at the Latin America and Caribbean. The United OF MISSOURI U.S. Transportation Command; Deputy and States must join with the international commu- IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES Chief of Staff, United States Atlantic Fleet; the nity to improve the living conditions of and to Director of Operations (J3) and subsequently empower the Afro-Latino communities Tuesday, July 19, 2005 Director of the Joint Staff. throughout the Americas. Mr. SKELTON. Mr. Speaker, it gives me His tenure as Chief of Naval Operations has As a result of the slave trade and immigra- great pleasure to rise today in order to recog- been underscored by remarkable strength and tion, approximately 80,000,000 to 150,000,000 nize and honor one of Missouri’s favorite sons, a clear vision for the future. Anticipating the persons of African descent live in Latin Amer- Admiral Vern Clark, United States Navy, our tremendous challenges of the rapidly changing ica and the Caribbean, representing the larg- 27th Chief of Naval Operations, as he pre- post-Cold War strategic environment, he set a est concentration of persons of African ances- pares to turn over the helm of the United course for deep and fundamental trans- try outside of Africa. -
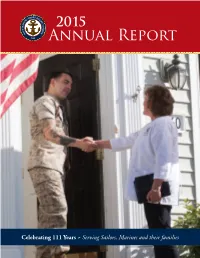
Annual Report
2015 Annual Report Celebrating 111 Years ~ Serving Sailors, Marines and their families MAKING A DIFFERENCE FOR SAILORS, MARINES, AND THEIR FAMILIES 2015 OUR MISSION NMCRS 4,021 34TABLE OF CONTENTS22 163 To provide, in partnership with the Navy and Marine Corps,TEAM financial, educational and other need-based Greetings from the Secretary of the Navy ...............3 VOLUNTEERSTRADITIONAL COMBATCASUALTY ASSISTANCE ADMINISTRATIVE assistance to active duty and retired Sailors andVISITING NURSES A MessageVISITING from theNURSES Commandant of theSTAF F Marines, their eligible family members and survivors. Marine Corps ...........................................................4 481,140 A Message from the Chief of Naval Operations ......5 Interest-free Loans and Grants VISION Volunteered FINANCIAL ASSISTANCEPresident’s Year in Review......................................6 Hours - As a non-profit, volunteer service organization, we Report of the Relief Committee ...............................7 use both financialSociety wideand non-financial resources to identify solutions to meet emergingBASIC needs. LIVING We EXPENSES help (FOOD,Report LODGING) of the Finance Committee............................8$19,074,436 clients improve personal financialTRANSPOR skills andTAT encourageION (INSURANCE, Financial CAR PAYMEN PositionT, RENT andAL Summary) of Operations$10,161,338 ......9 individual financial responsibility.FAMILY EMERGENCY $4,138,089 PROGRAMS Financial Highlights ...............................................10 CAR REPAIRS $3,509,726 A Comparison