年 報annual Report 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
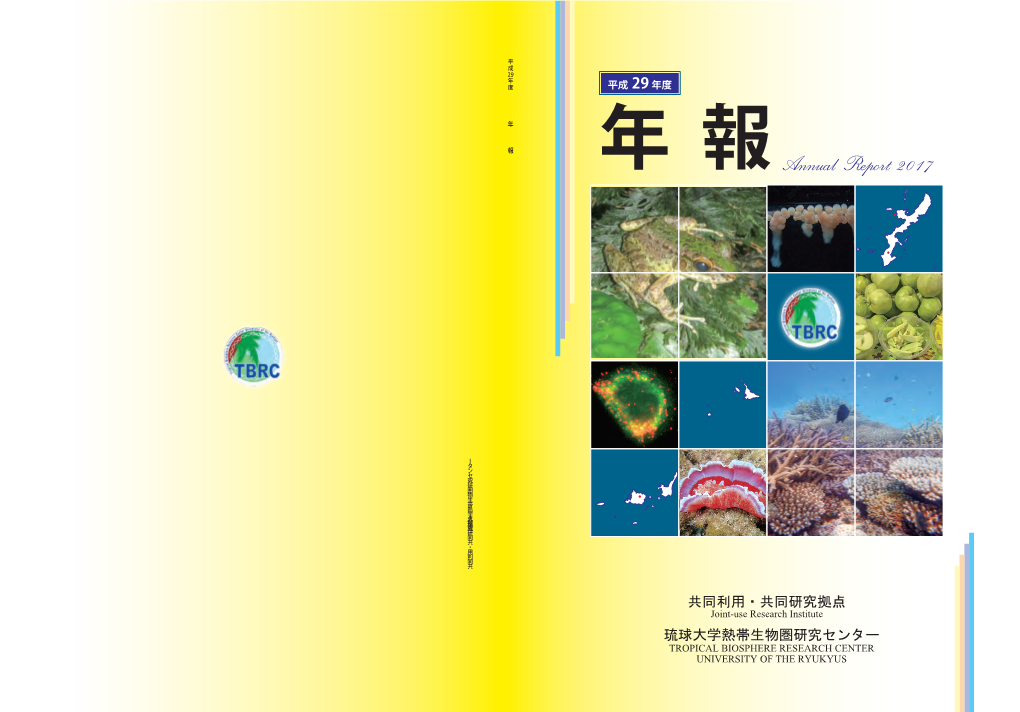
Load more
Recommended publications
-

Halogenated Tyrosine Derivatives from the Tropical Eastern Pacific
Article Cite This: J. Nat. Prod. 2019, 82, 1354−1360 pubs.acs.org/jnp Halogenated Tyrosine Derivatives from the Tropical Eastern Pacific Zoantharians Antipathozoanthus hickmani and Parazoanthus darwini † ‡ † § ‡ ⊥ ∥ Paul O. Guillen, , Karla B. Jaramillo, , Laurence Jennings, Gregorý Genta-Jouve, , # # # † Mercedes de la Cruz, Bastien Cautain, Fernando Reyes, Jenny Rodríguez, ‡ and Olivier P. Thomas*, † ESPOL Escuela Superior Politecnicá del Litoral, ESPOL, Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones Marinas, Campus Gustavo Galindo km. 30.5 vía Perimetral, P.O. Box 09-01-5863, Guayaquil, Ecuador ‡ Marine Biodiscovery, School of Chemistry and Ryan Institute, National University of Ireland Galway (NUI Galway), University Road, H91 TK33 Galway, Ireland § Zoology, School of Natural Sciences and Ryan Institute, National University of Ireland Galway (NUI Galway), University Road, H91 TK33 Galway, Ireland ⊥ ́ Equipe C-TAC, UMR CNRS 8038 CiTCoM, UniversitéParis Descartes, 4 Avenue de l’Observatoire, 75006 Paris, France ∥ UnitéMoleculeś de Communication et Adaptation des Micro-organismes (UMR 7245), Sorbonne Universites,́ Museuḿ National d’Histoire Naturelle, CNRS, Paris, France # Fundacioń MEDINA, Centro de Excelencia en Investigacioń de Medicamentos Innovadores en Andalucía, Avenida del Conocimiento 34, Parque Tecnologicó de Ciencias de la Salud, E-18016, Armilla, Granada, Spain *S Supporting Information ABSTRACT: In the search for bioactive marine natural products from zoantharians of the Tropical Eastern Pacific, four new tyrosine dipeptides, -

A Comprehensive Review on Morphological, Molecular
A COMPREHENSIVE REVIEW ON MORPHOLOGICAL, MOLECULAR AND PHYLOGENETIC TAXONOMY OF ZOANTHIDS Thakkar Nevya J1, Shah Kinjal R2, Shah Pinal D3, Mankodi Pradeep C4 1,2,3,4Department of Zoology,Faculty of Science,TheMaharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara, Gujarat, (India) ABSTRACT Zoanthids, benthic Anthozoans are found in nearly all marine environments. Despite their relative abundance, Zoanthids have been overlooked by scholars, because of the intrinsic difficulty in establishing a sound taxonomy based on external morphological criteria and internal structure due to the presence of sand and detritus in their body. In nature these cryptic organisms presents high grade of morphologic diversity especially as colour morphs within a species. This review provides a general introduction to Zoanthids, their ecological and pharmaceutical importance and two different methods of taxonomy i.e. morphological and molecular. Congeneric status of Zoanthids is discussed here through phylogeny. Several Molecular techniques and tools used for phylogenetic studies are summarized that are used by researchers in different biological disciplines. Key Words: DNA barcoding, DNA sequencing, phylogenetic analysis,Zoanthids I. INTRODUCTION Amongst all the animals dwelling in marine environment, few groups have so far not been studied well. The hexacorallian order Zoantharia (Family –Zoanthidea), which are found in shallow water, may also make up a considerable component of some deep-sea coral communities have received very little attention (Sinnigeret al. 2013; Burnettet al. 1997). Over the last decade, deep sea corals have received a considerable attention particularly on seamounts (Miller et al., 2009). Within coral reef communities other than corals mostly benthic molluscs have been studied in details. Even though more in diversity as well as abundance the sponges, zoanthids and actinarians are over looked by scientists. -

Zoanthid (Cnidaria: Anthozoa: Hexacorallia: Zoantharia) Species of Coral Reefs in Palau
Mar Biodiv DOI 10.1007/s12526-013-0180-5 ORIGINAL PAPER Zoanthid (Cnidaria: Anthozoa: Hexacorallia: Zoantharia) species of coral reefs in Palau James Davis Reimer & Doris Albinsky & Sung-Yin Yang & Julien Lorion Received: 3 June 2013 /Revised: 16 August 2013 /Accepted: 20 August 2013 # Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung and Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 Abstract Palau is world famous for its relatively pristine and Introduction highly diverse coral reefs, yet for many coral reef invertebrate taxa, few data exist on their diversity in this Micronesian coun- Palau is located at the southwestern corner of Micronesia, and try. One such taxon is the Zoantharia, an order of benthic is just outside the Coral Triangle, the region with the highest cnidarians within the Class Anthozoa (Subclass Hexacorallia) marine biodiversity in the world (Hoeksema 2007). Thus, Palau that are commonly found in shallow subtropical and tropical is an important link between the central Indo-Pacific and the waters. Here, we examine the species diversity of zoanthids in Pacific Islands, and diversity and distribution data of marine Palau for the first time, based on shallow-water (<35 m) scuba organisms from Palau can help us to understand the evolutionary surveys and morphological identification to create a preliminary and biogeographical history of the region. Because of Palau’s zoanthid species list for Palau. Our results indicated the presence combination of a high habitat diversity with a close proximity to of nine zoanthid species in Palau (Zoanthus sansibaricus, Z. the Coral Triangle, it has the most diverse marine flora and fauna gigantus, Palythoa tuberculosa, P. mutuki, P. -
Three New Species and the Molecular Phylogeny of Antipathozoanthus
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 725: 97–122Three (2017) new species and the molecular phylogeny ofAntipathozoanthus ... 97 doi: 10.3897/zookeys.725.21006 RESEARCH ARTICLE http://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Three new species and the molecular phylogeny of Antipathozoanthus from the Indo-Pacific Ocean (Anthozoa, Hexacorallia, Zoantharia) Hiroki Kise1,2, Takuma Fujii1,3, Giovanni Diego Masucci1, Piera Biondi1, James Davis Reimer1,2,4 1 Molecular Invertebrate Systematics and Ecology Laboratory, Graduate School of Engineering and Science, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213, Japan 2 Palau International Coral Reef Center, 1-M-Dock Road, Koror, Palau 96940 3 Research Center for Island Studies Amami Station, Kagoshima University, Naze-Yanagimachi 2-1, Amami, Kagoshima 894-0032, Japan 4 Tropical Biosphere Research Cen- ter, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213, Japan Corresponding author: Hiroki Kise ([email protected]) Academic editor: B.W. Hoeksema | Received 15 September 2017 | Accepted 7 November 2017 | Published 29 December 2017 http://zoobank.org/E47535C1-21CF-417C-A212-F6E819080565 Citation: Kise H, Fujii T, Masucci GD, Biondi P, Reimer JD (2017) Three new species and the molecular phylogeny of Antipathozoanthus from the Indo-Pacific Ocean (Anthozoa, Hexacorallia, Zoantharia). ZooKeys 725: 97–122.https:// doi.org/10.3897/zookeys.725.21006 Abstract In this study, three new species of macrocnemic zoantharians (Hexacorallia, Zoantharia) are described from localities in the Indo-Pacific Ocean including the Red Sea, the Maldives, Palau, and southern Ja- pan: Antipathozoanthus obscurus sp. n., A. remengesaui sp. n., and A. cavernus sp. -

Investigations Into the Reproductive Patterns
Zoological Studies 49(2): 182-194 (2010) Investigations into the Reproductive Patterns, Ecology, and Morphology in the Zoanthid Genus Palythoa (Cnidaria: Anthozoa: Hexacorallia) in Okinawa, Japan Eriko Shiroma1 and James Davis Reimer2,3,* 1Department of Marine Science, Biology and Chemistry, Faculty of Science, University of the Ryukyus, Senbaru 1, Nishihara, Okinawa 901-0213, Japan 2Molecular Invertebrate Systematics and Ecology, Rising Star Program, Transdisciplinary Research Organization for Subtropical Island Studies, University of the Ryukyus, Senbaru 1, Nishihara, Okinawa 901-0213, Japan 3Marine Biodiversity Research Program, Institute of Biogeosciences, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 2-15 Natsushima, Yokosuka, Kanagawa 237-0061, Japan (Accepted July 16, 2009) Eriko Shiroma and James Davis Reimer (2010) Investigations into the reproductive patterns, ecology, and morphology in the zoanthid genus Palythoa (Cnidaria: Anthozoa: Hexacorallia) in Okinawa, Japan. Zoological Studies 49(2): 182-194. The zoanthid genus Palythoa is found in shallow subtropical and tropical waters worldwide; yet many questions remain regarding the diversity of species and their evolution. Recent progress using molecular techniques has advanced species identifications but also raised new questions. In previous studies, it was hypothesized that P. sp. yoron may be the result of interspecific hybridization between the closely related species P. tuberculosa and P. mutuki. Here, in order to further assess the relationships among these 3 species, their sexual reproductive patterns, distribution, and morphology (tentacle number, colony shape and size, polyp shape, etc.) were investigated in 2008 at Odo Beach, Okinawa, Japan. Results show clear differences in morphology and distribution among all 3 species, with P. sp. yoron apparently intermediate between P. -
Cnidaria, Anthozoa, Zoantharia, Sphenopidae) from Okinawa-Jima Island, Japan
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 606: 11–24 (2016)A new solitary free-living species of the genus Sphenopus... 11 doi: 10.3897/zookeys.606.9310 RESEARCH ARTICLE http://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research A new solitary free-living species of the genus Sphenopus (Cnidaria, Anthozoa, Zoantharia, Sphenopidae) from Okinawa-jima Island, Japan Takuma Fujii1,2, James Davis Reimer3,4 1 Research Center for the Pacific Islands Amami Station, Kagoshima University, Naze-Yanagimachi 2-1, Ama- mi, Kagoshima 894-0032, Japan 2 Graduate School of Engineering and Science, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara-cho, Okinawa 903-0213, Japan 3 Molecular Invertebrate Systematics and Ecology La- boratory, Department of Biology, Chemistry & Marine Sciences, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213, Japan 4 Tropical Biosphere Research Center, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213, Japan Corresponding author: Takuma Fujii ([email protected]) Academic editor: B.W. Hoeksema | Received 23 May 2015 | Accepted 29 June 2016 | Published 21 July 2016 http://zoobank.org/EB98FE3B-665B-4CF2-8E8B-740D167BA2BB Citation: Fujii T, Reimer JD (2016) A new solitary free-living species of the genus Sphenopus (Cnidaria, Anthozoa, Zoantharia, Sphenopidae) from Okinawa-jima Island, Japan. ZooKeys 606: 11–24. doi: 10.3897/zookeys.606.9310 Abstract A new species of free-living solitary zoantharian is described from Okinawa, Japan. Sphenopus exilis sp. n. occurs on silty seafloors in Kin Bay and Oura Bay on the east coast of Okinawa-jima Island.Sphenopus exilis sp. n. is easily distinguished from other Sphenopus species by its small polyp size and slender shape, although there were relatively few differences between Sphenopus exilis sp. -
(Cnidaria, Hexacorallia) from the Galápagos Islands
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 42: 1–36Four (2010) new species and one new genus of zoanthids (Cnidaria, Hexacorallia) from... 1 doi: 10.3897/zookeys.42.378 RESEARCH ARTICLE www.pensoftonline.net/zookeys Launched to accelerate biodiversity research Four new species and one new genus of zoanthids (Cnidaria, Hexacorallia) from the Galápagos Islands James Davis Reimer1,2,†, Takuma Fujii3,‡ 1 Molecular Invertebrate Systematics and Ecology Laboratory, Rising Star Program, Trans-disciplinary Organi- zation for Subtropical Island Studies, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213, Ja- pan 2 Marine Biodiversity Research Program, Institute of Biogeosciences, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 2-15 Natsushima, Yokosuka, Kanagawa 237-0061, Japan 3 Graduate School of Engineering and Science, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213, Japan † urn:lsid:zoobank.org:author:3CD21222-ADA1-4A28-BE8B-7F9A9DEBA0F2 ‡ urn:lsid:zoobank.org:author:5A117804-991D-4F75-889B-7B1844BF4A99 Corresponding author: James Davis Reimer ( [email protected]) Academic editor: Bert W. Hoeksema | Received 31 December 2009 | Accepted 15 March 2010 | Published 1 April 2010 urn:lsid:zoobank.org:pub:7E58A32B-DF8A-4795-B0D6-C37CB3B89A0E Citation: Reimer JD, Fujii T (2010) Four new species and one new genus of zoanthids (Cnidaria, Hexacorallia) from the Galápagos Islands. ZooKeys 42: 1–36. doi: 10.3897/zookeys.42.378 Abstract Recent research has confi rmed the presence of several species of undescribed macrocnemic zoanthids (Cnidaria: Hexacorallia: Zoantharia: Macrocnemina) in the Galápagos. In this study four new species, including two belonging to a new genus, are described. -

Zoanthids of the Cape Verde Islands and Their Symbionts: Previously Unexamined Diversity in the Northeastern Atlantic
Contributions to Zoology, 79 (4) 147-163 (2010) Zoanthids of the Cape Verde Islands and their symbionts: previously unexamined diversity in the Northeastern Atlantic James D. Reimer1, 2, 4, Mamiko Hirose1, Peter Wirtz3 1 Molecular Invertebrate Systematics and Ecology Laboratory, Rising Star Program, Transdisciplinary Research Organization for Subtropical Island Studies (TRO-SIS), University of the Ryukyus, Senbaru 1, Nishihara, Okinawa 903-0213, Japan 2 Marine Biodiversity Research Program, Institute of Biogeosciences, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 2-15 Natsushima, Yokosuka, Kanagawa 237-0061, Japan 3 Centro de Ciências do Mar, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, PT 8005-139 Faro, Portugal 4 E-mail: [email protected] Key words: Cape Verde Islands, Cnidaria, Symbiodinium, undescribed species, zoanthid Abstract Symbiodinium ITS-rDNA ..................................................... 155 Discussion ...................................................................................... 155 The marine invertebrate fauna of the Cape Verde Islands con- Suborder Brachycnemina .................................................... 155 tains many endemic species due to their isolated location in the Suborder Macrocnemina ...................................................... 157 eastern Atlantic, yet research has not been conducted on most Conclusions ............................................................................. 158 taxa here. One such group are the zoanthids or mat anemones, Acknowledgements -

III. MARCO TEORICO 1. TAXONOMÍA El Orden Zoanthidea Ha
III. MARCO TEORICO 1. TAXONOMÍA El orden Zoanthidea ha presentado diferentes clasificaciones taxonómicas a través del tiempo, la primera clasificación es la de Mcmurrich (1889) el cual ubica a las especies de este orden en una sola familia (Zoanthidae) perteneciente a la subtribu Zoanthiae (Fig. 1). La siguiente clasificación la propone Haddon & Shackleton (1891), ellos solo reconocen a la familia Zoanthidae y son los primeros en dividir esta familia en 2 grandes subfamilias basados en sus arreglos mesentéricos: Brachycneminae en los géneros: Zoanthus, Isaurus, Mammillifera, Gemmaria, Palythoa y Sphenopus y Macrocneminae en los géneros: Epizoanthus y Parazoanthus (Fig. 1). En 1898 Duerden continua con la misma clasificación anterior haciendo un solo cambio: elimina el genero Mammillifera del orden Zoanthidea (Fig. 1). En 1902 el mismo investigador cambia el genero Gemmaria por Protopalythoa (Fig. 1). A partir de 1902 existe un vacío en las clasificaciones de este orden pues no se encuentran reportes en la literatura si no hasta 1957 cuando Muller separa el orden Zoanthidea en 2 familias: Zoanthidae y Epizoanthidae (Fig. 1). La siguiente clasificación que se encuentra es la publicada por Mather (1993) y es igual a la reportada por Burnett et al (1996) y Ryland (1997), estos autores dividen el orden 3 Zoanthidea en 2 subórdenes: Brachycnemina con las familias Zoanthidae (géneros Sphenopus, Zoanthus, Isaurus, Palythoa y Protopalythoa) y Neozoanthidae (genero Neozoanthus) y Macrocnemina con las familias Epizoanthidae (géneros Epizoanthus y Thoractus) y Parazoanthidae (géneros Parazoanthus, Isozoanthus y Gerardia); Fig. 1 Mas recientemente, Burnett (2001, en impresion) pide la separación de Sphenopus como género de la familia zoanthidae, ya que según sus investigaciones, basadas en genética molecular, este género pertenece a la familia Sphenopidae Hertwig, 1882 la cual había sido eliminada del orden por no encontrarse diferencias significativas con las otras familias. -

Some Animal Associates of the Zoanthids, Palythoa Mutuki
International Journal of Fisheries and Aquatic Studies 2016; 4(4): 380-384 ISSN: 2347-5129 (ICV-Poland) Impact Value: 5.62 (GIF) Impact Factor: 0.352 Some animal associates of the zoanthids, Palythoa IJFAS 2016; 4(4): 380-384 © 2016IJFAS mutuki (Haddon & Shackeleton, 1891) and Zoanthus www.fisheriesjournal.com sansibaricus (Carlgen, 1990) along rocky shores of Received: 28-05-2016 Accepted: 29-06-2016 Visakhapatnam, India – A check list Myla S Chakravarty Department of Marine Living Myla S Chakravarty, B Shanthi Sudha, PRC Ganesh and Amarnath Resources, Andhra University, Visakhapatnam – 530 003, Dogiparti Andhra Pradesh, India Abstract B Shanthi Sudha Animal associates of zoanthids- Palythoa mutuki and Zoanthus sansibaricus of Lawson’s Bay rocky Department of Marine Living Resources, Andhra University, shores of Visakhapatnam were recorded in the present study. P. mutuki and Z. sansibaricus were found Visakhapatnam – 530 003, distributed along the upper mid-littoral zone of the rocky shores, 21 species and four larval forms Andhra Pradesh, India belonging to five Phyla (Porifera, Annelida, Arthropod, Mollusca and Echinodermata) were recorded. The diversity of organisms associated with P. mutuki was more than with Z. sansibaricus. PRC Ganesh Department of Marine Living Keywords: Animal associates, Palythoa mutuki, Zoanthus sansibaricus Resources, Andhra University, Visakhapatnam – 530 003, 1. Introduction Andhra Pradesh, India The zoanthid species are distributed as encrusting mats along the intertidal rocky shores of Amarnath Dogiparti tropical oceans particularly towards the upper mid-littoral region [1]. They are normally Department of Marine Living exposed during neap tides and are subjected to the pounding action of the waves. Sand Resources, Andhra University, particles, broken shell pieces, sediment etc., are seen attached to the outer walls of the polyps. -

The Sands of Time: Rediscovery of the Genus Neozoanthus (Cnidaria: Hexacorallia) and Evolutionary Aspects of Sand Incrustation in Brachycnemic Zoanthids
Mar Biol DOI 10.1007/s00227-011-1624-8 ORIGINAL PAPER The sands of time: rediscovery of the genus Neozoanthus (Cnidaria: Hexacorallia) and evolutionary aspects of sand incrustation in brachycnemic zoanthids James Davis Reimer • Mamiko Hirose • Yuka Irei • Masami Obuchi • Frederic Sinniger Received: 2 August 2010 / Accepted: 6 January 2011 Ó Springer-Verlag 2011 Abstract The zoanthid family Neozoanthidae (Anthozoa: analyses. Specimens were colonial, partially incrusted with Hexacorallia: Zoantharia) was described in 1973 from large, irregular sand and debris, zooxanthellate, and found Madagascar as a monogeneric and monotypic taxon, and from the intertidal zone to depths of approximately 30 m. never reported again in literature. In 2008–2010, numerous Phylogenetic results utilizing mitochondrial 16S ribosomal zoanthid specimens fitting the morphological description of DNA and cytochrome oxidase subunit I sequences show Neozoanthus were collected in the Ryukyu Islands, Oki- the presence of two Neozoanthus species groups, one each nawa, Japan, and the Great Barrier Reef (GBR), Australia. from Japan and the GBR. Unexpectedly, the molecular Utilizing these specimens, this study re-examines the results also show Neozoanthus to be very closely related to phylogenetic position of Neozoanthidae and analyzes the the genus Isaurus, which as a member of the family evolutionary history of sand incrustation in zoanthids Zoanthidae, is not sand incrusted. These results suggest through phylogenetic and ancestral state reconstruction that during evolution zoanthids can acquire and lose the ability to incrust sand with relative rapidity. Communicated by C. Riginos. Electronic supplementary material The online version of this Introduction article (doi:10.1007/s00227-011-1624-8) contains supplementary material, which is available to authorized users. -

Redalyc.Antioxidant, Hemolytic, Antimicrobial, and Cytotoxic
Anais da Academia Brasileira de Ciências ISSN: 0001-3765 [email protected] Academia Brasileira de Ciências Brasil ALENCAR, DANIEL B.; MELO, ARTHUR A.; SILVA, GISELLE C.; LIMA, REBECA L.; PIRES-CAVALCANTE, KELMA M.S.; CARNEIRO, RÔMULO F.; RABELO, ADRIANA S.; SOUSA, OSCARINA V.; VIEIRA, REGINE H.S.F.; VIANA, FRANCISCO A.; SAMPAIO, ALEXANDRE H.; SAKER-SAMPAIO, SILVANA Antioxidant, hemolytic, antimicrobial, and cytotoxic activities of the tropical Atlantic marine zoanthid Palythoa caribaeorum Anais da Academia Brasileira de Ciências, vol. 87, núm. 2, abril-junio, 2015, pp. 1113- 1123 Academia Brasileira de Ciências Rio de Janeiro, Brasil Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32739721048 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Anais da Academia Brasileira de Ciências (2015) 87(2): 1113-1123 (Annals of the Brazilian Academy of Sciences) Printed version ISSN 0001-3765 / Online version ISSN 1678-2690 http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201520140370 www.scielo.br/aabc Antioxidant, hemolytic, antimicrobial, and cytotoxic activities of the tropical Atlantic marine zoanthid Palythoa caribaeorum DANIEL B. ALENCAR1, ARTHUR A. MELO1, GISELLE C. SILVA2, REBECA L. LIMA1, KELMA M.S. PIRES-CAVALCANTE1, RÔMULO F. CARNEIRO1, ADRIANA S. RABELO1, OSCARINA V. SOUSA2, REGINE H.S.F. VIEIRA2, FRANCISCO A. VIANA3, ALEXANDRE H. SAMPAIO1 and SILVANA SAKER-SAMPAIO1 1Departamento de Engenharia de Pesca, Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, Av. Mister Hull, s/n, Caixa Postal 6043, 60455-970 Fortaleza, CE, Brasil 2Instituto de Ciências do Mar, Universidade Federal do Ceará, Av.