理科の教科書で茎の観察に採用すべき植物材料について Title の一提案( Fulltext )
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Vascular Plants of Massachusetts
The Vascular Plants of Massachusetts: The Vascular Plants of Massachusetts: A County Checklist • First Revision Melissa Dow Cullina, Bryan Connolly, Bruce Sorrie and Paul Somers Somers Bruce Sorrie and Paul Connolly, Bryan Cullina, Melissa Dow Revision • First A County Checklist Plants of Massachusetts: Vascular The A County Checklist First Revision Melissa Dow Cullina, Bryan Connolly, Bruce Sorrie and Paul Somers Massachusetts Natural Heritage & Endangered Species Program Massachusetts Division of Fisheries and Wildlife Natural Heritage & Endangered Species Program The Natural Heritage & Endangered Species Program (NHESP), part of the Massachusetts Division of Fisheries and Wildlife, is one of the programs forming the Natural Heritage network. NHESP is responsible for the conservation and protection of hundreds of species that are not hunted, fished, trapped, or commercially harvested in the state. The Program's highest priority is protecting the 176 species of vertebrate and invertebrate animals and 259 species of native plants that are officially listed as Endangered, Threatened or of Special Concern in Massachusetts. Endangered species conservation in Massachusetts depends on you! A major source of funding for the protection of rare and endangered species comes from voluntary donations on state income tax forms. Contributions go to the Natural Heritage & Endangered Species Fund, which provides a portion of the operating budget for the Natural Heritage & Endangered Species Program. NHESP protects rare species through biological inventory, -

Dispersion of Vascular Plant in Mt. Huiyangsan, Korea
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Elsevier - Publisher Connector Journal of Korean Nature Vol. 3, No. 1 1-10, 2010 Dispersion of Vascular Plant in Mt. Huiyangsan, Korea Hyun-Tak Shin1, Sung-Tae Yoo2, Byung-Do Kim2, and Myung-Hoon YI3* 1Gyeongsangnam-do Forest Environment Research Institute, Jinju 660-871, Korea 2Daegu Arboretum 284 Daegok-Dong Dalse-Gu Daegu 704-310, Korea 3Department of Landscape Architecture, Graduate School, Yeungnam University, Gyeongsan 712-749, Korea Abstract: We surveyed that vascular plants can be classified into 90 families and 240 genus, 336 species, 69 variants, 22 forms, 3 subspecies, total 430 taxa. Dicotyledon plant is 80.9%, monocotyledon plant is 9.8%, Pteridophyta is 8.1%, Gymnosermae is 1.2% among the whole plant family. Rare and endangered plants are Crypsinus hastatus, Lilium distichum, Viola albida, Rhododendron micranthum, totalling four species. Endemic plants are Carex okamotoi, Salix koriyanagi for. koriyanagi, Clematis trichotoma, Thalictrum actaefolium var. brevistylum, Galium trachyspermum, Asperula lasiantha, Weigela subsessilis, Adenophora verticillata var. hirsuta, Aster koraiensis, Cirsium chanroenicum and Saussurea seoulensis total 11 taxa. Specialized plants are 20 classification for I class, 7 classifications for the II class, 7 classifications for the III class, 2 classification for the IV class, and 1 classification for the V class, total 84 taxa. Naturalized plants specified in this study are 10 types but Naturalization rate is not high compared to the area of BaekDu-DaeGan. This survey area is focused on the center of BaekDu- DaeGan, and it has been affected by excessive investigations and this area has been preserved as Buddhist temples' woods. -
Hemiptera, Heteroptera, Miridae, Isometopinae) from Borneo with Remarks on the Distribution of the Tribe
ZooKeys 941: 71–89 (2020) A peer-reviewed open-access journal doi: 10.3897/zookeys.941.47432 RESEARCH ARTICLE https://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Two new genera and species of the Gigantometopini (Hemiptera, Heteroptera, Miridae, Isometopinae) from Borneo with remarks on the distribution of the tribe Artur Taszakowski1*, Junggon Kim2*, Claas Damken3, Rodzay A. Wahab3, Aleksander Herczek1, Sunghoon Jung2,4 1 Institute of Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Faculty of Natural Sciences, University of Silesia in Katowice, Bankowa 9, 40-007 Katowice, Poland 2 Laboratory of Systematic Entomology, Depart- ment of Applied Biology, College of Agriculture and Life Sciences, Chungnam National University, Daejeon, South Korea 3 Institute for Biodiversity and Environmental Research, Universiti Brunei Darussalam, Jalan Universiti, BE1410, Darussalam, Brunei 4 Department of Smart Agriculture Systems, College of Agriculture and Life Sciences, Chungnam National University, Daejeon, South Korea Corresponding author: Artur Taszakowski ([email protected]); Sunghoon Jung ([email protected]) Academic editor: F. Konstantinov | Received 21 October 2019 | Accepted 2 May 2020 | Published 16 June 2020 http://zoobank.org/B3C9A4BA-B098-4D73-A60C-240051C72124 Citation: Taszakowski A, Kim J, Damken C, Wahab RA, Herczek A, Jung S (2020) Two new genera and species of the Gigantometopini (Hemiptera, Heteroptera, Miridae, Isometopinae) from Borneo with remarks on the distribution of the tribe. ZooKeys 941: 71–89. https://doi.org/10.3897/zookeys.941.47432 Abstract Two new genera, each represented by a single new species, Planicapitus luteus Taszakowski, Kim & Her- czek, gen. et sp. nov. and Bruneimetopus simulans Taszakowski, Kim & Herczek, gen. et sp. nov., are described from Borneo. -

Number 3, Spring 1998 Director’S Letter
Planning and planting for a better world Friends of the JC Raulston Arboretum Newsletter Number 3, Spring 1998 Director’s Letter Spring greetings from the JC Raulston Arboretum! This garden- ing season is in full swing, and the Arboretum is the place to be. Emergence is the word! Flowers and foliage are emerging every- where. We had a magnificent late winter and early spring. The Cornus mas ‘Spring Glow’ located in the paradise garden was exquisite this year. The bright yellow flowers are bright and persistent, and the Students from a Wake Tech Community College Photography Class find exfoliating bark and attractive habit plenty to photograph on a February day in the Arboretum. make it a winner. It’s no wonder that JC was so excited about this done soon. Make sure you check of themselves than is expected to seedling selection from the field out many of the special gardens in keep things moving forward. I, for nursery. We are looking to propa- the Arboretum. Our volunteer one, am thankful for each and every gate numerous plants this spring in curators are busy planting and one of them. hopes of getting it into the trade. preparing those gardens for The magnolias were looking another season. Many thanks to all Lastly, when you visit the garden I fantastic until we had three days in our volunteers who work so very would challenge you to find the a row of temperatures in the low hard in the garden. It shows! Euscaphis japonicus. We had a twenties. There was plenty of Another reminder — from April to beautiful seven-foot specimen tree damage to open flowers, but the October, on Sunday’s at 2:00 p.m. -

Agroforestry News Index Vol 1 to Vol 22 No 2
Agroforestry News Index Vol 1 to Vol 22 No 2 2 A.R.T. nursery ..... Vol 2, No 4, page 2 Acorns, edible from oaks ..... Vol 5, No 4, page 3 Aaron, J R & Richards: British woodland produce (book review) ..... Acorns, harvesting ..... Vol 5, No 4, Vol 1, No 4, page 34 page 3 Abies balsamea ..... Vol 8, No 2, page Acorns, nutritional composition ..... 31 Vol 5, No 4, page 4 Abies sibirica ..... Vol 8, No 2, page 31 Acorns, removing tannins from ..... Vol 5, No 4, page 4 Abies species ..... Vol 19, No 1, page 13 Acorns, shelling ..... Vol 5, No 4, page 3 Acca sellowiana ..... Vol 9, No 3, page 4 Acorns, utilisation ..... Vol 5, No 4, page 4 Acer macrophyllum ..... Vol 16, No 2, page 6 Acorus calamus ..... Vol 8, No 4, page 6 Acer pseudoplatanus ..... Vol 3, No 1, page 3 Actinidia arguta ..... Vol 1, No 4, page 10 Acer saccharum ..... Vol 16, No 1, page 3 Actinidia arguta, cultivars ..... Vol 1, No 4, page 14 Acer saccharum - strawberry agroforestry system ..... Vol 8, No 1, Actinidia arguta, description ..... Vol page 2 1, No 4, page 10 Acer species, with edible saps ..... Vol Actinidia arguta, drawings ..... Vol 1, 2, No 3, page 26 No 4, page 15 Achillea millefolium ..... Vol 8, No 4, Actinidia arguta, feeding & irrigaton page 5 ..... Vol 1, No 4, page 11 3 Actinidia arguta, fruiting ..... Vol 1, Actinidia spp ..... Vol 5, No 1, page 18 No 4, page 13 Actinorhizal plants ..... Vol 3, No 3, Actinidia arguta, nurseries page 30 supplying ..... Vol 1, No 4, page 16 Acworth, J M: The potential for farm Actinidia arguta, pests and diseases forestry, agroforestry and novel tree .... -

Chinaxiv:202107.00062V1 中图分类号:Q949 文献标识码:A
ChinaXiv合作期刊 利用叶绿体基因组数据解析锦葵科梧桐亚科的系统位置和 属间关系 黎若竹 1,2,蔡杰 3,杨俊波 3,张志荣 3,李德铢 3,郁文彬 1,4,5* (1. 中国科学院西双版纳热带植物园 综合保护中心,云南 勐腊 666303;2. 中国科学院大 学,北京 100049; 3. 中国科学院昆明植物研究所 中国西南野生生物种质资源库,昆明 650201; 4. 中国科学院核心植物园保护生物学协同中心,云南 勐腊 666303;5. 中国科学 院东南亚生物多样性研究中心,云南 勐腊 666303) 摘 要:分子系统学研究将传统梧桐科与锦葵科、木棉科和椴树科合并为广义锦葵科,并进 一步分为 9 个亚科。然而,9 个亚科之间的关系尚未完全明确,且梧桐亚科内的属间关系也 未得到解决。为了明确梧桐亚科在锦葵科中的系统发育位置,厘清梧桐亚科内部属间系统发 育关系,该研究对锦葵科 8 个亚科进行取样,共选取 55 个样本,基于叶绿体基因组数据, 采用最大似然法和贝叶斯分析构建系统发育树。结果表明:(1)广义锦葵科中,刺果藤亚科 和扁担杆亚科组成 Byttneriina 分支,Malvadendrina 分支中山芝麻亚科为其他亚科的姐妹群, 随后分出梧桐亚科(WCG、LSC 和 SSC 矩阵构成的数据集),以及 Malvatheca 分支(木棉 亚科和锦葵亚科)与非洲芙蓉亚科-椴树亚科的姐妹关系;(2)在梧桐亚科中,可乐果属分 支( Cola clade)是独立一支,随后是酒瓶树属分支(Brachychiton clade)与 苹 婆 属( Sterculia clade)+ 银叶树属分支(Heritiera clade)形成姐妹关系(WCG、LSC 和 CDS 矩阵);(3) 在可乐果属分支(Cola clade)中,可乐果属等为梧桐属(含闭果桐属)和胖大海属+舟翅桐 属的姐妹群。该研究基于叶绿基因组数据基本澄清了广义锦葵科的亚科系统关系以及梧桐亚 科内各属关系,系统发育树框架基本明晰,但梧桐亚科在 Malvadendrina 分支的位置和酒瓶 树属在梧桐亚科的位置,以 及 梧桐属的概念及范围仍需进一步研究,尤其是结合核基因组数 据进行分析。 关键词:梧桐亚科,梧桐属,锦葵科,系统发育基因组,叶绿体基因组 chinaXiv:202107.00062v1 中图分类号:Q949 文献标识码:A 收稿日期:2021-03-24 基金项目:中国科学院重大科技基础设施开放研究项目(2017-LSF-GBOWS-02);云南省万人计划“青年 拔尖人才”[Supported by the Large-scale Scientific Facilities of the Chinese Academy of Sciences (No. 2017-LSF-GBOWS-02); Ten Thousand Talents Program of Yunnan for Top‐notch Young Talents.]。 作者简介:黎若竹(1996- ),硕士研究生,主要研究方向为保护生物学,(E-mail)[email protected]。 *通讯作者:郁文彬,博士,研究员,研究方向为植物系统演化,(E-mail)[email protected]。 1 ChinaXiv合作期刊 Plastid phylogenomics resolving phylogenetic placement and genera phylogeny of Sterculioideae (Malvaceae s. l.) LI Ruozhu1,2, CAI Jie3, YANG Junbo3, ZHANG Zhirong3, LI Dezhu3, YU Wenbin1,4,5* (1. Center for Integrative Conservation, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Mengla 666303, Yunnan, China; 2. -

Universidad De San Carlos De Guatemala Facultad De Ciencias Químicas Y Farmacia
Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia Aislamiento y elucidación estructural de metabolitos secundarios mayoritarios del extracto etanólico de las hojas de la especie Perrottetia longistylis (Manteco, Capulaltapa) y el tamizaje fitoquímico y evaluación de la actividad antifúngica, antibacteriana y citotóxica del extracto etanólico de las hojas de la especie Euonymus enantiophylla (Alís, Rou´j Xiwáan) Familia Celastraceae Carmen Teresa Garnica Marroquín Química Guatemala, junio del 2008 Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia Aislamiento y elucidación estructural de metabolitos secundarios mayoritarios del extracto etanólico de las hojas de la especie Perrottetia longistylis (Manteco, Capulaltapa) y el tamizaje fitoquímico y evaluación de la actividad antifúngica, antibacteriana y citotóxica del extracto etanólico de las hojas de la especie Euonymus enantiophylla (Alís, Rou´j Xiwáan) Familia Celastraceae Informe de tesis Presentado por Carmen Teresa Garnica Marroquín Para optar al título de Química Guatemala, junio del 2008 Tesis Carmen Teresa Garnica Marroquín Junta Directiva Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia Oscar Manuel Cóbar Pinto, Ph.D. Decano Licenciado Pablo Ernesto Oliva Soto Secretario Lillian Raquel Irving Antillón, M.A Vocal I Licenciada Liliana Vides Vocal II Licenciada Beatriz Eugenia Batres Vocal III Bachiller Mariesmeralda Arriaga Monterroso Vocal IV Bachiller José Juan Vega Pérez Vocal V Tesis Carmen Teresa Garnica Marroquín Dedicatoria y Agradecimientos Yo soy una parte de todo aquello que he encontrado en mi camino. Alfred Tennyson Dedicatoria A mis ángeles por ser mi razón de existir, por ser lo que me impulsa a ser mejor cada día y lo que me permite mantener la fe. -
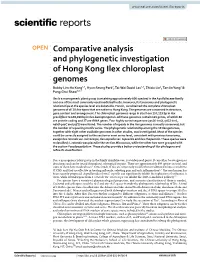
Comparative Analysis and Phylogenetic Investigation of Hong
www.nature.com/scientificreports OPEN Comparative analysis and phylogenetic investigation of Hong Kong Ilex chloroplast genomes Bobby Lim‑Ho Kong1,3, Hyun‑Seung Park2, Tai‑Wai David Lau1,3, Zhixiu Lin4, Tae‑Jin Yang2 & Pang‑Chui Shaw1,3* Ilex is a monogeneric plant group (containing approximately 600 species) in the Aquifoliaceae family and one of the most commonly used medicinal herbs. However, its taxonomy and phylogenetic relationships at the species level are debatable. Herein, we obtained the complete chloroplast genomes of all 19 Ilex types that are native to Hong Kong. The genomes are conserved in structure, gene content and arrangement. The chloroplast genomes range in size from 157,119 bp in Ilex gracilifora to 158,020 bp in Ilex kwangtungensis. All these genomes contain 125 genes, of which 88 are protein‑coding and 37 are tRNA genes. Four highly varied sequences (rps16-trnQ, rpl32-trnL, ndhD-psaC and ycf1) were found. The number of repeats in the Ilex genomes is mostly conserved, but the number of repeating motifs varies. The phylogenetic relationship among the 19 Ilex genomes, together with eight other available genomes in other studies, was investigated. Most of the species could be correctly assigned to the section or even series level, consistent with previous taxonomy, except Ilex rotunda var. microcarpa, Ilex asprella var. tapuensis and Ilex chapaensis. These species were reclassifed; I. rotunda was placed in the section Micrococca, while the other two were grouped with the section Pseudoaquifolium. These studies provide a better understanding of Ilex phylogeny and refne its classifcation. Ilex, a monogeneric plant group in the family Aquifoliaceae, is a widespread genus. -

AQUIFOLIACEAE 1. ILEX Linnaeus, Sp. Pl. 1: 125. 1753
AQUIFOLIACEAE 冬青科 dong qing ke Chen Shukun (陈书坤)1, Ma Haiying (马海英)2, Feng Yuxing (俸宇星)3; Gabrielle Barriera4, Pierre-André Loizeau4 Trees or shrubs, evergreen or deciduous. Leaves alternate, rarely opposite; leaf blade leathery, papery, or membranous, margin entire, serrate, or spinose; stipules minute, persistent or caducous, scar callose; petiole present, rarely absent. Inflorescence a cyme usually of order 1, 2, or 3(–5), respectively composed of a maximum of 1, 3, or 7(–31) developed flowers, axillary, solitary on current year’s branchlets or fasciculate on second year’s branchlets. Plants dioecious. Flowers hypogynous, regular, small, unisexual, by stamens or ovary abortive, 4–6(–23)-merous; calyx persistent; corolla often white or cream, rarely green, yellow, pink, or red; petals imbricate, mostly connate at base up to half of their length. Male flowers: calyx 4–8-lobed; petals 4–8; stamens isomerous, alternating with petals, epipetalous; anthers oblong-ovoid, introrse, longitudinally dehiscent; rudimentary ovary subglobose or pulvinate, rostrate. Female flowers: calyx 4–8-lobed; petals 4–8; staminodes sagittate or cordate, isomerous, alternating with petals, epipetalous; ovary superior, ovoid, 4–8(–10)-loculed, rarely pubescent; style rarely developed; stigma capitate, discoid, or columnar. Fruit a drupe, red, brown, or black (or green in Ilex chapaensis), usually globose; exocarp membranous or papery; mesocarp fleshy. Pyrenes (1–)4–6(–23); endocarp smooth, leathery, woody, or stony, striate, striate-sulcate, or rugose, and/or pitted. One genus and 500–600 species: tropical and subtropical to temperate regions of both the N and S Hemispheres, mainly in the tropical regions of Central and South America and Asia; 204 species (149 endemic) in China, distributed in regions south of the Chang Jiang and Qinling Mountains, mainly in S and SW China. -

Tribu Anthemideae Familia Asteraceae
FamiliaFamilia Asteraceae Asteraceae - Tribu- Tribu Anthemideae Cardueae Hurrell, Julio Alberto Plantas cultivadas de la Argentina : asteráceas-compuestas / Julio Alberto Hurrell ; Néstor D. Bayón ; Gustavo Delucchi. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Hemisferio Sur, 2017. 576 p. ; 24 x 17 cm. ISBN 978-950-504-634-8 1. Cultivo. 2. Plantas. I. Bayón, Néstor D. II. Delucchi, Gustavo III. Título CDD 580 © Editorial Hemisferio Sur S.A. 1a. edición, 2017 Pasteur 743, C1028AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Telefax: (54-11) 4952-8454 e-mail: [email protected] http//www.hemisferiosur.com.ar Reservados todos los derechos de la presente edición para todos los países. Este libro no se podrá reproducir total o parcialmente por ningún método gráfico, electrónico, mecánico o cualquier otro, incluyendo los sistemas de fotocopia y fotoduplicación, registro magnetofónico o de alimentación de datos, sin expreso consentimiento de la Editorial. Hecho el depósito que prevé la ley 11.723 IMPRESO EN LA ARGENTINA PRINTED IN ARGENTINA ISBN 978-950-504-634-8 Fotografías de tapa (Pericallis hybrida) y contratapa (Cosmos bipinnatus) por Daniel H. Bazzano. Esta edición se terminó de imprimir en Gráfica Laf S.R.L., Monteagudo 741, Villa Lynch, San Martín, Provincia de Buenos Aires. Se utilizó para su interior papel ilustración de 115 gramos; para sus tapas, papel ilustración de 300 gramos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Septiembre de 2017. 24 Plantas cultivadas de la Argentina Plantas cultivadas de la Argentina Asteráceas (= Compuestas) Julio A. Hurrell Néstor D. Bayón Gustavo Delucchi Editores Editorial Hemisferio Sur Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017 25 FamiliaFamilia Asteraceae Asteraceae - Tribu- Tribu Anthemideae StifftieaeCardueae Autores María B. -
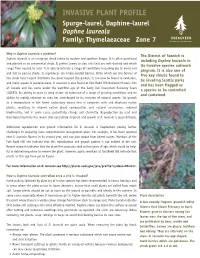
INVASIVE PLANT PROFILE Spurge-Laurel, Daphine-Laurel Daphne Laureola N E E R G R
INVASIVE PLANT PROFILE Spurge-laurel, Daphine-laurel Daphne laureola n e e r g r e Family: Thymelaeaceae Zone 7 v E Why is Daphne laureola a problem? The District of Saanich is Daphne laureola is an evergreen shrub native to western and southern Europe. It is often purchased including Daphne laureola in and planted as an ornamental shrub. It prefers loamy to clay soils that are well-drained and which its invasive species outreach range from neutral to acid. It is able to tolerate a range of conditions including dry to moist soil program. It is also one of and full to partial shade. It reproduces via single-seeded berries. Birds which eat the berries of five key shrubs found to the shrub have helped distribute the plant beyond the garden. It can now be found in roadsides, be invading Seattle parks and moist woods in lowland areas. D. laureola is also found at Fort Rodd Hill National Historic Site and has been flagged as of Canada and has come under the watchful eye of the Garry Oak Ecosystem Recovery Team a species to be controlled (GOERT). Its ability to grow in deep shade, its tolerance of a range of growing conditions and its and contained. ability to rapidly colonize an area has contributed to its invasion of natural spaces. Its growth as a monoculture in the forest understory means that it competes with and displaces native plants, resulting in altered native plant communities and natural succession, reduced biodiversity, and in some cases, potentially change soil chemistry. Reproduction by seed and distribution by birds has meant that controlling dispersal and growth of D. -

Vascular Flora of The
VASCULAR FLORA OF THE UPPER ETOWAH RIVER WATERSHED, GEORGIA by LISA MARIE KRUSE (Under the Direction of DAVID E. GIANNASI) ABSTRACT The Etowah River Basin in North Georgia is a biologically diverse Southern Appalachian River system, threatened by regional population growth. This is a two-part botanical study in the Upper Etowah watershed. The primary component is a survey of vascular flora. Habitats include riparian zones, lowland forest, tributary drainages, bluffs, and uplands. A total of 662 taxa were inventoried, and seventeen reference communities were described and mapped. Small streams, remote public land, and forested private land are important for plant conservation in this watershed. In the second component, cumulative plant species richness was sampled across six floodplain sites to estimate optimal widths for riparian buffer zones. To include 90% of floodplain species in a buffer, 60-75% of the floodplain width must be protected, depending on the stream size. Soil moisture influences species richness, and is dependent on upland water sources. An optimal buffer would protect hydrologic connections between floodplains and uplands. INDEX WORDS: Etowah River, Southeastern United States, floristic inventory, riparian buffer zone, floodplain plant species, plant habitat conservation VASCULAR FLORA OF THE UPPER ETOWAH RIVER WATERSHED, GEORGIA by LISA MARIE KRUSE B.S., Emory University, 1996 A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF SCIENCE