Paleoasia Project Series 32 A01 2020年度研究報告書
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
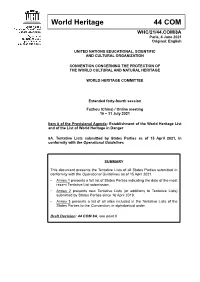
Tentative Lists Submitted by States Parties As of 15 April 2021, in Conformity with the Operational Guidelines
World Heritage 44 COM WHC/21/44.COM/8A Paris, 4 June 2021 Original: English UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE WORLD HERITAGE COMMITTEE Extended forty-fourth session Fuzhou (China) / Online meeting 16 – 31 July 2021 Item 8 of the Provisional Agenda: Establishment of the World Heritage List and of the List of World Heritage in Danger 8A. Tentative Lists submitted by States Parties as of 15 April 2021, in conformity with the Operational Guidelines SUMMARY This document presents the Tentative Lists of all States Parties submitted in conformity with the Operational Guidelines as of 15 April 2021. • Annex 1 presents a full list of States Parties indicating the date of the most recent Tentative List submission. • Annex 2 presents new Tentative Lists (or additions to Tentative Lists) submitted by States Parties since 16 April 2019. • Annex 3 presents a list of all sites included in the Tentative Lists of the States Parties to the Convention, in alphabetical order. Draft Decision: 44 COM 8A, see point II I. EXAMINATION OF TENTATIVE LISTS 1. The World Heritage Convention provides that each State Party to the Convention shall submit to the World Heritage Committee an inventory of the cultural and natural sites situated within its territory, which it considers suitable for inscription on the World Heritage List, and which it intends to nominate during the following five to ten years. Over the years, the Committee has repeatedly confirmed the importance of these Lists, also known as Tentative Lists, for planning purposes, comparative analyses of nominations and for facilitating the undertaking of global and thematic studies. -

Discovery of the Fuyan Teeth: Challenging Or Complementing the Out-Of-Africa Scenario?
ZOOLOGICAL RESEARCH Discovery of the Fuyan teeth: challenging or complementing the out-of-Africa scenario? Yu-Chun LI, Jiao-Yang TIAN, Qing-Peng KONG Although it is widely accepted that modern humans (Homo route about 40-60 kya (Macaulay et al, 2005; Sun et al, 2006). sapiens sapiens) can trace their African origins to 150-200 kilo The lack of human fossils dating earlier than 70 kya in eastern years ago (kya) (recent African origin model; Henn et al, 2012; Eurasia implies that the out-of-Africa immigrants around 100 Ingman et al, 2000; Poznik et al, 2013; Weaver, 2012), an kya likely failed to expand further east (Shea, 2008). Consistent alternative model suggests that the diverse populations of our with this notion, the Late Pleistocene hominid records species evolved separately on different continents from archaic previously found in eastern Eurasia have been dated to only human forms (multiregional origin model; Wolpoff et al, 2000; 40-70 kya, including the Liujiang man (67 kya; Shen et al, 2002) Wu, 2006). The recent discovery of 47 teeth from a Fuyan cave and Tianyuan man (40 kya; Fu et al, 2013b; Shang et al, 2007) in southern China (Liu et al, 2015) indicated the presence of H. in China, the Mungo Man in Australia (40-60 kya; Bowler et al, s. sapiens in eastern Eurasia during the early Late Pleistocene. 1972), the Niah Cave skull from Borneo (40 kya; Barker et al, Since the age of the Fuyan teeth (80-120 kya) predates the 2007) and the Tam Pa Ling cave man in Laos (46-51 kya; previously assumed out-of-Africa exodus (60 kya) by at least 20 Demeter et al, 2012). -

Curriculum Vitae Erik Trinkaus
9/2014 Curriculum Vitae Erik Trinkaus Education and Degrees 1970-1975 University of Pennsylvania Ph.D 1975 Dissertation: A Functional Analysis of the Neandertal Foot M.A. 1973 Thesis: A Review of the Reconstructions and Evolutionary Significance of the Fontéchevade Fossils 1966-1970 University of Wisconsin B.A. 1970 ACADEMIC APPOINTMENTS Primary Academic Appointments Current 2002- Mary Tileston Hemenway Professor of Arts & Sciences, Department of Anthropolo- gy, Washington University Previous 1997-2002 Professor: Department of Anthropology, Washington University 1996-1997 Regents’ Professor of Anthropology, University of New Mexico 1983-1996 Assistant Professor to Professor: Dept. of Anthropology, University of New Mexico 1975-1983 Assistant to Associate Professor: Department of Anthropology, Harvard University MEMBERSHIPS Honorary 2001- Academy of Science of Saint Louis 1996- National Academy of Sciences USA Professional 1992- Paleoanthropological Society 1990- Anthropological Society of Nippon 1985- Société d’Anthropologie de Paris 1973- American Association of Physical Anthropologists AWARDS 2013 Faculty Mentor Award, Graduate School, Washington University 2011 Arthur Holly Compton Award for Faculty Achievement, Washington University 2005 Faculty Mentor Award, Graduate School, Washington University PUBLICATIONS: Books Trinkaus, E., Shipman, P. (1993) The Neandertals: Changing the Image of Mankind. New York: Alfred A. Knopf Pub. pp. 454. PUBLICATIONS: Monographs Trinkaus, E., Buzhilova, A.P., Mednikova, M.B., Dobrovolskaya, M.V. (2014) The People of Sunghir: Burials, Bodies and Behavior in the Earlier Upper Paleolithic. New York: Ox- ford University Press. pp. 339. Trinkaus, E., Constantin, S., Zilhão, J. (Eds.) (2013) Life and Death at the Peştera cu Oase. A Setting for Modern Human Emergence in Europe. New York: Oxford University Press. -

Direct Dating of Neanderthal Remains from the Site of Vindija Cave and Implications for the Middle to Upper Paleolithic Transition
Direct dating of Neanderthal remains from the site of Vindija Cave and implications for the Middle to Upper Paleolithic transition Thibaut Devièsea,1, Ivor Karavanicb,c, Daniel Comeskeya, Cara Kubiaka, Petra Korlevicd, Mateja Hajdinjakd, Siniša Radovice, Noemi Procopiof, Michael Buckleyf, Svante Pääbod, and Tom Highama aOxford Radiocarbon Accelerator Unit, Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, University of Oxford, Oxford OX1 3QY, United Kingdom; bDepartment of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, HR-10000 Zagreb, Croatia; cDepartment of Anthropology, University of Wyoming, Laramie, WY 82071; dDepartment of Evolutionary Genetics, Max-Planck-Institute for Evolutionary Anthropology, D-04103 Leipzig, Germany; eInstitute for Quaternary Palaeontology and Geology, Croatian Academy of Sciences and Arts, HR-10000 Zagreb, Croatia; and fManchester Institute of Biotechnology, University of Manchester, Manchester M1 7DN, United Kingdom Edited by Richard G. Klein, Stanford University, Stanford, CA, and approved July 28, 2017 (received for review June 5, 2017) Previous dating of the Vi-207 and Vi-208 Neanderthal remains from to directly dating the remains of late Neanderthals and early Vindija Cave (Croatia) led to the suggestion that Neanderthals modern humans, as well as artifacts recovered from the sites they survived there as recently as 28,000–29,000 B.P. Subsequent dating occupied. It has become clear that there have been major pro- yielded older dates, interpreted as ages of at least ∼32,500 B.P. We blems with dating reliability and accuracy across the Paleolithic have redated these same specimens using an approach based on the in general, with studies highlighting issues with underestimation extraction of the amino acid hydroxyproline, using preparative high- of the ages of different dated samples from previously analyzed performance liquid chromatography (Prep-HPLC). -

SOM Postscript
This is the final peer-reviewed accepted manuscript of: M. Romandini, G. Oxilia, E. Bortolini, S. Peyrégne, D. Delpiano, A. Nava, D. Panetta, G. Di Domenico, P. Martini, S. Arrighi, F. Badino, C. Figus, F. Lugli, G. Marciani, S. Silvestrini, J. C. Menghi Sartorio, G. Terlato, J.J. Hublin, M. Meyer, L. Bondioli, T. Higham, V. Slon, M. Peresani, S. Benazzi, A late Neanderthal tooth from northeastern Italy, Journal of Human Evolution, 147 (2020), 102867 The final published version is available online at: https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2020.102867 Rights / License: The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. For all terms of use and more information see the publisher's website. This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (https://cris.unibo.it/) When citing, please refer to the published version. Supplementary Online Material (SOM): A late Neanderthal tooth from northeastern Italy This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (https://cris.unibo.it/) When citing, please refer to the published version. SOM S1 DNA extraction, library preparation and enrichment for mitochondrial DNA The tooth from Riparo Broion was sampled in the clean room of the University of Bologna in Ravenna, Italy. After removing a thin layer of surface material, the tooth was drilled adjacent to the cementoenamel junction using 1.0 mm disposable dental drills. Approximately 50 mg of tooth powder were collected. All subsequent laboratory steps were performed at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany, using automated liquid handling systems (Bravo NGS workstation, Agilent Technologies) as described in Rohland et al. -

Geographic Names
GEOGRAPHIC NAMES CORRECT ORTHOGRAPHY OF GEOGRAPHIC NAMES ? REVISED TO JANUARY, 1911 WASHINGTON GOVERNMENT PRINTING OFFICE 1911 PREPARED FOR USE IN THE GOVERNMENT PRINTING OFFICE BY THE UNITED STATES GEOGRAPHIC BOARD WASHINGTON, D. C, JANUARY, 1911 ) CORRECT ORTHOGRAPHY OF GEOGRAPHIC NAMES. The following list of geographic names includes all decisions on spelling rendered by the United States Geographic Board to and including December 7, 1910. Adopted forms are shown by bold-face type, rejected forms by italic, and revisions of previous decisions by an asterisk (*). Aalplaus ; see Alplaus. Acoma; township, McLeod County, Minn. Abagadasset; point, Kennebec River, Saga- (Not Aconia.) dahoc County, Me. (Not Abagadusset. AQores ; see Azores. Abatan; river, southwest part of Bohol, Acquasco; see Aquaseo. discharging into Maribojoc Bay. (Not Acquia; see Aquia. Abalan nor Abalon.) Acworth; railroad station and town, Cobb Aberjona; river, IVIiddlesex County, Mass. County, Ga. (Not Ackworth.) (Not Abbajona.) Adam; island, Chesapeake Bay, Dorchester Abino; point, in Canada, near east end of County, Md. (Not Adam's nor Adams.) Lake Erie. (Not Abineau nor Albino.) Adams; creek, Chatham County, Ga. (Not Aboite; railroad station, Allen County, Adams's.) Ind. (Not Aboit.) Adams; township. Warren County, Ind. AJjoo-shehr ; see Bushire. (Not J. Q. Adams.) Abookeer; AhouJcir; see Abukir. Adam's Creek; see Cunningham. Ahou Hamad; see Abu Hamed. Adams Fall; ledge in New Haven Harbor, Fall.) Abram ; creek in Grant and Mineral Coun- Conn. (Not Adam's ties, W. Va. (Not Abraham.) Adel; see Somali. Abram; see Shimmo. Adelina; town, Calvert County, Md. (Not Abruad ; see Riad. Adalina.) Absaroka; range of mountains in and near Aderhold; ferry over Chattahoochee River, Yellowstone National Park. -

Ancient DNA and Multimethod Dating Confirm the Late Arrival of Anatomically Modern Humans in Southern China
Ancient DNA and multimethod dating confirm the late arrival of anatomically modern humans in southern China Xue-feng Suna,1,2, Shao-qing Wenb,1, Cheng-qiu Luc, Bo-yan Zhoub, Darren Curnoed,2, Hua-yu Lua, Hong-chun Lie, Wei Wangf, Hai Chengg, Shuang-wen Yia, Xin Jiah, Pan-xin Dub, Xing-hua Xua, Yi-ming Lua, Ying Lua, Hong-xiang Zheng (郑鸿翔)b, Hong Zhangb, Chang Sunb, Lan-hai Weib, Fei Hani, Juan Huangj, R. Lawrence Edwardsk, Li Jinb, and Hui Li (李辉)b,l,2 aSchool of Geography and Ocean Science, Nanjing University, 210023 Nanjing, China; bSchool of Life Sciences & Institute of Archaeological Science, Fudan University, Shanghai 200438, China; cHubei Provincial Institute of Cultural Relics and Archeology, 430077 Wuhan, China; dAustralian Museum Research Institute, Australian Museum, Sydney, NSW 2010, Australia; eDepartment of Geosciences, National Taiwan University, 106 Taipei, Taiwan; fInstitute of Cultural Heritage, Shandong University, 266237 Qingdao, China; gInstitute of Global Environmental Change, Xi’an Jiaotong University, 710049 Xi’an, China; hSchool of Geography Science, Nanjing Normal University, 210023 Nanjing, China; iResearch Centre for Earth System Science, Yunnan University, 650500 Kunming, China; jCultural Relics Administration of Daoxian County, Daoxian 425300, China; kDepartment of Geology and Geophysics, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455; and lFudan-Datong Institute of Chinese Origin, Shanxi Academy of Advanced Research and Innovation, 037006 Datong, China Edited by Richard G. Klein, Stanford University, Stanford, CA, and approved November 13, 2020 (received for review September 10, 2020) The expansion of anatomically modern humans (AMHs) from year before present, i.e., before AD1950) Ust’-Ishim femur Africa around 65,000 to 45,000 y ago (ca. -

Sarawak—A Neglected Birding Destination in Malaysia RONALD ORENSTEIN, ANTHONY WONG, NAZERI ABGHANI, DAVID BAKEWELL, JAMES EATON, YEO SIEW TECK & YONG DING LI
30 BirdingASIA 13 (2010): 30–41 LITTLE-KNOWN AREA Sarawak—a neglected birding destination in Malaysia RONALD ORENSTEIN, ANTHONY WONG, NAZERI ABGHANI, DAVID BAKEWELL, JAMES EATON, YEO SIEW TECK & YONG DING LI Introduction It is our hope that this article will be a catalyst One of the ironies of birding in Asia is that despite for change. Alhough much of Sarawak has been the fact that Malaysia is one of the most popular logged and developed, the state still contains destinations for birdwatchers visiting the region, extensive tracts of rainforest habitat; it is still one very few visit the largest state in the country. of the least developed states in Malaysia once away Peninsular Malaysia, and the state of Sabah in east from the four main coastal cities. Given its extensive Malaysia, are well-known and are visited several coastline, Sarawak contains excellent wintering times a year by international bird tour operators grounds for waders and other waterbirds. BirdLife as well as by many independent birdwatchers. But International has designated 22 Important Bird Areas Malaysia’s largest state, Sarawak, which sits (IBAs) in Sarawak, the highest number for any state between the two and occupies one fifth of eastern in Malaysia and more than in all the states of west Borneo, is unfortunately often overlooked by Malaysia combined (18), whilst Sabah has 15 IBAs birdwatchers. The lack of attention given to (Yeap et al. 2007). Sarawak is not only a loss for birders, but also to the state, as the revenue that overseas birdwatchers Why do birders neglect Sarawak? bring in can be a powerful stimulus for protecting That Sarawak is neglected is clear from an examination forests, wetlands and other important bird habitats. -

Human Origin Sites and the World Heritage Convention in Eurasia
World Heritage papers41 HEADWORLD HERITAGES 4 Human Origin Sites and the World Heritage Convention in Eurasia VOLUME I In support of UNESCO’s 70th Anniversary Celebrations United Nations [ Cultural Organization Human Origin Sites and the World Heritage Convention in Eurasia Nuria Sanz, Editor General Coordinator of HEADS Programme on Human Evolution HEADS 4 VOLUME I Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France and the UNESCO Office in Mexico, Presidente Masaryk 526, Polanco, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de Mexico, D.F., Mexico. © UNESCO 2015 ISBN 978-92-3-100107-9 This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). By using the content of this publication, the users accept to be bound by the terms of use of the UNESCO Open Access Repository (http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en). The designations employed and the presentation of material throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The ideas and opinions expressed in this publication are those of the authors; they are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization. Cover Photos: Top: Hohle Fels excavation. © Harry Vetter bottom (from left to right): Petroglyphs from Sikachi-Alyan rock art site. -

Supplementary Information 1
Supplementary Information 1 Archaeological context and morphology of Chagyrskaya 8 Archaeological, spatial and stratigraphical context of Chagyrskaya 8 Chagyrskaya Cave (51°26’32.99’’, 83°09’16.28’’) is located in the mountains of northwestern Altai, on the left bank of the Charysh River (Tigirek Ridge) (Fig. S1.1, A). The cave faces north and is situated at an elevation of 373 m ASL, 19 m above the river. The cave is relatively small and consists of two chambers, spanning a total area of 130 m2 (Fig. S1.1, A, D). Investigations started in 2007 and approximately 35 m2 have been excavated since that time by two teams (Fig. S1.1, D) (1,2). The stratigraphic sequence contains Holocene (layers 1–4) and Pleistocene layers (5-7). The Neandertal artifacts and anthropological remains are associated with layers 6a, 6b, 6c/1 and 6c/2 (Fig. S1.1, E). Among the Upper Pleistocene layers, only the lower layer 6c/2 is preserved in situ, while the upper layers with Neandertal lithics have been re-deposited from that lower layer via colluvial processes (2). Additional evidence of re-deposition is seen in the size sorting of the paleontological remains and bone tools, with the largest bones found in the lower layers 6c/1 and 6c/2, and the smallest bones in the upper layers 5, 6a and 6b (1,2). The Chagyrskaya 8 specimen was found during wet-sieving of layer 6b (horizon 2) in the 2011 field expedition headed by Sergey Markin. Using field documentation, we reconstructed the spatial (Fig. S1.1, B, C) and stratigraphic (Fig. -

Journal of Dental Research
Journal of Dental Research http://jdr.sagepub.com/ New Evidence of Dental Pathology in 40,000-Year-Old Neandertals M.J. Walker, J. Zapata, A. V. Lombardi and E. Trinkaus J DENT RES published online 29 December 2010 DOI: 10.1177/0022034510387797 The online version of this article can be found at: http://jdr.sagepub.com/content/early/2010/12/24/0022034510387797.citation Published by: http://www.sagepublications.com On behalf of: International and American Associations for Dental Research Additional services and information for Journal of Dental Research can be found at: Email Alerts: http://jdr.sagepub.com/cgi/alerts Subscriptions: http://jdr.sagepub.com/subscriptions Reprints: http://www.sagepub.com/journalsReprints.nav Permissions: http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav Downloaded from jdr.sagepub.com at SAGE Publications on February 22, 2011 DISCOVERY! Martin Taubman, Editor M.J. Walker1, J. Zapata1, A.V. Lombardi2, and E. Trinkaus3* New Evidence of Dental 1Area de Antropología Física, Departamento de Zoología Pathology in 40,000-year-old y Antropología Física, Facultad de Biología, Campus Universitario de Espinardo, Universidad de Murcia, 30100 Neandertals Murcia, Spain; 22584 Blossom Lane, New Castle, PA 16105, USA; and 3Department of Anthropology, Washington University, Saint Louis, MO 63130, USA; *corresponding author, [email protected] J Dent Res X(X):xx-xx, XXXX KEY WORDS: caries, cementoma, Neandertals, INTRODUCTION Pleistocene. nlike modern urban humans with a soft refined diet and consequent ram- Upant dental pathology, especially dental caries and periodontal disease, dental and alveolar pathology was relatively rare in Pleistocene humans. This holds true for the Neandertals, who were contemporaneous with and imme- diately preceded modern humans in western Eurasia, between ~200,000 and ~35,000 years ago. -

Life and Death at the Pe Ş Tera Cu Oase
Life and Death at the Pe ş tera cu Oase 00_Trinkaus_Prelims.indd i 8/31/2012 10:06:29 PM HUMAN EVOLUTION SERIES Series Editors Russell L. Ciochon, The University of Iowa Bernard A. Wood, George Washington University Editorial Advisory Board Leslie C. Aiello, Wenner-Gren Foundation Susan Ant ó n, New York University Anna K. Behrensmeyer, Smithsonian Institution Alison Brooks, George Washington University Steven Churchill, Duke University Fred Grine, State University of New York, Stony Brook Katerina Harvati, Univertit ä t T ü bingen Jean-Jacques Hublin, Max Planck Institute Thomas Plummer, Queens College, City University of New York Yoel Rak, Tel-Aviv University Kaye Reed, Arizona State University Christopher Ruff, John Hopkins School of Medicine Erik Trinkaus, Washington University in St. Louis Carol Ward, University of Missouri African Biogeography, Climate Change, and Human Evolution Edited by Timothy G. Bromage and Friedemann Schrenk Meat-Eating and Human Evolution Edited by Craig B. Stanford and Henry T. Bunn The Skull of Australopithecus afarensis William H. Kimbel, Yoel Rak, and Donald C. Johanson Early Modern Human Evolution in Central Europe: The People of Doln í V ĕ stonice and Pavlov Edited by Erik Trinkaus and Ji ří Svoboda Evolution of the Hominin Diet: The Known, the Unknown, and the Unknowable Edited by Peter S. Ungar Genes, Language, & Culture History in the Southwest Pacifi c Edited by Jonathan S. Friedlaender The Lithic Assemblages of Qafzeh Cave Erella Hovers Life and Death at the Pe ş tera cu Oase: A Setting for Modern Human Emergence in Europe Edited by Erik Trinkaus, Silviu Constantin, and Jo ã o Zilh ã o 00_Trinkaus_Prelims.indd ii 8/31/2012 10:06:30 PM Life and Death at the Pe ş tera cu Oase A Setting for Modern Human Emergence in Europe Edited by Erik Trinkaus , Silviu Constantin, Jo ã o Zilh ã o 1 00_Trinkaus_Prelims.indd iii 8/31/2012 10:06:30 PM 3 Oxford University Press is a department of the University of Oxford.