2-5 世界のロケット打ち上げ射場 2-5 世界のロケット打ち上げ射場 2-5-1 世界の主要ロケット打ち上げ射場一覧 (2008年2月現在)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MIT Japan Program Working Paper 01.10 the GLOBAL COMMERCIAL
MIT Japan Program Working Paper 01.10 THE GLOBAL COMMERCIAL SPACE LAUNCH INDUSTRY: JAPAN IN COMPARATIVE PERSPECTIVE Saadia M. Pekkanen Assistant Professor Department of Political Science Middlebury College Middlebury, VT 05753 [email protected] I am grateful to Marco Caceres, Senior Analyst and Director of Space Studies, Teal Group Corporation; Mark Coleman, Chemical Propulsion Information Agency (CPIA), Johns Hopkins University; and Takashi Ishii, General Manager, Space Division, The Society of Japanese Aerospace Companies (SJAC), Tokyo, for providing basic information concerning launch vehicles. I also thank Richard Samuels and Robert Pekkanen for their encouragement and comments. Finally, I thank Kartik Raj for his excellent research assistance. Financial suppport for the Japan portion of this project was provided graciously through a Postdoctoral Fellowship at the Harvard Academy of International and Area Studies. MIT Japan Program Working Paper Series 01.10 Center for International Studies Massachusetts Institute of Technology Room E38-7th Floor Cambridge, MA 02139 Phone: 617-252-1483 Fax: 617-258-7432 Date of Publication: July 16, 2001 © MIT Japan Program Introduction Japan has been seriously attempting to break into the commercial space launch vehicles industry since at least the mid 1970s. Yet very little is known about this story, and about the politics and perceptions that are continuing to drive Japanese efforts despite many outright failures in the indigenization of the industry. This story, therefore, is important not just because of the widespread economic and technological merits of the space launch vehicles sector which are considerable. It is also important because it speaks directly to the ongoing debates about the Japanese developmental state and, contrary to the new wisdom in light of Japan's recession, the continuation of its high technology policy as a whole. -

05/31/2017 Taylor County Acctpa21 Time: 16:10:10 Check Register − Disbursement Fund
PAGE NUMBER: 1 DATE: 05/31/2017 TAYLOR COUNTY ACCTPA21 TIME: 16:10:10 CHECK REGISTER − DISBURSEMENT FUND SELECTION CRITERIA: transact.ck_date between ’20170501 00:00:00.000’ and ’20170531 00:00:00.000’ ACCOUNTING PERIOD: 8/17 FUND − 411 − GENERAL CLEARING CASH ACCT CHECK NO ISSUE DT VENDOR NAME DEPARTMENT −−−−−DESCRIPTION−−−−−− SALES TAX AMOUNT 1001 1015498 05/02/17 1671 A−1 VACUUMS 6570 WINSOR REPAIR 0.00 45.00 1001 1015499 05/02/17 4178 BRANDON ABBOTT 6010 DAYTON 0.00 76.00 1001 1015500 05/02/17 2088 ABERCROMBIE PEST CONTROL 3075 PEST CNTRL SRV 0.00 45.00 1001 1015501 05/02/17 1063 ABILENE AUTO GLASS 6010 14−17 TAHOE 0.00 389.00 1001 1015502 05/02/17 1709 ABILENE DIAGNOSTIC, PLLC 7010 VARIOUS PEOPLE 0.00 177.89 1001 1015503 05/02/17 2170 ABILENE GENERAL TIRE CO. 5400 FLT RPR,TIRE SEALNT 0.00 47.50 1001 1015504 05/02/17 2021 ABILENE HYDRAULICS, LLC 5300 HYD CYLNDR RPR 0.00 180.00 1001 1015505 05/02/17 1087 BMC ABILENE LUMBER 5015 2X6 0.00 131.66 1001 1015506 05/02/17 1089 ABILENE MAINTENANCE SUPP 6570 FILTERS 0.00 94.00 1001 1015506 05/02/17 1089 ABILENE MAINTENANCE SUPP 6570 TISSUE,TWL,LNR,GLOVES 0.00 241.60 TOTAL CHECK 0.00 335.60 1001 1015507 05/02/17 1097 APSCO 6550 VALVE KIT,PVC,HOSE 0.00 70.78 1001 1015507 05/02/17 1097 APSCO 6550 TEE,BUSHING,GLUE 0.00 290.63 1001 1015507 05/02/17 1097 APSCO 5030 TEE,FAUCET,COUP 0.00 141.43 1001 1015507 05/02/17 1097 APSCO 5030 ANGLE STOP, NIPPLE 0.00 28.86 1001 1015507 05/02/17 1097 APSCO 6550 BUSHING 0.00 85.37 1001 1015507 05/02/17 1097 APSCO 6550 UNION,MIP,TUBING 0.00 117.54 1001 1015507 05/02/17 -

<> CRONOLOGIA DE LOS SATÉLITES ARTIFICIALES DE LA
1 SATELITES ARTIFICIALES. Capítulo 5º Subcap. 10 <> CRONOLOGIA DE LOS SATÉLITES ARTIFICIALES DE LA TIERRA. Esta es una relación cronológica de todos los lanzamientos de satélites artificiales de nuestro planeta, con independencia de su éxito o fracaso, tanto en el disparo como en órbita. Significa pues que muchos de ellos no han alcanzado el espacio y fueron destruidos. Se señala en primer lugar (a la izquierda) su nombre, seguido de la fecha del lanzamiento, el país al que pertenece el satélite (que puede ser otro distinto al que lo lanza) y el tipo de satélite; este último aspecto podría no corresponderse en exactitud dado que algunos son de finalidad múltiple. En los lanzamientos múltiples, cada satélite figura separado (salvo en los casos de fracaso, en que no llegan a separarse) pero naturalmente en la misma fecha y juntos. NO ESTÁN incluidos los llevados en vuelos tripulados, si bien se citan en el programa de satélites correspondiente y en el capítulo de “Cronología general de lanzamientos”. .SATÉLITE Fecha País Tipo SPUTNIK F1 15.05.1957 URSS Experimental o tecnológico SPUTNIK F2 21.08.1957 URSS Experimental o tecnológico SPUTNIK 01 04.10.1957 URSS Experimental o tecnológico SPUTNIK 02 03.11.1957 URSS Científico VANGUARD-1A 06.12.1957 USA Experimental o tecnológico EXPLORER 01 31.01.1958 USA Científico VANGUARD-1B 05.02.1958 USA Experimental o tecnológico EXPLORER 02 05.03.1958 USA Científico VANGUARD-1 17.03.1958 USA Experimental o tecnológico EXPLORER 03 26.03.1958 USA Científico SPUTNIK D1 27.04.1958 URSS Geodésico VANGUARD-2A -

Kata Pengantar
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja) LAPAN dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2019. Laporan ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban Pusfatja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan penetapan kinerja pada tahun anggaran 2019. Laporan ini memaparkan data dan analisis secara komprehensif terhadap hasil kinerja yang telah dicapai Pusfatja pada Tahun Anggaran 2019 atau tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Pusfatja Tahun 2015-2019. Laporan disusun secara sistematis berdasarkan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang dijabarkan dalam DIPA Pusfatja tahun 2019 untuk menghasilkan akuntabilitas kinerja. Penyajian laporan ini disusun secara berurutan mulai dari uraian tugas dan fungsi serta organisasi Pusfatja, kemudian perencanaan kinerja yang meliputi rencana strategis tahun 2015-2019 dan penetapan kinerja tahun 2019, serta akuntabilitas kinerja tahun 2019 meliputi capaian kinerja Pusfatja beserta analisisnya dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusfatja tahun 2019. Sebagai penutup laporan, dipaparkan simpulan umum atas capaian kinerja Pusfatja. Pada laporan ini juga dilampirkan data-data pendukung berupa Rencana Strategis Pusfatja 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, untuk memperkuat informasi yang dijelaskan dalam laporan. LAKIN Pusfatja tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran i kinerja Pusfatja yang terkait dengan PK 2019 atau capaian tahun 2019 berdasarkan Renstra PUSFATJA tahun 2015-2019 dan Keputusan Kepala No 251 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Penginderaan Jauh. -

Power, Propulsion, and Communications for Microspacecraft Missions
NASA / CRm1998-206607 Power, Propulsion, and Communications for Microspacecraft Missions W.A. de Groot, T.M. Maloney, and M.J. Vanderaar NYMA, Inc., Brook Park, Ohio Prepared for the COSPAR Colloquium on Scientific Microsatellites cosponsored by the Committee on Space Research, International Academy of Astronautics, and the National Science Council (NSC) Tainan, Taiwan, ROC, December 14-17, 1997 Prepared under Contract NAS3-27186 National Aeronautics and Space Administration Lewis Research Center March 1998 Available from NASA Center for Aerospace Information National Technical Information Service 800 Elkridge Landing Road 5287 Port Royal Road Linthicum Heights, MD 21090-2934 Springfield, VA 22100 Price Code: A03 Price Code: A03 POWER, PROPULSION, AND COMMUNICATIONS FOR MICROSPACECRAFT MISSIONS W. A. de Groot, T. M. Maloney, and M. J. Vanderaar Nyma Inc., 2001 Aerospace Parkway Brook Park, OH 44142, USA ABSTRACT The development of small sized, low weight spacecraft should lead to reduced scientific mission costs by lowering fabrication and launch costs. An order of magnitude reduction in spacecraft size can be obtained by miniaturizing components. Additional reductions in spacecraft weight, size, and cost can be obtained by utilizing the synergy that exists between different spacecraft systems. The state-of-the-art of three major systems, spacecraft power, propulsion, and communications is discussed. Potential strategies to exploit the synergy between these systems and/or the payload are identified. Benefits of several of these synergies are discussed. INTRODUCTION In an era of continually shrinking budgets it is prudent to investigate means of reducing le+5 ISS e spacecraft mission costs. These costs can o MIR • bi roughly be divided among three categories: a. -

Aeronauticalengineering
NASA SP-7037 (308) September 1994 AERONAUTICALENGINEERING SI 001 SP7037(308 940922 S090569 A NASA CENTER FOR AERGSPACE INFORMATION ACCESSIONING 800 ELKRIDGE LANOING ROAD LINTHICUM HEIGHTS MD 210902934 A CONTINUING BIBLIOGRAPHYWITH INDEXES (NASA-SP-7037(308)) AERONAUTICAL N95-11371 ENGINEERING: A CONTINUING BIBLIOGRAPHY WITH INDEXES (SUPPLEMENT 308) (NASA) 95 p Unclas 00/01 0024954 The NASA STI Program ... in Profile Since its founding, NASA has been dedicated to the advancement of aeronautics and space science. The NASA Scientific and Technical Information (STI) Program plays a key part in helping NASA maintain this important role. The NASA STI Program provides access to the NASA STI Database, the largest collection of aeronautical and space science STI in the world. The Program is also NASA's institutional mechanism for disseminating the results of its research and development activities. Specialized services that help round out the Program's diverse offerings include creating custom thesauri, translating material to or from 34 foreign languages, building customized databases, organizing and publishing research results ... even providing videos. For more information about the NASA STI Program, you can: • Phone the NASA Access Help Desk at (301) 621-0390 • Fax your question to the NASA Access Help Desk at (301) 621-0134 • E-mail your question via the Internet to [email protected] • Write to: NASA Access Help Desk NASA Center for AeroSpace Information 800 Elkridge Landing Road Linthicum Heights, MD 21090-2934 NASA SP-7037 (308) September 1994 AERONAUTICALENGINEERING A CONTINUING BIBLIOGRAPHY WITH INDEXES National Aeronautics and Space Administration Scientific and Technical Information Program Washington, DC 1994 This publication was prepared by the NASA Center for AeroSpace Information, 800 Elkridge Landing Road, Linthicum Heights, MD 21090-2934, (301) 621-0390. -

In Kepler's Gardens
In Kepler’s Gardens A global journey mapping the ‘new’ world Edited by Gerfried Stocker / Christine Schöpf / Hannes Leopoldseder Ars Electronica 2020 Festival for Art, Technology, and Society September 9 — 13, 2020 Ars Electronica, Linz Editors: Hannes Leopoldseder, Christine Schöpf, Gerfried Stocker Editing: Veronika Liebl, Anna Grubauer, Maria Koller, Alexander Wöran Translations: German — English: Douglas Deitemyer, Daniel Benedek Copyediting: Laura Freeburn, Mónica Belevan Graphic design and production: Main layout: Cornelia Prokop, Lunart Werbeagentur Cover: Gerhard Kirchschläger Minion Typeface: IBM Plex Sans PEFC Certified This product is from Printed by: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., Linz sustainably managed forests and controlled sources Paper: MagnoEN Bulk 1,1 Vol., 115 g/m², 300 g/m² www.pefc.org PEFC Certified © 2020 Ars Electronica PEFC Certified PEFC Certified This product is This product is This product is PEFC Certified © 2020 for the reproduced works by the artists, from sustainably from sustainably from sustainably This product is from managed forests or their legal successors managed forests managed forests sustainably managed and controlled and controlled and controlled forests and controlled sources Published by sources sources sources Hatje Cantz Verlag www.pefc.org www.pefc.org www.pefc.org www.pefc.org Mommsenstrasse 27 10629 Berlin PEFC Certified Germany This product is from www.hatjecantz.com sustainably managed forests and controlled A Ganske Publishing Group company sources www.pefc.org Hatje Cantz -
1975 Gsfc Battery Workshop
TF; 1975 GSFC BATTERY WORKSHOP (NAS3-TI?-X-71-34) IH'r 1975 GSFC EAT'XERY UOFKSHCE (SASX) 342 F HC P19.CL CSCL 1CC Unclas ~3144 41513 THE 1975 GSFC BATTERY WORKSHOP November 1975 GODDARD SPACE FLIGHT CENTER Greenbelt, Maryland CONTENTS -Page INTRODUCTION TO KEYNOTE ADDRESS, F. FO~~/GSFC........ 1 KEYNOTE ADDRESS, J. ~urcell/~~F~.................. 1 STANDARD CELL/BATTERY, G. Halpert/GSFC. ............ 4 SEPARATORS (Chairman: G. Halpert/GSFC) 1. DEGRADATION OF NYLON, H. ~im/HughesResearch ..... 9 2. CYCLE TEST RESULTS, NYLON & POLYPROPYLENE, T. Henningan/GSFC ..................... 16 3. CADMIUM MIGRATION IN SEPARATORS, P. ~c~ermott/ Coppin State College ..................... 19 4. TEFLONATED ELECTRODES, L. Miller/Eagle Picher. .... 2 8 CHEMICAL ANALYSIS (Chairman: G. ~alpert/GSFC) 1. ELECTROLYTE DISTRIBUTION & POTENTIALS, Dr. L. May/ Catholic University ...................... 34 2. REFERENCE ELECTRODE TECHNOLOGY, S. ~rause/ Hughes Aircraft. ....................... 39 CELL MANUFACTURING (Chairman: F. ~ord/GsFC) 1. TEFLONATED NEGATIVES, S. Kraclse/Hughes Aircraft .... 4 5 2. PERFORMANCE OF PLATES FROM DIFFERENT SPIRALS, Dr. W. Scott/TRW ...................... 4 9 3. LEAK DETECTION IN CELLS, S. ~ross/~oeing......... 59 4. PULSE CHARGING, Dr. H. Cheh/Columbia University ..... 6 2 5. REWORKING CELLS - ELECTROLYTE REMOVAL, F. Ford/GSFC ........................ 7 0 iii CONTENTS (continued) -Page OPEN DISCUSSION (Chairman: F. Ford/GSFC) ............. 79 Panel Members: Dr. W. Scott/TRW; S. Krause/HAC; F. Betz/NRL; S. ~ross/~oeing;G. H~~P~~~/GSFC FLIGHT BATTERY EXPERIENCE (Chairman: W. ~ebster/GSFC) 1. RESULTS FROM LOW EARTH ORBIT TESTING FOR 3S0, S. Krause/Hughes Aircraft. ................. 2. LIFE CYCLE TEST DATA, ATS-6 & OSO-8, W. Webster/ GSFC ............................. 3. SMS BATTERY PERFORMANCE, J. Armantrout/ Aeronutronic- Ford ..................... -
Disbursements Register for 10/1/2016 to 9/30/2017 County of Galveston
County of Galveston Disbursements Register for 10/1/2016 to 9/30/2017 Date Payee Amount Description 10/04/2016 AECOM TECHNICAL SERVICES INC 13,893.46 61st Street Boat Ramp and Wash 10/04/2016 AID TO VICTIMS OF DOMESTIC ABUSE 1,665.00 BIPP COUNSELING FOR THE MONTH 10/04/2016 ALWAYS SAFETY AND 1ST AID INC 1,058.25 BLANKET FOR SAFETY & FIRST AID 10/04/2016 AMERICAN ASSOCIATION OF NOTARIES INC. 91.94 Notary Seal for Darla Cox ~ Te 10/04/2016 AMERICAN FENCE AND SUPPLY CO 351.37 ITEM 010-B40238 BLK 2-3/8'X 8' 10/04/2016 AMERICAN STAMP & MARKETING PRODUCTS 965.54 Repair 1 Rapid Print Machine # 10/04/2016 AQUATEX WATER CONDITIONING INC 154.00 TROUBLESHOOT/REPAIR WATER SOFT 10/04/2016 B&H FOTO & ELECTRONICS CORP 31.73 Epson Ink Maintenance Tank 10/04/2016 BACLIFF BUILDERS SUPPLY INC. 351.94 BLANKET FOR DRAINAGE CREW SUPP 10/04/2016 BAYGAS INC 185.36 BLANKET FOR PROPANE GAS TO HEA 10/04/2016 BEIRNE MAYNARD & PARSONS LLP 28,949.69 BEIRNE, MAYNARD & PARSONS, LLP 10/04/2016 BOSWORTH PAPERS INC 56.21 File box labels 8.5 x 11 60# S 10/04/2016 BROOKSIDE EQUIPMENT 69.30 BLANKET PO FOR REPAIR PARTS AN 10/04/2016 BUILDING PRODUCTS PLUS 1,312.50 6X6 WITH 5/8 DRILL HOLE BALLOR 10/04/2016 BUYATHREAD 504.00 POLO SHIRTS WITH "JJTLC" ROUND 10/04/2016 CAP FLEET UPFITTERS 5,692.80 BLANK PO REQUEST FOR CAP FLEET 10/04/2016 CARNES FUNERAL HOME INC 7,025.00 BLANKET-TRANSPORTATION OF DEAD 10/04/2016 CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY CO 492.33 Cat #674291 L920H-CA(R) Butte 10/04/2016 CENTERPOINT ENERGY 79.83 BLANKET PURCHASE ORDER FOR GAS 10/04/2016 CHERRY CRUSHED CONCRETE INC 24,349.11 Recycled Crushed Concrete 10/04/2016 CITY OF GALVESTON 360.29 CONTRACT RENTAL GALV HANGAR 10/04/2016 CLASSIC AUTOPLEX F-T LLC 2,400.74 BLANKET PO REQUEST FOR CLASSIC 10/04/2016 COASTAL WIPERS INC 525.00 White Cotton Huck 10/04/2016 COBURN SUPPLY COMPANY INC 9,429.39 HVAC SUPPLIES AND EQUIPMENT AS 10/04/2016 COMCAST COMMERCIAL SERVICES LLC 146.27 Cabling and Internet service f 10/04/2016 COMPETITIVE CHOICE, INC. -

Winter 1994 Gems & Gemology
TABL CONTENTS EDITORIAL Gems o> Gemology: Sixty Years of History and History-Making Richard T. Liddicoat FEATURE ARTICLE Color Grading of Colored Diamonds in the GIA Gem Trade Laboratory fohn M.King, Thomas M. Moses, Tames E. Shigley, and Yan Liu NOTES AND NEW TECHNIQUES Ruby and Sapphire from the Southern Ural Mountains, Russia Alexander 1. Kissin Gem Corundum in Alkali Basalt: Origin and Occurrence A. A. Levinson and P. A. Cook REGULAR FEATURES 264 Gem Trade Lab Notes 271 GemNews 281 Book Reviews 282 Gemological Abstracts 291 Annual Index ABOUT THE COVER: Colored diamonds are among the most intriguing and valuable ge111s,This issue presents, for the first time, a report on how the CIA Gem Trade Laboratory color gnides colored diamonds. The diamonds here illustrate some of the exciting colors. They were provided by: American Siba, Cora Diamond Corp., U. Doppelt a) Co., Ishaia Trading Corp., I. Wolf,L. Wolf, B. Zuclzer, and CIA GTL. The descriptions below reflect the color grades that would be given on the new grading reports (clue to printing fluctuations, color reproduct ion may not be exact): (1)2.73 ct Fancy black; (2) 22,28 ct Fancy ftayisli yellowish yew ("chameleon");(3) 20.95 ct Fancy Intense yellow (Internally Flawless); (4) 1.56 ct Fancy Deep orange; (-5) 5.30 ct Fancy green; (6) 5.59 ct Fancy gray-blue; (7)0.46 ct Fancy Intense pink; (8) 5.26 ct Fancy gray-blue; (9)2.20 ci Fancy Deep brownish yellowish orange: (20) 4.49 ct Fancy Deep greenish yellow; (11) 20.17 ct Fancy Deep blue; (12) 1.49 ct Fancy Intense yellowish orange; -
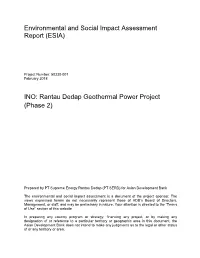
Rantau Dedap Geothermal Power Project (Phase 2)
Environmental and Social Impact Assessment Report (ESIA) Project Number: 50330-001 February 2018 INO: Rantau Dedap Geothermal Power Project (Phase 2) Prepared by PT Supreme Energy Rantau Dedap (PT SERD) for Asian Development Bank The environmental and social impact assessment is a document of the project sponsor. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB’s Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. Your attention is directed to the “Terms of Use” section of this website. In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of or any territory or area. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT 250MW Rantau Dedap Geothermal Power Plant (Phase 1- 92MW) South Sumatra, Indonesia DRAFT FINAL 24 January 2018 2401 2018 Environmental and Social Impact Assessment and Management Plan EXECUTIVE SUMMARY DESCRIPTION OF PROJECT PT Supreme Energy Rantau Dedap (PT SERD) is a Joint Venture of Supreme Energy, Engie, and Marubeni to develop a geothermal power plant with 250MW (gross) installed capacity the Pojet crossing two regencies (Muara Enim and Lahat) and one city (Pagar Alam) in South Sumatra Province. The Project location is approximately 225 km from Palembang, the capital city of South Sumatra. PT “E‘Ds Geotheal Wokig Aea Peit oes the ‘atau Dedap geotheal pospet aea. Developing geothermal energy is of strategic importance to the Government of Indonesia (GoI) which targets to generate a total of new 35,000MW by 2025 of which 23% (8,100MW) are aimed to be from renewable resources. -

Job Room Type Faces
/ HIS BOOK is the prop- erty of the Government Printing Office, and may be called for at any time. fl Please do not mutilate or destroy it. & & t* t* & JOB ROOM GOVERNMENT PR INTING OFFICE WASHINGTON 1904 r: vW' ; f r^ v Jj i> r r- Vilii ~'w^ j \ \ NEW GOVERNMENT PRINTING OFFICE Specimen Book - AND ** CATALOGUE ** Showing Faces of the Body and Job Types, Borders, Ornaments, Brass Rule, Cuts, etc., now in stock in the Job Room of this Office FEBRUARY, 1904 JOB ROOM GOVERNMENT PRINTING OFFICE Regarding Requisitions £# SEPARATE requisition muSt be made with each order. This will save time, trouble, A etc., as well as diminish the chances of making errors. It is not necessary, however, to make separate requisition for printing and binding when books are ordered. This [Si ScS ‘S3 # Office is not authorized to furnish blank paper, and all requisitions muSt be for cS cS cS c&ic&oc&o printing or binding. S S tS c&o <&« W Under the law all books, except record or account books, muS be bound in plain sheep or cloth, except books for Libraries of Congress, Surgeon General’s Office, State Department, and Patent Office. All requisitions muSt conform thereto. Copy muSt invariably accompany the requisition and should be attached thereto—requisition on top. Making a requisition for a certain form or book, and referring to an order for work of a similar Style made weeks or months previously, is liable to lead to mistakes and delays, and such requests will not be entertained by this Office.