農村JR13064 農業セクター.Indb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Integrated Regional Information Network (IRIN): Burundi
U.N. Department of Humanitarian Affairs Integrated Regional Information Network (IRIN) Burundi Sommaire / Contents BURUNDI HUMANITARIAN SITUATION REPORT No. 4...............................................................5 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 26 July 1996 (96.7.26)..................................................9 Burundi-Canada: Canada Supports Arusha Declaration 96.8.8..............................................................11 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 14 August 1996 96.8.14..............................................13 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 15 August 1996 96.8.15..............................................15 Burundi: Statement by the US Catholic Conference and CRS 96.8.14...................................................17 Burundi: Regional Foreign Ministers Meeting Press Release 96.8.16....................................................19 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 16 August 1996 96.8.16..............................................21 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 20 August 1996 96.8.20..............................................23 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 21 August 1996 96.08.21.............................................25 Burundi: Notes from Burundi Policy Forum meeting 96.8.23..............................................................27 Burundi: IRIN Summary of Main Events for 23 August 1996 96.08.23................................................30 Burundi: Amnesty International News Service 96.8.23.......................................................................32 -

The Burundi Peace Process
ISS MONOGRAPH 171 ISS Head Offi ce Block D, Brooklyn Court 361 Veale Street New Muckleneuk, Pretoria, South Africa Tel: +27 12 346-9500 Fax: +27 12 346-9570 E-mail: [email protected] Th e Burundi ISS Addis Ababa Offi ce 1st Floor, Ki-Ab Building Alexander Pushkin Street PEACE CONDITIONAL TO CIVIL WAR FROM PROCESS: THE BURUNDI PEACE Peace Process Pushkin Square, Addis Ababa, Ethiopia Th is monograph focuses on the role peacekeeping Tel: +251 11 372-1154/5/6 Fax: +251 11 372-5954 missions played in the Burundi peace process and E-mail: [email protected] From civil war to conditional peace in ensuring that agreements signed by parties to ISS Cape Town Offi ce the confl ict were adhered to and implemented. 2nd Floor, Armoury Building, Buchanan Square An AU peace mission followed by a UN 160 Sir Lowry Road, Woodstock, South Africa Tel: +27 21 461-7211 Fax: +27 21 461-7213 mission replaced the initial SA Protection Force. E-mail: [email protected] Because of the non-completion of the peace ISS Nairobi Offi ce process and the return of the PALIPEHUTU- Braeside Gardens, Off Muthangari Road FNL to Burundi, the UN Security Council Lavington, Nairobi, Kenya Tel: +254 20 386-1625 Fax: +254 20 386-1639 approved the redeployment of an AU mission to E-mail: [email protected] oversee the completion of the demobilisation of ISS Pretoria Offi ce these rebel forces by December 2008. Block C, Brooklyn Court C On 18 April 2009, at a ceremony to mark the 361 Veale Street ON beginning of the demobilisation of thousands New Muckleneuk, Pretoria, South Africa DI Tel: +27 12 346-9500 Fax: +27 12 460-0998 TI of PALIPEHUTU-FNL combatants, Agathon E-mail: [email protected] ON Rwasa, leader of PALIPEHUTU-FNL, gave up AL www.issafrica.org P his AK-47 and military uniform. -

Rapport Octobre 2013
Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues « A.PRO.D.H. » RAPPORT MENSUEL D’OCTOBRE 2013 0. INTRODUCTION Le présent rapport est un condensé de toutes les violations des droits humains enregistrées par nos observateurs provinciaux. En plus des violations des droits humains enregistrées, il relève les améliorations par rapport aux mois passés. L’appréciation de la situation des droits humains procède par l’analyse du contexte sécuritaire, politique, judiciaire et social qui a prévalu au cours du mois car le respect de la dignité humaine ou bien l’atteinte aux libertés fondamentales de la personne humaine est une fonction directe de l’évolution du climat qui règne entre les citoyens, vu sous les 4 angles. La première partie du présent rapport concerne sur cette analyse. En second lieu, nous mettrons en exergue les différents cas d’atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique en relevant autant que faire se peut, les circonstances dans lesquelles les victimes ont été tuées ou ont subi de mauvais traitements. Les cas de torture et de viol constituent aussi des formes de violation des droits humains qui attirent beaucoup d’attention chez des observateurs des droits humains de l’APRODH. Une analyse approfondie de ces cas fera objet de la troisième partie du rapport. La situation carcérale constitue aussi une partie non moins importante dans les rapports mensuels de l’APRODH. Ainsi, elle sera abordée à travers les visites des cachots et des lieux de détention que nous avons effectuées au cours du mois d’Octobre aussi bien au niveau du siège qu’à celui de nos antennes. -
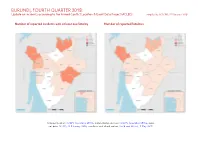
BURUNDI, FOURTH QUARTER 2018: Update on Incidents According to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Compiled by ACCORD, 25 February 2020
BURUNDI, FOURTH QUARTER 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 25 February 2020 Number of reported incidents with at least one fatality Number of reported fatalities National borders: GADM, November 2015b; administrative divisions: GADM, November 2015a; incid- ent data: ACLED, 22 February 2020; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 BURUNDI, FOURTH QUARTER 2018: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 25 FEBRUARY 2020 Contents Conflict incidents by category Number of Number of reported fatalities 1 Number of Number of Category incidents with at incidents fatalities Number of reported incidents with at least one fatality 1 least one fatality Violence against civilians 136 28 58 Conflict incidents by category 2 Protests 23 0 0 Development of conflict incidents from December 2016 to December 2018 2 Riots 17 10 10 Strategic developments 8 0 0 Methodology 3 Battles 7 3 7 Conflict incidents per province 4 Explosions / Remote 5 1 3 violence Localization of conflict incidents 4 Total 196 42 78 Disclaimer 6 This table is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 22 February 2020). Development of conflict incidents from December 2016 to December 2018 This graph is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 22 February 2020). 2 BURUNDI, FOURTH QUARTER 2018: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 25 FEBRUARY 2020 Methodology GADM. Incidents that could not be located are ignored. The numbers included in this overview might therefore differ from the original ACLED data. -

Dep Ar Tement De La Population Republique Du Burundi Ministere De L'interieur Departement De La Population
REPUBLIQUE DU BURUNDI MINISTERE DE L'I1'!TERIEUR DEP AR TEMENT DE LA POPULATION REPUBLIQUE DU BURUNDI MINISTERE DE L'INTERIEUR DEPARTEMENT DE LA POPULATION Centre Français sur 1 et le Dé ppement 15, rue ,'Ecole de Médecine 70 PARIS CEDEX 06 Tél. (1) 46 33 9941 RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1 6 A O'U T 1 979 TOME II Volume VIII RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROVINCE DE NGOZI Bujumbura, Octobre 1983 " -3- RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1 6 A 0 U T 1 979 SOMMAIRE PAGES Ayant-propos 4 1. Introduction 5 2. principaux Résultats 6 2.1- Effectifs et Densités 6 2.2- Lieu de Naissance et Lieu de Résidence 9 2.3- Sexe et Age 11 2.4- Alphabétisation et Scolarisation 15 2.5- population Active et Inactive 17 2.6- Professions et Branches d'Activité 18 2.7- Ménage et Rugo 21 3. Conclusion 23 4. Annexes 24 4.1- Liste des tableaux 24 4.2- Résultats Bruts 28 -4- AVANT·-PROPOS Comme pour toutes les autres publications sur les Résultats définitifs du Recensement général de la Population effectué en 1979, le présent rapport se réfère aux anciennes limites de la Province de NGOZI avant la nouvelle déli mitation du territoire Burundais. Après une brève introduction, le lecteur y trouvera les principaux résultats sur les effectifs et densité, le lieu de naissance et le lieu de ré sidence, le sexe et l'âge, l'alphabétisation et la scolarisation, la population active et inactive, les professions et les branches d'activités, les ménages et rugo et enfin des annexes contenant la liste des tableaux bruts. -

BURUNDI: Carte De Référence
BURUNDI: Carte de référence 29°0'0"E 29°30'0"E 30°0'0"E 30°30'0"E 2°0'0"S 2°0'0"S L a c K i v u RWANDA Lac Rweru Ngomo Kijumbura Lac Cohoha Masaka Cagakori Kiri Kiyonza Ruzo Nzove Murama Gaturanda Gatete Kayove Rubuga Kigina Tura Sigu Vumasi Rusenyi Kinanira Rwibikara Nyabisindu Gatare Gakoni Bugabira Kabira Nyakarama Nyamabuye Bugoma Kivo Kumana Buhangara Nyabikenke Marembo Murambi Ceru Nyagisozi Karambo Giteranyi Rugasa Higiro Rusara Mihigo Gitete Kinyami Munazi Ruheha Muyange Kagugo Bisiga Rumandari Gitwe Kibonde Gisenyi Buhoro Rukungere NByakuizu soni Muvyuko Gasenyi Kididiri Nonwe Giteryani 2°30'0"S 2°30'0"S Kigoma Runyonza Yaranda Burara Nyabugeni Bunywera Rugese Mugendo Karambo Kinyovu Nyabibugu Rugarama Kabanga Cewe Renga Karugunda Rurira Minyago Kabizi Kirundo Rutabo Buringa Ndava Kavomo Shoza Bugera Murore Mika Makombe Kanyagu Rurende Buringanire Murama Kinyangurube Mwenya Bwambarangwe Carubambo Murungurira Kagege Mugobe Shore Ruyenzi Susa Kanyinya Munyinya Ruyaga Budahunga Gasave Kabogo Rubenga Mariza Sasa Buhimba Kirundo Mugongo Centre-Urbain Mutara Mukerwa Gatemere Kimeza Nyemera Gihosha Mukenke Mangoma Bigombo Rambo Kirundo Gakana Rungazi Ntega Gitwenzi Kiravumba Butegana Rugese Monge Rugero Mataka Runyinya Gahosha Santunda Kigaga Gasave Mugano Rwimbogo Mihigo Ntega Gikuyo Buhevyi Buhorana Mukoni Nyempundu Gihome KanabugireGatwe Karamagi Nyakibingo KIRUCNanika DGaOsuga Butahana Bucana Mutarishwa Cumva Rabiro Ngoma Gisitwe Nkorwe Kabirizi Gihinga Miremera Kiziba Muyinza Bugorora Kinyuku Mwendo Rushubije Busenyi Butihinda -
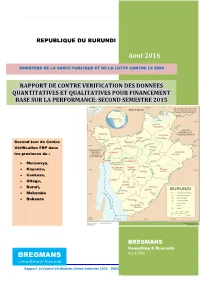
Second Semestre 2015
P a g e | 1 REPUBLIQUE DU BURUNDI Aout 2016 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA RAPPORT DE CONTRE VERIFICATION DES DONNEES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES POUR FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE: SECOND SEMESTRE 2015 Second tour de Contre Vérification FBP dans les provinces de : Muramvya, Kayanza, Cankuzo, Gitega, Bururi, Makamba Bubanza BREGMANS Consulting & Research BREGMANS Aout 2016 Consulting & Research Rapport de Contre Vérification: IIième Semestre 2015; BREGMANS Consulting & Research P a g e | 2 Carte du Burundi Rapport de Contre Vérification: IIième Semestre 2015; BREGMANS Consulting & Research P a g e | 3 Rapport de Contre Vérification: IIième Semestre 2015; BREGMANS Consulting & Research P a g e | 4 Note de remerciements : Ce travail de contre vérification a pu aboutir à ce point grâce aux efforts combinés des personnes compétentes qui ont su mettre à profit leurs connaissances en termes techniques, en termes d’organisation et en conseils pertinents pour le bon déroulement des activités. Nos remerciements sont adressés aux responsables du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida au Burundi et aux membres de la Cellule Technique Nationale pour le Financement Basé sur la performance (FBP) qui ont bien pris le temps d’exprimer leurs attentes concernant le choix des structures constituant l’échantillon de notre travail de terrain. Leurs avis techniques et leurs discussions constructives nous ont permis d’harmoniser nos vues sur la finalité du travail de contre vérification. Nos sincères remerciements vont aussi à l’endroit des acteurs de terrain dans les différentes provinces visitées. Ils nous ont facilité l’accès aux structures sanitaires et aux données malgré les temps difficiles que le pays traverse. -

MFA-MAGAZINE Nber 61 of 21St Febr 2020 Ministère Des Affaires Etrangères
REPUBLIQUE DU BURUNDI MFA-MAGAZINE Nber 61 of 21st Febr 2020 Ministère des Affaires Etrangères Bujumbura: The Head of State meets Representatives of reli- Sommaire page gious denominations in a moralization session Bujumbura: Head of State meets representa- tives of religious de- 1 nominations in a mor- alization session Bubanza: CNDD-FDD party members urged to 2 remain calm before, during and after 2020 elections The Minister of Foreign Affairs invited to na- 3 tional assembly in ple- nary session on oral issues he Head of State, His Excellency Pierre Nkurunziza, hosted the fourth ses- Coronavirus: China's T sion of moralization of the society on Friday, 21 February 2020 in Bujum- Ambassador to Burundi bura City Hall, towards certain Representatives of religious denominations tranquilizes parents with 5 students in China grouped within the African Ministry of compassion MAC. The Reverend Pastor Denise Nkurunziza took part in this session. At the end of the closed-door session, the Deputy Spokesperson of the Presi- dent of the Republic, Mr Alain Diomède Nzeyimana, said that these Religious Elections 2020: valida- tion of the insignia of Confessions set themselves the goal of working according to the theme ''unity in political parties and 6 the diversity'' coalitions ( source: www.rtnb.bi) CNL: Hon. Agathon Rwasa nominated for 7 2020 presidential candi- date st Page 2 MFA-MAGAZINE Nbr 61 OF 21 Febr 2020 Bubanza: CNDD-FDD party members urged to remain calm before, during and after 2020 elections the Sangwe cooperative on that hill. In Gihanga com- mune, the Bagumyabanga inaugurated the hillperma- nences of Gihungwe, Buringa, Village 2, Village 3, Vil- lage 5 and the Gihanga Centre. -

Congressional Budget Justification Fiscal Year 2017
U.S. AFRICAN DEVELOPMENT FOUNDATION “Creating Pathways to Prosperity” CONGRESSIONAL BUDGET JUSTIFICATION Fiscal Year 2017 The U.S. African Development Foundation (USADF) is an independent agency of the U.S. federal government, funding grassroots development projects to African-owned and led enterprises, cooperatives and community-based organizations. Our objective is to build African communities’ capacity, resilience, and economic activities at the community level so all Africans can contribute to Africa’s growth story. USADF is on the frontier of development, working directly with Africans on the ground to combat some of Africa’s most difficult development challenges with programs to increase U.S. development presence in the hardest to reach areas of extreme poverty. USADF grants (up to $250,000 each), enable our grantees to address the root causes of poverty, hunger, and lack of infrastructure (particularly energy poverty) in their communities to: Combat hunger through resilience, agricultural, and livestock programming Improve access to local and regional markets for small-holder farmers, cooperatives and entrepreneurs Empower women and girls to create and control their own economic livelihoods Create job opportunities and resources for youth through training Promote African solutions to the lack of basic infrastructure, particularly in rural areas and urban slums March 3, 2016 Washington, D.C. www.USADF.gov (This page was intentionally left blank) www.USADF.gov United States African Development Foundation THE BOARD OF DIRECTORS AND THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES AFRICAN DEVELOPMENT FOUNDATION WASHINGTON, DC We are pleased to present the Administration’s FY 2017 budget justification for the United States African Development Foundation (USADF). -

Summary June
g UPDATE OF THE HUMANITARIAN SITUATION IN BURUNDI1 WHO Burundi Summary of June 2003 1. General Context and Security 1.1. The rebellion cantonment process in Burundi following the cease fire agreement was officially launched by the Burundi Minister of Defence on the 6 June. Since then and after several attempts of cantonment, 22 combatants of FNL could be installed on the site of Muyange (Buramata commune in Bubanza province) located about fifty km from Bujumbura. 1.2. However at the time when a group of 300 other combatants were awaited on the site, a shelling attack on the site was done on the 30 June by the rebel group FDD-CNDD (faction which did not adhere yet to the cantonment process) with 4 died among the rebels. 1.3. This attack was condemned by the Government of Burundi which called all political actors not signatories of the cease fire agreement to continue negotiation because the cantonment should continue with the support of the African Union Mission in Burundi and the International Community ( already the World Bank freed 500,000 US$ for the construction of the first cantonment site by the Government). 1.4. A mission of the Security Council of the United Nations which was in the Great Lakes region visited Burundi and recommended to the International Community to make all necessary efforts to support the peace process initiatives mainly to help the African Union Mission in Burundi. 1.5. In addition the insecurity was marked this June by fighting between the rebels and the National Army in Kayanza, Bujumbura Rural, Muramvya and Gitega and also by the assassination of the local administration officers and the abduction of four Members of the Parliament (belonging to FRODEBU political party). -

Diversité, Endémisme, Géographie Et Conservation Des Fabaceae De L'afrique Centrale
FACULTE DES SCIENCES Ecole Interfacultaire de Bioingénieurs Service d’Ecologie du Paysage et Systèmes de Production Végétale Diversité, endémisme, géographie et conservation des Fabaceae de l'Afrique Centrale Thèse présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Docteur en Sciences Par Joël NDAYISHIMIYE Promoteur : Professeur Charles DE CANNIÈRE (Université Libre de Bruxelles) Co-promoteur : Professeur Jan BOGAERT (Université de Liège/Gembloux Agro Bio Tech) Co-promoteur : Professeur Marie Josée BIGENDAKO (Université du Burundi) Octobre, 2011 FACULTE DES SCIENCES Ecole Interfacultaire de Bioingénieurs Service d’Ecologie du Paysage et Systèmes de Production Végétale Diversité, endémisme, géographie et conservation des Fabaceae de l'Afrique Centrale Thèse présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Docteur en Sciences Par Joël NDAYISHIMIYE Composition du Jury : Professeur Marjolein VISSER (Président, Université Libre de Bruxelles) Professeur Farid DAHDOUH-GUEBAS (Secrétaire, Université Libre de Bruxelles) Professeur Charles DE CANNIERE (Promoteur, Université Libre de Bruxelles) Professeur Jan BOGAERT (Co-promoteur, Université de Liège/Gembloux Agro Bio Tech) Professeur Marie Josée BIGENDAKO (Co-promoteur, Université du Burundi) Dr Steven DESSEIN (Membre, Jardin Botanique National de Belgique) Octobre, 2011 Remerciements REMERCIEMENTS Cette thèse est le résultat des efforts et de l’encadrement de cinq années reçu au Service d’Ecologie du Paysage et Systèmes de Production Végétale (FK060) de l’Université Libre de Bruxelles. Pour cette raison, il est de notre devoir de formuler des remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à notre formation. Nous voudrions exprimer premièrement, nos sincères remerciements au Professeur Jan BOGAERT de Université de Liège (Gembloux Agro-Bio Tech), ancien Directeur du Service FK060, co-promoteur actuel de cette thèse et qui continue, malgré ses multiples occupations à assurer avec efficacité le suivi de nos travaux. -

Burundi Country Portfolio
Burundi Country Portfolio Overview: Country program established in 2008. USADF currently U.S. African Development Foundation Partner Organization: manages a portfolio of 11 projects and one Cooperative Agreement. Country Program Coordinator: Geoffrey Kayigi Association pour le Développement Total commitment is $1.8 million. PO Box 7210, CCOAIB Building, Remera 1, Transformationnel des Communautés (DTC) Quartier Kabondo, Avenue Gihungwe Country Strategy: The program focuses on grassroots Plot 2280, Umuganda Bld , Kigali, Rwanda Tel: +250-78-830-3934 Number 5177 B.P. 929, Bujumbura, Burundi organizations, cooperatives, capacity building, and small enterprise Email: [email protected] Tel.: + 257-22-27-79-58 development in a post-conflict environment. Email: [email protected] Grantee Duration Value Summary ASSOPRO Maramvya 2012-2016 $153,900 Sector: Agricultural Production (Rice) 2593-BUR Beneficiaries: 570 members Town/City: Mutimbuzi Commune Summary: The project funds will be used to build the group’s capacity to function independently by providing vital infrastructure including a storage facility and huller, as well as technical training and working capital. Intergroupment Ishaka de Buhiga 2013-2017 $200,400 Sector: Agricultural Production & Processing (Maize & Potatoes) (Ishaka) Beneficiaries: 13 member associations composed of 220 farmers 2857-BUR Town/City: Buhinga Commune Summary: The project funds will be used to begin producing maize and processing maize flour. The funds will also be used to expand potato production of which a portion will be kept as seed for members and the rest will be sold for food. Union des Associations Rizicoles 2013-2015 $87,800 Sector: Agricultural Production (Rice) de Beneficiaries: 14 associations with a 3,210 members Nyabitsinda (UARN) Town/City: Nyabitsinda Commune 2918-BUR Summary: The project funds will be used to construct a storage facility, purchase farming tools, hire and train staff and provide trainings on agricultural production, leadership and management.