KISHIDAIA, No.117, Aug
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Checklist of the Non -Acarine Arachnids
Original Research A CHECKLIST OF THE NON -A C A RINE A R A CHNIDS (CHELICER A T A : AR A CHNID A ) OF THE DE HOOP NA TURE RESERVE , WESTERN CA PE PROVINCE , SOUTH AFRIC A Authors: ABSTRACT Charles R. Haddad1 As part of the South African National Survey of Arachnida (SANSA) in conserved areas, arachnids Ansie S. Dippenaar- were collected in the De Hoop Nature Reserve in the Western Cape Province, South Africa. The Schoeman2 survey was carried out between 1999 and 2007, and consisted of five intensive surveys between Affiliations: two and 12 days in duration. Arachnids were sampled in five broad habitat types, namely fynbos, 1Department of Zoology & wetlands, i.e. De Hoop Vlei, Eucalyptus plantations at Potberg and Cupido’s Kraal, coastal dunes Entomology University of near Koppie Alleen and the intertidal zone at Koppie Alleen. A total of 274 species representing the Free State, five orders, 65 families and 191 determined genera were collected, of which spiders (Araneae) South Africa were the dominant taxon (252 spp., 174 genera, 53 families). The most species rich families collected were the Salticidae (32 spp.), Thomisidae (26 spp.), Gnaphosidae (21 spp.), Araneidae (18 2 Biosystematics: spp.), Theridiidae (16 spp.) and Corinnidae (15 spp.). Notes are provided on the most commonly Arachnology collected arachnids in each habitat. ARC - Plant Protection Research Institute Conservation implications: This study provides valuable baseline data on arachnids conserved South Africa in De Hoop Nature Reserve, which can be used for future assessments of habitat transformation, 2Department of Zoology & alien invasive species and climate change on arachnid biodiversity. -

A Novel Trade-Off for Batesian Mimics Running Title
Out of the frying pan and into the fire: A novel trade-off for Batesian mimics Running title: Salticids that mimic ants and get eaten by ant specialists Ximena J. Nelson*†, Daiqin Li§ and Robert R. Jackson† *Department of Psychology, Animal Behaviour Laboratory, Macquarie University, Sydney, NSW 2109, Australia Email: [email protected] Phone: 61-2-98509232 Fax: 61-2-98509231 §Department of Biological Sciences, National University of Singapore, Singapore †School of Biological Sciences, University of Canterbury, Private Bag 4800, Christchurch, New Zealand Key words: Ants, Batesian mimicry, myrmecophagy, predation, spiders, trade-off Abstract A mimicry system was investigated in which the models were ants (Formicidae) and both the mimics and the predators were jumping spiders (Salticidae). By using motionless lures in simultaneous-presentation prey-choice tests, how the predators respond specifically to the static appearance of ants and ant mimics was determined. These findings suggest a rarely considered adaptive trade-off for Batesian mimics of ants. Mimicry may be advantageous when it deceives ant-averse potential predators, but disadvantageous in encounters with ant- eating specialists. Nine myrmecophagic (ant-eating) species (from Africa, Asia, Australia and North America) and one araneophagic (spider-eating) species (Portia fimbriata from Queensland) were tested with ants (5 species), with myrmecomorphic (ant-like) salticids (6 species of Myrmarachne) and with non-ant-like prey (dipterans and ordinary salticids). The araneophagic salticid chose an ordinary salticid and chose flies significantly more often than ants. P. fimbriata also chose the ordinary salticid and chose flies significantly more often than myrmecomorphic salticids. However, there was no significant difference in how P. -

Supraspecific Names in Spider Systematic and Their Nomenclatural Problems
Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters 55: 42-45 Karlsruhe, April 2018 Supraspecific names in spider systematic and their nomenclatural problems Yuri M. Marusik doi: 10.30963/aramit5507 Abstract. Three different types of the names used in spider systematics are recognized and discussed: 1) typified taxonomic names, 2) non-typified taxonomic names, and 3) non-taxonomic names. Typified names are those from genus to superfamily group names; they are regulated by the ICZN. Non-typified names are used for taxonomic groups higher than superfamilies (e.g., Haplogynae, Mesothelae, etc.); they are not regulated by the ICZN but have an authorship, a fixed year of publication and are incorporated in a hierarchical classification. Non-taxonomic names are not regulated by any formal rules, unranked, have no authorship or description, and are non-typified. Some difficulties connected with the non-typified names in spider systematics are briefly discussed. Senior synonyms of some non-typified and non-taxonomic names are discussed, and suggestions are given on how to deal with the non-typified names lacking senior synonyms. Keywords: clade name, non-typified name, typified name. Zusammenfassung. Supraspezifische Namen in der Spinnensystematik und ihre nomenklatorischen Probleme. Drei verschie- dene Namenstypen in der Spinnensystematik werden diskutiert: 1) typisierte taxonomische Namen, 2) nicht-typisierte taxonomische Namen sowie 3) nicht-taxonomische Namen. Typisierte Namen reichen von Gattungen bis zu Überfamilien und sind durch die ICZN reguliert. Nicht-typisierte Namen werden für taxonomische Einheiten oberhalb von Überfamilien verwendet (z. B. Haplogynae, Meso- thelae), sind nicht durch die ICZN reguliert, haben aber Autoren, ein Erstbeschreibungsjahr und werden in hierarchischen Klassifikatio- nen verwendet. -

Landscape-Scale Connections Between the Land Use, Habitat Quality and Ecosystem Goods and Services in the Mureş/Maros Valley
TISCIA monograph series Landscape-scale connections between the land use, habitat quality and ecosystem goods and services in the Mureş/Maros valley Edited by László Körmöczi Szeged-Arad 2012 Two countries, one goal, joint success! Landscape-scale connections between the land use, habitat quality and ecosystem goods and services in the Mureş/Maros valley TISCIA monograph series 1. J. Hamar and A. Sárkány-Kiss (eds.): The Maros/Mureş River Valley. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River and its Environment, 1995. 2. A. Sárkány-Kiss and J. Hamar (eds.): The Criş/Körös Rivers’ Valleys. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River and its Environment, 1997. 3. A. Sárkány-Kiss and J. Hamar (eds.): The Someş/Szamos River Valleys. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River and its Environment, 1999. 4. J. Hamar and A. Sárkány-Kiss (eds.): The Upper Tisa Valley. Preparatory Proposal for Ramsar Site Designation and an Ecological Background, 1999. 5. L. Gallé and L. Körmöczi (eds.): Ecology of River Valleys, 2000. 6. Sárkány-Kiss and J. Hamar (eds.): Ecological Aspects of the Tisa River Basin, 2002. 7. L. Gallé (ed.): Vegetation and Fauna of Tisza River Basin, I. 2005. 8. L. Gallé (ed.): Vegetation and Fauna of Tisza River Basin, II. 2008. 9. L. Körmöczi (ed.): Ecological and socio-economic relations in the valleys of river Körös/Criş and river Maros/Mureş, 2011. 10. L. Körmöczi (ed.): Landscape-scale connections between the land use, habitat quality and ecosystem goods and services in the Mureş/Maros valley, 2012. -

Records of New Genus Chrysilla (Group Spider: Sub-Order: Araneae: Family: Salticidae) in India at Agroecosystem, at Sonitpur, Assam
Journal on New Biological Reports 3(1): 38 – 43 (2014) ISSN 2319 – 1104 (Online) Records of new Genus Chrysilla (Group Spider: Sub-order: Araneae: Family: Salticidae) in India at Agroecosystem, at Sonitpur, Assam 1 2 Mansur Ahmed 1, J. Anam 1, Malabika Kakati Saikia , S.V. Manthen and P. K. Saikia 1 1 Animal Ecology and Wildlife Biology Lab, Department of Zoolgy, Gopinath Bardoloi Nagar, Gauhati University, Guwahati-782014, Assam, India 2 J.D.P.S. Mahavidyalaya, Daryapur, Maharastra-444803 (Received on: 07 March, 2014; accepted on: 22 March, 2014) ABSTRACT The genus Chrysilla (Salticidae) was first described by Thorell (1887) and is insufficiently known. Presently eight species has been reported. Three of them were known only from their males, four from females and only one from both male and females. The type species ( Chrysilla lauta) , C. albens , C. delicata, C. doriai, C. deelemani and C. acerosa belongs to Asia. This is the first record of genus Chrysilla from India. The specimen was collected from sugarcane field of Sonitpur district of Assam, India. The type specimen was deposited in the Biodiversity Museum, Department of Zoology and Animal Ecology and Wildlife Biology lab, Gauhati University, India. The genus Chrysilla can be distinguished from Phintella and Leius by the thin , long and more colourfull bodies, stronger RTA and much longer than wide genital bulb of male palps, copulatory openings separated by one diameter or so and piriform spermathecae of epigyne. The new species is similar to that Chrysilla lauta , Chrysilla deelemani and Chrysilla acerosa but differs from the former two by the wider than long RTA with a ventral tip and the much longer embolus as in Chrysilla acerosa Wang and Zhang, 2012, differ from the later by the shape of prosoma, hight of clypeus, bulbus and median apophysis. -

196 Arachnology (2019)18 (3), 196–212 a Revised Checklist of the Spiders of Great Britain Methods and Ireland Selection Criteria and Lists
196 Arachnology (2019)18 (3), 196–212 A revised checklist of the spiders of Great Britain Methods and Ireland Selection criteria and lists Alastair Lavery The checklist has two main sections; List A contains all Burach, Carnbo, species proved or suspected to be established and List B Kinross, KY13 0NX species recorded only in specific circumstances. email: [email protected] The criterion for inclusion in list A is evidence that self- sustaining populations of the species are established within Great Britain and Ireland. This is taken to include records Abstract from the same site over a number of years or from a number A revised checklist of spider species found in Great Britain and of sites. Species not recorded after 1919, one hundred years Ireland is presented together with their national distributions, before the publication of this list, are not included, though national and international conservation statuses and syn- this has not been applied strictly for Irish species because of onymies. The list allows users to access the sources most often substantially lower recording levels. used in studying spiders on the archipelago. The list does not differentiate between species naturally Keywords: Araneae • Europe occurring and those that have established with human assis- tance; in practice this can be very difficult to determine. Introduction List A: species established in natural or semi-natural A checklist can have multiple purposes. Its primary pur- habitats pose is to provide an up-to-date list of the species found in the geographical area and, as in this case, to major divisions The main species list, List A1, includes all species found within that area. -

Catalogue of the Jumping Spiders of Northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae)
INSTITUTE FOR SYSTEMATICS AND ECOLOGY OF ANIMALS, SIBERIAN BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae) by D.V. Logunov & Yu.M. Marusik KMK Scientific Press Ltd. 2000 D. V. Logunov & Y. M. Marusik. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 2000. 299 pp. In English. Ä. Â. Ëîãóíîâ & Þ. Ì. Ìàðóñèê. Êàòàëîã ïàóêîâ-ñêàêóí÷èêîâ Ñåâåðíîé Àçèè (Arachnida, Araneae, Salticidae). Ìîñêâà: èçäàòåëüñòâî ÊÌÊ. 2000. 299 ñòð. Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå. This is the first complete catalogue of the jumping spiders of northern Asia. It is based on both original data and published data dating from 1861 to October 2000. Northern Asia is defined as the territories of Siberia, the Russian Far East, Mongolia, northern provinces of China, and both Korea and Japan (Hokkaido only). The catalogue lists 216 valid species belonging to 41 genera. The following data are supplied for each species: a range character- istic, all available records from northern Asia with approximate coordinates (mapped), all misidentifications and doubtful records (not mapped), habitat preferences, references to available biological data, taxonomic notes on species where necessary, references to lists of regional fauna and to catalogues of general importance. 24 species are excluded from the list of the Northern Asian salticids. 5 species names are newly synonymized: Evarcha pseudolaetabunda Peng & Xie, 1994 with E. mongolica Danilov & Logunov, 1994; He- liophanus mongolicus Schenkel, 1953 with H. baicalensis Kulczyñski, 1895; Neon rostra- tus Seo, 1995 with N. minutus ¯abka, 1985; Salticus potanini Schenkel, 1963 with S. -

SA Spider Checklist
REVIEW ZOOS' PRINT JOURNAL 22(2): 2551-2597 CHECKLIST OF SPIDERS (ARACHNIDA: ARANEAE) OF SOUTH ASIA INCLUDING THE 2006 UPDATE OF INDIAN SPIDER CHECKLIST Manju Siliwal 1 and Sanjay Molur 2,3 1,2 Wildlife Information & Liaison Development (WILD) Society, 3 Zoo Outreach Organisation (ZOO) 29-1, Bharathi Colony, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004, India Email: 1 [email protected]; 3 [email protected] ABSTRACT Thesaurus, (Vol. 1) in 1734 (Smith, 2001). Most of the spiders After one year since publication of the Indian Checklist, this is described during the British period from South Asia were by an attempt to provide a comprehensive checklist of spiders of foreigners based on the specimens deposited in different South Asia with eight countries - Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. The European Museums. Indian checklist is also updated for 2006. The South Asian While the Indian checklist (Siliwal et al., 2005) is more spider list is also compiled following The World Spider Catalog accurate, the South Asian spider checklist is not critically by Platnick and other peer-reviewed publications since the last scrutinized due to lack of complete literature, but it gives an update. In total, 2299 species of spiders in 67 families have overview of species found in various South Asian countries, been reported from South Asia. There are 39 species included in this regions checklist that are not listed in the World Catalog gives the endemism of species and forms a basis for careful of Spiders. Taxonomic verification is recommended for 51 species. and participatory work by arachnologists in the region. -

Arachnologische Arachnology
Arachnologische Gesellschaft E u Arachnology 2015 o 24.-28.8.2015 Brno, p Czech Republic e www.european-arachnology.org a n Arachnologische Mitteilungen Arachnology Letters Heft / Volume 51 Karlsruhe, April 2016 ISSN 1018-4171 (Druck), 2199-7233 (Online) www.AraGes.de/aramit Arachnologische Mitteilungen veröffentlichen Arbeiten zur Faunistik, Ökologie und Taxonomie von Spinnentieren (außer Acari). Publi- ziert werden Artikel in Deutsch oder Englisch nach Begutachtung, online und gedruckt. Mitgliedschaft in der Arachnologischen Gesellschaft beinhaltet den Bezug der Hefte. Autoren zahlen keine Druckgebühren. Inhalte werden unter der freien internationalen Lizenz Creative Commons 4.0 veröffentlicht. Arachnology Logo: P. Jäger, K. Rehbinder Letters Publiziert von / Published by is a peer-reviewed, open-access, online and print, rapidly produced journal focusing on faunistics, ecology Arachnologische and taxonomy of Arachnida (excl. Acari). German and English manuscripts are equally welcome. Members Gesellschaft e.V. of Arachnologische Gesellschaft receive the printed issues. There are no page charges. URL: http://www.AraGes.de Arachnology Letters is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Autorenhinweise / Author guidelines www.AraGes.de/aramit/ Schriftleitung / Editors Theo Blick, Senckenberg Research Institute, Senckenberganlage 25, D-60325 Frankfurt/M. and Callistus, Gemeinschaft für Zoologische & Ökologische Untersuchungen, D-95503 Hummeltal; E-Mail: [email protected], [email protected] Sascha -

PDF Hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/129008 Please be advised that this information was generated on 2018-02-19 and may be subject to change. Through arthropod eyes Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity Toos van Noordwijk Through arthropod eyes Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity Van Noordwijk, C.G.E. 2014. Through arthropod eyes. Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity. Ph.D. thesis, Radboud University Nijmegen, the Netherlands. Keywords: Biodiversity, chalk grassland, dispersal tactics, conservation management, ecosystem restoration, fragmentation, grazing, insect conservation, life‑history strategies, traits. ©2014, C.G.E. van Noordwijk ISBN: 978‑90‑77522‑06‑6 Printed by: Gildeprint ‑ Enschede Lay‑out: A.M. Antheunisse Cover photos: Aart Noordam (Bijenwolf, Philanthus triangulum) Toos van Noordwijk (Laamhei) The research presented in this thesis was financially spupported by and carried out at: 1) Bargerveen Foundation, Nijmegen, the Netherlands; 2) Department of Animal Ecology and Ecophysiology, Institute for Water and Wetland Research, Radboud University Nijmegen, the Netherlands; 3) Terrestrial Ecology Unit, Ghent University, Belgium. The research was in part commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation as part of the O+BN program (Development and Management of Nature Quality). Financial support from Radboud University for printing this thesis is gratefully acknowledged. Through arthropod eyes Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. -

Taxonomic Revision of the Longiscapus-Group of Arcuphantes
Acta arachnol., 44 (2) : 129-152, December 30, 1995 Taxonomic Revision of the longiscapus-group of Arcuphantes (Araneae: Linyphiidae) in Western Japan, with a Note on the Concurrent Diversification of Copulatory Organs between Males and Females Yoh IHARA 1 井 原 庸1):西 日本 の ナ ガ エヤ ミサ ラグモ種 群 の分類 学的 改訂 お よび雌雄 の交尾 器 官の協 同的 多様 化 Abstract The longiscapus group in the genus Arcuphantes (Linyphiidae) is revised based on genital morphology and geographic distributional pattern. This group should be treated as a closely related species group or a single superspecies by their morphology and distribution. Three known species, A, longiscapus, A. hibanus and A. iharai, and five new species, A. saitoi, A. setouchi, A. tsurusakii, A. nojimai and A. okiensis are described. These eight species are only distributed in western Honshu, northeastern Shikoku and some adjacent islands, Japan. It gives para- patric pattern to the distribution except for some cases of narrow overlap. Mor- phological correspondence between male palp and epigynum was found as a species- specific character. Twenty species of the genus Arcuphantes (Linyphiidae) have been described from various areas of Japan. However, their taxonomy is still far from complete, and there are many undescribed species even in the main islands of Japan. What makes the taxonomy more complicated is the remarkable geographic differentiation in their copulatory organs exhibited by the species of the genus. In this paper, I deal with eight species of the genus Arcuphantes (longiscapus, hibanus, iharai and five new species), which are closely related to each other, from western Honshu, Shikoku and some adjacent islands, Japan. -
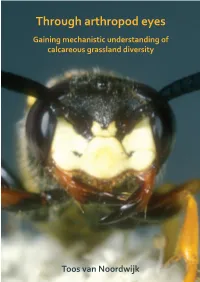
Through Arthropod Eyes Gaining Mechanistic Understanding of Calcareous Grassland Diversity
Through arthropod eyes Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity Toos van Noordwijk Through arthropod eyes Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity Van Noordwijk, C.G.E. 2014. Through arthropod eyes. Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity. Ph.D. thesis, Radboud University Nijmegen, the Netherlands. Keywords: Biodiversity, chalk grassland, dispersal tactics, conservation management, ecosystem restoration, fragmentation, grazing, insect conservation, life‑history strategies, traits. ©2014, C.G.E. van Noordwijk ISBN: 978‑90‑77522‑06‑6 Printed by: Gildeprint ‑ Enschede Lay‑out: A.M. Antheunisse Cover photos: Aart Noordam (Bijenwolf, Philanthus triangulum) Toos van Noordwijk (Laamhei) The research presented in this thesis was financially spupported by and carried out at: 1) Bargerveen Foundation, Nijmegen, the Netherlands; 2) Department of Animal Ecology and Ecophysiology, Institute for Water and Wetland Research, Radboud University Nijmegen, the Netherlands; 3) Terrestrial Ecology Unit, Ghent University, Belgium. The research was in part commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation as part of the O+BN program (Development and Management of Nature Quality). Financial support from Radboud University for printing this thesis is gratefully acknowledged. Through arthropod eyes Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann volgens besluit van het college van decanen en ter verkrijging van de graad van doctor in de biologie aan de Universiteit Gent op gezag van de rector prof. dr. Anne De Paepe, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 26 augustus 2014 om 10.30 uur precies door Catharina Gesina Elisabeth van Noordwijk geboren op 9 februari 1981 te Smithtown, USA Promotoren: Prof.