The Sessile Organisms Society of Japan
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ART/SMSG/SAERI Expedition Report: Hummock Island February 2021
ART/SMSG/SAERI Expedition Report: Hummock Island February 2021 Significance of peat dust and terrestrial erosion for marine communities around Hummock Island Amy Guest, Dr Paul Brewin, Dr Paul Brickle, Dr Karen von Juterzenka, and Dr Klemens Pütz Cosmasterias lurida (beaded starfish) and Munida gregaria (lobster krill) on a peat covered sandy substrate, Hummock Island February 2021 ART/SMSG/SAERI expedition report: Hummock Island, February 2021 Logistics Expedition dates: 4 - 14th Feb 2021 (for Daily Log see Appendix 1; Dive log see Appendix 2) Vessels: SMSG Fram (5.8 m RHIB), launched from Roy Cove; Sailing Yacht Porvenir II. Accommodation: Roy Cove self-catering, ART House Hummock Island Participants: Dr Paul Brickle (Co-PI) Dr Paul Brewin (Co-PI) Steve Cartwright (Dive Officer / Coxswain) Joost Pompert (Scientist / Surveyor) Sacha Cleminson (Scientist / Surveyor) 4th – 8th February, N.B. flew out from Fox Bay. Amy Guest (PhD Student / Surveyor / Logistics) Sally Poncet (Antarctic Research Trust) Ken Passfield (Antarctic Research Trust) Background Hummock Island lies to the west of West Falkland (Figure 1). Like on other islands in the Falklands, Hummock Island´s rocky surface is covered by peat soil. Decades of grazing on the island has led to de- vegetation of about one third of the 303 ha and subsequent substantial erosion. Large areas were replaced by black ground indicating the extension and distribution of exposed peat soil. The Antarctic Research Trust (ART) is currently re-vegetating the island by tussac planting campaigns. Tussac roots and above ground blade structures will stabilise the peat soil and, moreover, will prove very efficient in storage of atmospheric carbon. -

A New Early Miocene Barnacle Lineage and the Roots of Sea-Turtle Fouling Chelonibiidae (Cirripedia, Balanomorpha) Mathias Harzhausera∗, William A
Journal of Systematic Palaeontology, Vol. 9, Issue 4, December 2011, 473–480 A new Early Miocene barnacle lineage and the roots of sea-turtle fouling Chelonibiidae (Cirripedia, Balanomorpha) Mathias Harzhausera∗, William A. Newmanb and Patrick Grunertc aGeological-Paleontological Department, Natural History Museum Vienna, Burgring 7, A-1014 Vienna, Austria; bScripps Institution of Oceanography, UCSD, 9500 Gilman Drive, La Jolla CA 92093, USA; cInstitute for Earth Sciences, University of Graz, Heinrichstraße 26, A-8010 Graz, Austria (Received 6 May 2010; accepted 15 Jul 2010; printed 29 November 2011) The origin of the mainly sea-turtle fouling balanomorph family Chelonibiidae is still poorly documented. Aside from an Eocene erratic specimen assigned to an extinct subfamily, the extant subfamily Chelonibiinae did not appear in the fossil record before the Late Miocene. Protochelonibiinae Harzhauser & Newman subfam. nov. is here introduced as an extinct sister-group of Chelonibiinae. The subfamily is known so far only from the proto-Mediterranean and the Paratethys seas and ranged from Early Miocene to Late Pliocene. Members of the subfamily are characterized by large walls with tripartite rostra which display distinct sutures on the external surface. The tripartite rostrum, however, has evolved independently several times in the evolution of the balanomorphs and cannot be treated as synapomorphy. The subfamily comprises one new genus and two species. Protochelonibia Harzhauser & Newman gen. nov. is the type genus of Protochelonibiinae and Protochelonibia submersa Harzhauser & Newman sp. nov. is introduced as type species of this genus. Chelonobia Capellinii [sic] De Alessandri, 1895, from the Late Pliocene of Italy, reassigned as Protochelonibia capellinii (De Alessandri, 1895), is the youngest record of the subfamily. -
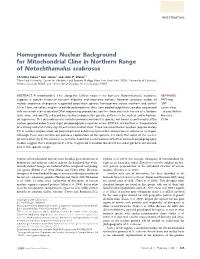
Homogeneous Nuclear Background for Mitochondrial Cline in Northern Range of Notochthamalus Scabrosus
INVESTIGATION Homogeneous Nuclear Background for Mitochondrial Cline in Northern Range of Notochthamalus scabrosus Christina Zakas,* Ken Jones,† and John P. Wares‡,1 *New York University, Center for Genomics and Systems Biology, New York, New York 10003, †University of Colorado, Aurora, Colorado 80045, and ‡University of Georgia, Athens, Georgia 30602 ABSTRACT A mitochondrial cline along the Chilean coast in the barnacle Notochthamalus scabrosus KEYWORDS suggests a species history of transient allopatry and secondary contact. However, previous studies of RAD-seq nuclear sequence divergence suggested population genetic homogeneity across northern and central SNP Chile. Here, we collect single-nucleotide polymorphism data from pooled population samples sequenced cytonuclear with restriction site2associated DNA sequencing procedures, confirm these data with the use of a Golden- disequilibrium Gate array, and identify a discordance between population genetic patterns in the nuclear and mitochon- barnacle drial genomes. This discordance was noted in previous work on this species, but here it is confirmed that the Chile nuclear genome exhibits only slight phylogeographic variation across 3000 km of coastline, in the presence of a strong and statistically significant mitochondrial cline. There are nevertheless markers (approximately 5% of nuclear single-nucleotide polymorphisms) exhibiting cytonuclear disequilibrium relative to mitotype. Although these data confirm our previous explorations of this species, it is likely that some of the nuclear genomic diversity of this species has yet to be explored, as comparison with other barnacle phylogeography studies suggest that a divergence of similar magnitude should be found in the nuclear genome somewhere else in the species range. Patterns of mitochondrial diversity have heralded great discoveries in Pavlova et al. -

Benthic Assemblages in South American Intertidal Rocky Shores: Biodiversity, Services, and Threats
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/299507578 Benthic Assemblages in South American Intertidal Rocky Shores: Biodiversity, Services, and Threats Chapter · January 2016 READS 318 29 authors, including: Gregorio Bigatti Alvar Carranza IBIOMAR- Instituto de Biología de Organismo… University of the Republic, Uruguay 82 PUBLICATIONS 563 CITATIONS 96 PUBLICATIONS 814 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Tito Lotufo Erasmo C Macaya University of São Paulo University of Concepción 37 PUBLICATIONS 216 CITATIONS 63 PUBLICATIONS 441 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE All in-text references underlined in blue are linked to publications on ResearchGate, Available from: Alvar Carranza letting you access and read them immediately. Retrieved on: 26 May 2016 Chapter BENTHIC ASSEMBLAGES IN SOUTH AMERICAN INTERTIDAL ROCKY SHORES: BIODIVERSITY, SERVICES, AND THREATS Patricia Miloslavich1,2, Juan José Cruz-Motta,1,3, Alejandra Hernández1,4, César Herrera1, Eduardo Klein1, Francisco Barros5, Gregorio Bigatti6, Maritza Cárdenas7, Alvar Carranza8, Augusto Flores9, Patricia Gil10, Judith Gobin11, Jorge Gutiérrez12, Marcos Krull5, Juan F. Lazarus13, Edgardo Londoño13, Tito Lotufo9, Erasmo Macaya14, Elba Mora15, Sergio Navarrete16, Gabriela Palomo17, Mirtala Parragué16, Franciane Pellizzari18, Rosana Rocha19, Leonardo Romero20, Roberto Retamales21, Roger Sepúlveda22, Michelle C. Silva18 and Sabrina Soria17 1Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela 2Australian Institute of Marine Science, -
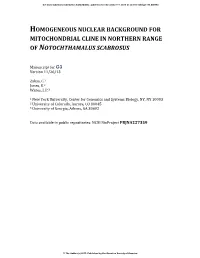
Homogeneous Nuclear Background for Mitochondrial Cline in Northern Range of Notochthamalus Scabrosus
G3: Genes|Genomes|Genetics Early Online, published on December 17, 2013 as doi:10.1534/g3.113.008383 HOMOGENEOUS NUCLEAR BACKGROUND FOR MITOCHONDRIAL CLINE IN NORTHERN RANGE OF NOTOCHTHAMALUS SCABROSUS Manuscript for G3 Version 11/26/13 Zakas, C.1 Jones, K.2 Wares, J. P.3 1 New York University, Center for Genomics and Systems Biology, NY, NY 10003 2 University of Colorado, Aurora, CO 80045 3 University of Georgia, Athens, GA 30602 Data available in public repositories: NCBI BioProject PRJNA227359 © The Author(s) 2013. Published by the Genetics Society of America. Running Title: Low SNP variation in Notochthamalus Keywords: RAD-seq, SNP, cytonuclear disequilibrium, barnacle, Chile Corresponding author: J. P. Wares Department of Genetics University of Georgia Athens, Georgia, USA 30602 [email protected] 2 Abstract A mitochondrial cline along the Chilean coast in the barnacle Notochthamalus scabrosus suggests a species history of transient allopatry and secondary contact. However, previous studies of nuclear sequence divergence suggested population genetic homogeneity across northern and central Chile. Here we collect SNP data from pooled population samples sequenced with RAD-seq procedures, confirm these data using a GoldenGate array, and identify a discordance between population genetic patterns in the nuclear and mitochondrial genomes. This discordance was noted in previous work on this species, but here it is confirmed that the nuclear genome exhibits only slight phylogeographic variation across 3000km of coastline, in the presence of a strong and statistically significant mitochondrial cline. There are nevertheless markers (approximately 5% of nuclear SNPs) exhibiting cytonuclear disequilibrium relative to mitotype. Although these data confirm our previous explorations of this species, it is likely that some of the nuclear genomic diversity of this species has yet to be explored, as comparison with other barnacle phylogeography studies suggest that a divergence of similar magnitude should be found in the nuclear genome somewhere else in the species range. -

John P. Wares Publications
John P. Wares wareslab.genetics.uga.edu University of Georgia – Department of Genetics & Odum School of Ecology Education B.S. in Zoology with Honors University of Oklahoma, 1995 Ph.D. in Zoology and Genetics Duke University, 2000 Postdoctoral Training University of New Mexico PI: Tom Turner, 2000-2002 University of California, Davis PI: Rick Grosberg, 2002-2004 Academic Positions Assistant Professor University of Georgia, 2005-2011 Associate Professor University of Georgia, 2011-present Visiting Lecturer UW - Friday Harbor Labs, summer 2016 Publications (n=90; 76 while at UGA) n.b. I tend to promote students and junior colleagues via 1st authorship, with senior authorship as last. I also have a philosophical goal in publishing as much in Open Access and low-cost journals as possible. ξ equal authorship *student 2019 (0) 2018 (2) Wares, J. P., S. Crickenberger, A. F. Govindarajan, J. L. Hamrick, K. M. Skoczen, D. W. Trapnell, and D. S. Wethey. 2018. The cryptic population biology of Chthamalus fragilis Darwin, 1854 on the Atlantic coast of North America. J. Crustacean Biol., DOI: doi.org/10.1093/jcbiol/ruy070. Ewers-Saucedo, C.* and J. P. Wares. 2018. Population connectivity and phylogeography of Crustaceans. In: G. Poore and M. Thiel, eds. Evolution and Biogeography. The Natural History of the Crustacea, vol. 8. in press. 2017 (5) Ewers-Saucedo, C*., B. K. K. Chan, J. D. Zardus, and J. P. Wares. 2017. Parallel patterns of host-specific morphology and genetic admixture in sister lineages of a commensal barnacle. Biol. Bull. 232:171-185. Chandler, V. K*. and J. P. Wares. -

Cladistic Analysis of the Cirripedia Thoracica
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Cladistic analysis of the Cirripedia Thoracica Schram, F.R.; Glenner, H.; Hoeg, J.T.; Hensen, P.G. Publication date 1995 Published in Zoölogical Journal of the Linnean Society Link to publication Citation for published version (APA): Schram, F. R., Glenner, H., Hoeg, J. T., & Hensen, P. G. (1995). Cladistic analysis of the Cirripedia Thoracica. Zoölogical Journal of the Linnean Society, 114, 365-404. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:28 Sep 2021 Zoological Journal of the Linnean Society (1995), 114: 365–404. With 12 figures Cladistic analysis of the Cirripedia Thoracica HENRIK GLENNER,1 MARK J. GRYGIER,2 JENS T. HOšEG,1* PETER G. JENSEN1 AND FREDERICK R. -

The Oceanic Concordance of Phylogeography and Biogeography: a Case Study in Notochthamalus Christine Ewers-Saucedo1, James M
The oceanic concordance of phylogeography and biogeography: a case study in Notochthamalus Christine Ewers-Saucedo1, James M. Pringle2, Hector H. Sepulveda 3, James E. Byers4, Sergio A. Navarrete5 & John P. Wares4,6 1College of Biological Sciences, University of California, Davis, California 95616 2Institute for the Study of Earth, Ocean, and Space, University of New Hampshire, Durham, New Hampshire 03824 3Departamento de Geofisica, Universidad de Concepcion, Concepcion, Chile 4Odum School of Ecology, University of Georgia, Athens, Georgia 30602 5Estacion Costera de Investigaciones Marinas Las Cruces and Center for Marine Conservation, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Casilla 114D, Santiago, Chile 6Department of Genetics, University of Georgia, Athens, Georgia 30602 Keywords Abstract Biogeography, Chile, connectivity, Pacific Ocean, population genetics. Dispersal and adaptation are the two primary mechanisms that set the range dis- tributions for a population or species. As such, understanding how these mecha- Correspondence nisms interact in marine organisms in particular – with capacity for long-range John P. Wares, Department of Genetics, dispersal and a poor understanding of what selective environments species are University of Georgia, Athens, GA 30602. responding to – can provide useful insights for the exploration of biogeographic Tel: 706-542-7720; patterns. Previously, the barnacle Notochthamalus scabrosus has revealed two Fax: 706-542-8000; evolutionarily distinct lineages with a joint distribution that suggests an associa- -

Eco-Taphonomy of Mass-Aggregated Giant Balanids Concavus
Acta Geologica Polonica , Vol. 58 (2008), No. 1, pp. 87-103 Eco-taphonomy of mass-aggregated giant balanids Concavus (Concavus ) concavus (DARWIN , 1854) from the Lower Pliocene (Zanclean) of Rafina near Pikermi (Attica, Greece) URSZULA RADWAŃSKA & ANDRZEJ RADWAŃSKI Institute of Geology, University of Warsaw, Żwirki i Wigury , 93, PL-02-089 Warszawa, Poland. E-mail: [email protected] ABSTRACT: RADWAŃSKA , U. & R ADWAŃSKI , A. 2008. Eco-taphonomy of mass-aggregated giant balanids Concavus (Con - cavus ) concavus (DARWIN , 1854) from the Lower Pliocene (Zanclean) of Rafina near Pikermi (Attica, Greece). Acta Geologica Polonica , 58 (1) , 87-103 . Warszawa. The large- to giant-sized balanids, mass-aggregated in a tempestite of the Lower Pliocene (Zanclean) section at Ra - fina near Pikermi, Greece, represent a single species, Concavus (Concavus ) concavus (DARWIN , 1854) [ non BRONN , 1831], the taxonomy of which is revised. The peculiarly shaped forms ‘ raphanoides ’ and ‘ scutorum ’ are ecopheno - types of this species; the same applies to the ‘ tulipiformis ’ specimens reported previously from this section. Discussed are dynamic events controlling the life and death conditions in the nearshore (offshore) environment of Rafina, where the giant specimens of Concavus (Concavus ) concavus (DARWIN , 1854) flourished through several succes - sive generations. As opportunistic species they adopted the r-selection reproduction strategy in order to dominate over other biota. The intermittent action of high-energy agents was responsible for the production of balanid-shell hash that involved taphonomic feedback. This enabled further colonization of the biotope and the growth of multiphased (bouquet-like and pyramidal) clusters. The demise of the monospecific balanid communities is ascribed to a heavy storm which stirred-up the whole balanid-bearing sequence, to produce a proximal tempestite. -
![Jehlius Cirratus[I]](https://docslib.b-cdn.net/cover/2342/jehlius-cirratus-i-3462342.webp)
Jehlius Cirratus[I]
A peer-reviewed version of this preprint was published in PeerJ on 7 February 2017. View the peer-reviewed version (peerj.com/articles/2971), which is the preferred citable publication unless you specifically need to cite this preprint. Guo B, Wares JP. 2017. Large-scale gene flow in the barnacle Jehlius cirratus and contrasts with other broadly-distributed taxa along the Chilean coast. PeerJ 5:e2971 https://doi.org/10.7717/peerj.2971 1 RH: Phylogeography Jehlius in cirratus 2 Large-‐scale gene flow in the barnacle Jehlius cirratus and contrasts 3 with other broadly-‐distributed taxa along the Chilean coast 4 5 Guo B.1,2 6 Wares J. P.* 2 7 8 1 National Engineering Research Center of Maricultural Facilities of China, College of 9 Marine Science and Technology, Zhejiang Ocean University, Zhoushan 316004, PR 10 China 11 2 Department oF Genetics, University oF Georgia, Athens, Georgia, USA 12 13 *corresponding author: John P. Wares, University [email protected] of Georgia, 14 15 Key Words: phylogeography, gene FloW, barnacle, chthamalid, Chile, biogeography 16 1 PeerJ Preprints | https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.596v4 | CC BY 4.0 Open Access | rec: 12 Sep 2016, publ: 12 Sep 2016 17 Abstract 18 We evaluate the population genetic structure of the intertidal Jehlius barnacle 19 cirratus across a broad portion oF its geographic on distributi using data From the 20 mitochondrial cytochrome oxidase I (COI) gene region. Despite sampling diversity 21 From over 3000km oF the linear range oF this species, there is only slight regional 22 structure indicated, With Φ overall CT of 0.036 (p<0.001) yet no support for isolation 23 by distance. -

Zoogeografía De Macroinvertebrados Bentónicos De La Costa De Chile: Contribución Para La Conservación Marina
Revista Chilena de Historia Natural 73: 99-129, 2000 Zoogeografía de macroinvertebrados bentónicos de la costa de Chile: contribución para la conservación marina Zoogeography of benthic macroinvertebrates of the Chilean coast: contribution for marine conservation DOMINGO A. LANCELLOTII & JULIO A. VASQUEZ 1 Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Casilla 117, Coquimbo, Chile, e-mail: [email protected] RESUMEN La diversidad de macroinvertebrados marinos ha recibido una atención creciente, no obstante, con un escaso tratamiento en el contexto biogeográfico. Este estudio analiza los registros de 1.601 especies de macroinvertebrados bentónicos pertenecientes a: Demospongiae, Anthozoa, Polychaeta, Mollusca, Crustacea, Echinodermata y Ascideacea, agrupados en 10 zonas y tratados desde una perspectiva zoogeográfica. Mollusca (611 especies), Polychaeta (403) y Crustacea (370) corresponden a los grupos mejor representados a lo largo de la costa chilena, determinantes en el patrón global de la biodiversidad. Este aumenta suavemente de norte a sur, interrumpido por máximos que sugieren esfuerzos diferenciales de estudio más que un comportamiento natural de la biodiversidad. El grado de agrupamiento entre las zonas muestra las tres unidades biogeográficas definidas recientemente por Lancellotti & V ásquez. Este arreglo, que representa lo exhibido por los grupos más diversos, se ve alterado en los grupos menos representados donde las diferencias obedecen al patrón de afinidades mostradas por las zonas comprendidas dentro de la Región Templada Transicional. El quiebre zoogeográfico alrededor de los 41° S, sugerido largamente en la literatura, sólo ocurre en Echinodermata y Demospongiae, evidenciando en los otros taxa la existencia de un área de transición entre los 35° y 48° S, caracterizada por un reemplazo gradual de especies. -

Pleistocene, Mississippian, & Devonian Stratigraphy of The
64 ANNUAL TRI-STATE GEOLOGICAL FIELD CONFERENCE GUIDEBOOK Pleistocene, Mississippian, & Devonian Stratigraphy of the Burlington, Iowa, Area October 12-13, 2002 Iowa Geological Survey Guidebook Series 23 Cover photograph: Exposures of Pleistocene Peoria Loess and Illinoian Till overlie Mississippian Keokuk Fm limestones at the Cessford Construction Co. Nelson Quarry; Field Trip Stop 4. 64th Annual Tri-State Geological Field Conference Pleistocene, Mississippian, & Devonian Stratigraphy of the Burlington, Iowa, Area Hosted by the Iowa Geological Survey prepared and led by Brian J. Witzke Stephanie A. Tassier-Surine Iowa Dept. Natural Resources Iowa Dept. Natural Resources Geological Survey Geological Survey Iowa City, IA 52242-1319 Iowa City, IA 52242-1319 Raymond R. Anderson Bill J. Bunker Iowa Dept. Natural Resources Iowa Dept. Natural Resources Geological Survey Geological Survey Iowa City, IA 52242-1319 Iowa City, IA 52242-1319 Joe Alan Artz Office of the State Archaeologist 700 Clinton Street Building Iowa City IA 52242-1030 October 12-13, 2002 Iowa Geological Survey Guidebook 23 Additional Copies of this Guidebook May be Ordered from the Iowa Geological Survey 109 Trowbridge Hall Iowa City, IA 52242-1319 Phone: 319-335-1575 or order via e-mail at: http://www.igsb.uiowa.edu ii IowaDepartment of Natural Resources, Geologial Survey TABLE OF CONTENTS Pleistocene, Mississippian, & Devonian Stratigraphy of the Burlington, Iowa, Area Introduction to the Field Trip Raymond R. Anderson ............................................................................................................................