スタートアップセミナー Start-Up Seminar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

0 Universidade Do Sul De Santa Catarina Bruno
0 UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA BRUNO RODRIGUES GONZALEZ OS SIMPSONS NO BRASIL: IRONIZANDO ESTEREÓTIPOS Palhoça SC 2012 1 BRUNO RODRIGUES GONZALEZ OS SIMPSONS NO BRASIL: IRONIZANDO ESTEREÓTIPOS Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Ciências da Linguagem da Universidade do Sul de Santa Catarina, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciências da Linguagem. Orientador: Prof. Dr. Fernando Simão Vugman. Palhoça SC 2012 2 3 4 Dedico esta dissertação à minha família que sempre me mostrou o caminho da educação e do amor. 5 AGRADECIMENTOS Agradeço aos meus pais Ulisses Gonzalez e Nádima Rodrigues Gonzalez que nunca mediram esforços por acreditar em meus sonhos e em minha jornada. Não apenas pela concretização deste estudo, mas por tudo o que foram e ainda serão em minha vida. A meu orientador Fernando Simão Vugman, que me incentivou na realização deste trabalho. Agradeço por toda orientação, apoio, atenção e cobranças. Aos professores Dilma Rocha e Solange Gallo por também estarem presentes em reuniões que foram fundamentais para a realização deste trabalho. Ao professor Tunico Amancio, por aceitar meu convite de imediato para ser examinador em minha banca. A todos meus amigos que afetivamente me acolheram e me acompanharam nesta longa etapa. Enfim, minha gratidão para com os professores, familiares e amigos, vocês sempre serão meus eternos companheiros a quem eu sempre serei grato, pois de uma forma ou de outra estiveram do meu lado nestes momentos encantadores e difíceis. 6 Se a culpa é minha eu coloco em quem eu quiser. (Homer Simpson) 7 RESUMO O objetivo deste estudo é detectar estereótipos do Brasil e dos brasileiros no episódio “O feitiço de Lisa” (Blame it on Lisa) da série televisiva Os Simpsons , estereótipos estes já outrora detectados e catalogados pelo professor Dr. -

Emotional and Linguistic Analysis of Dialogue from Animated Comedies: Homer, Hank, Peter and Kenny Speak
Emotional and Linguistic Analysis of Dialogue from Animated Comedies: Homer, Hank, Peter and Kenny Speak. by Rose Ann Ko2inski Thesis presented as a partial requirement in the Master of Arts (M.A.) in Human Development School of Graduate Studies Laurentian University Sudbury, Ontario © Rose Ann Kozinski, 2009 Library and Archives Bibliotheque et 1*1 Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington OttawaONK1A0N4 OttawaONK1A0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-57666-3 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-57666-3 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par I'lnternet, prefer, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre imprimes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

Die Flexible Welt Der Simpsons
BACHELORARBEIT Herr Benjamin Lehmann Die flexible Welt der Simpsons 2012 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Die flexible Welt der Simpsons Autor: Herr Benjamin Lehmann Studiengang: Film und Fernsehen Seminargruppe: FF08w2-B Erstprüfer: Professor Peter Gottschalk Zweitprüfer: Christian Maintz (M.A.) Einreichung: Mittweida, 06.01.2012 Faculty of Media BACHELOR THESIS The flexible world of the Simpsons author: Mr. Benjamin Lehmann course of studies: Film und Fernsehen seminar group: FF08w2-B first examiner: Professor Peter Gottschalk second examiner: Christian Maintz (M.A.) submission: Mittweida, 6th January 2012 Bibliografische Angaben Lehmann, Benjamin: Die flexible Welt der Simpsons The flexible world of the Simpsons 103 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2012 Abstract Die Simpsons sorgen seit mehr als 20 Jahren für subversive Unterhaltung im Zeichentrickformat. Die Serie verbindet realistische Themen mit dem abnormen Witz von Cartoons. Diese Flexibilität ist ein bestimmendes Element in Springfield und erstreckt sich über verschiedene Bereiche der Serie. Die flexible Welt der Simpsons wird in dieser Arbeit unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf den Wiedersehenswert der Serie untersucht. 5 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ............................................................................................. 5 Abkürzungsverzeichnis .................................................................................... 7 1 Einleitung ................................................................................................... -
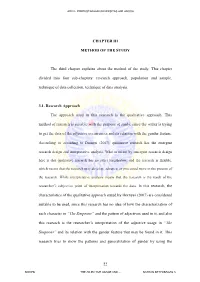
The Adjective Usage and Its Relation with Gender
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA CHAPTER III METHOD OF THE STUDY The third chapter explains about the method of the study. This chapter divided into four sub-chapters: research approach, population and sample, technique of data collection, technique of data analysis. 3.1. Research Approach The approach used in this research is the qualitative approach. This method of research is suitable with the purpose of study, since the writer is trying to get the data of the adjective occurrences and its relation with the gender feature. According to according to Dornyei (2007), qualitative research has the emergent research design and interpretative analysis. What is meant by emergent research design here is that qualitative research has no strict foreshadow, and the research is flexible, which means that the research may develop, advance, or processed more in the process of the research. While interpretative analysis means that the research is the result of the researcher‟s subjective point of interpretation towards the data. In this research, the characteristics of the qualitative approach stated by Dornyei (2007) are considered suitable to be used, since this research has no idea of how the characterization of each character in “The Simpsons” and the pattern of adjectives used in it, and also this research is the researcher‟s interpretation of the adjective usage in “The Simpsons” and its relation with the gender feature that may be found in it. This research tries to show the patterns and generalization of gender by using the 22 SKRIPSI THE ADJECTIVE USAGE AND ... NATHAN SETYOBAGAS A. ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 23 qualitative approach on lexical items, especially the adjective used in each gender role in The Simpsons. -
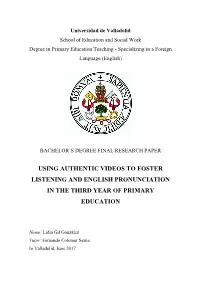
Using Authentic Videos to Foster Listening and English Pronunciation in the Third Year of Primary Education
Universidad de Valladolid Lidia Gil González Universidad de Valladolid School of Education and Social Work Degree in Primary Education Teaching - Specializing in a Foreign Language (English) BACHELOR’S DEGREE FINAL RESEARCH PAPER USING AUTHENTIC VIDEOS TO FOSTER LISTENING AND ENGLISH PRONUNCIATION IN THE THIRD YEAR OF PRIMARY EDUCATION Name: Lidia Gil González Tutor: Fernando Colomer Serna In Valladolid, June 2017 1 Universidad de Valladolid Lidia Gil González ABSTRACT Spanish legislation on education emphasizes the role of listening and pronunciation in the English classroom. That is why the present article aims to research whether students can improve both skills thanks to authentic videos. Therefore, an action plan was implemented with two classrooms in 3rd Primary: experimental and control group. Data was collected by means of a pre and post listening test, pre and post pronunciation exercises and a teacher diary. The treatment consisted of a series of six short videos necessary to solve the increasingly demanding post-viewing activities. Having suffered a setback, results reveal that the experimental group does not progress as much as the control one in terms of listening, but videos do have a positive effect on vowel articulation and pace. Keywords: listening, pronunciation, authentic videos, Primary Education. RESUMEN La legislación española en materia educativa prioriza el papel de la comprensión oral y la pronunciación en las clases de inglés. Por ello, el presente artículo pretende investigar si los alumnos pueden mejorar ambas habilidades gracias al uso de vídeos. Para ello, se ha puesto en marcha un plan de acción con dos clases de 3º de Primaria: grupo experimental y control. -

Day Day One August 21
Thursday Day One August 21 2p 8:30p 9:9:9: "Life on the Fast Lane" :2222: :22"Itchy and Scratchy and Marge" 2:30p 9p :0110: :01"Homer's Night Out" :3223: :32"Bart Gets Hit by a Car" 3p 9:30p :1111: :11"The Crêpes of Wrath" :4224: :42"One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish" 3:30p :2112: :21"Krusty Gets Busted" 10p :5225: :52"The Way We Was" 4p :3113: :31"Some Enchanted Evening" 10:30p :6226: :62"Homer vs. Lisa and the 8th Commandment" Season 2: 1990 -1991 Season 1: 1989 -1990 11p 4:30p 10a :4114: :41"Bart Gets an 'F'" :7227: :72"Principal Charming" 1:1:1: "Simpsons Roasting on an Open Fire" 11:30p 5p 10:30a :5115: :51"Simpson and Delilah" :8228: :82"Oh Brother, Where Art Thou?" 2:2:2: "Bart the Genius" 5:30p 11a :6116: :61"Treehouse of Horror" 3:3:3: "Homer's Odyssey" 6p 11:30a :7117: :71"Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish" 4:4:4: "There's No Disgrace Like Home" 12p 6:30p 5:5:5: "Bart the General" :8118: :81"Dancin' Homer" 12:30p 7p 6:6:6: "Moaning Lisa" :9119: :91"Dead Putting Society" 1p 7:30p 7:7:7: "The Call of the Simpsons" :0220: :02"Bart vs. Thanksgiving" 1:30p 8p 8:8:8: "The Telltale Head" :1221: :12"Bart the Daredevil" Friday Day Two August 22 6a 1p 5p Season 2: 1990 -1991 (cont'd) 414141:41 ::: "Like Father, Like Clown" 555555:55 ::: "Colonel Homer" 636363:63 ::: "Lisa the Beauty Queen" 12a 292929:29 ::: "Bart's Dog Gets an "F"" 6:30a 1:30p 5:30p 424242:42 ::: "Treehouse of Horror II" 565656:56 ::: "Black Widower" 646464:64 ::: "Treehouse of Horror III" 12:30a 303030:30 ::: "Old Money" 7a 2p 6p 434343:43 ::: -

DECLARATION of Jane Sunderland in Support of Request For
Columbia Pictures Industries Inc v. Bunnell Doc. 373 Att. 1 Exhibit 1 Twentieth Century Fox Film Corporation Motion Pictures 28 DAYS LATER 28 WEEKS LATER ALIEN 3 Alien vs. Predator ANASTASIA Anna And The King (1999) AQUAMARINE Banger Sisters, The Battle For The Planet Of The Apes Beach, The Beauty and the Geek BECAUSE OF WINN-DIXIE BEDAZZLED BEE SEASON BEHIND ENEMY LINES Bend It Like Beckham Beneath The Planet Of The Apes BIG MOMMA'S HOUSE BIG MOMMA'S HOUSE 2 BLACK KNIGHT Black Knight, The Brokedown Palace BROKEN ARROW Broken Arrow (1996) BROKEN LIZARD'S CLUB DREAD BROWN SUGAR BULWORTH CAST AWAY CATCH THAT KID CHAIN REACTION CHASING PAPI CHEAPER BY THE DOZEN CHEAPER BY THE DOZEN 2 Clearing, The CLEOPATRA COMEBACKS, THE Commando Conquest Of The Planet Of The Apes COURAGE UNDER FIRE DAREDEVIL DATE MOVIE 4 Dockets.Justia.com DAY AFTER TOMORROW, THE DECK THE HALLS Deep End, The DEVIL WEARS PRADA, THE DIE HARD DIE HARD 2 DIE HARD WITH A VENGEANCE DODGEBALL: A TRUE UNDERDOG STORY DOWN PERISCOPE DOWN WITH LOVE DRIVE ME CRAZY DRUMLINE DUDE, WHERE'S MY CAR? Edge, The EDWARD SCISSORHANDS ELEKTRA Entrapment EPIC MOVIE ERAGON Escape From The Planet Of The Apes Everyone's Hero Family Stone, The FANTASTIC FOUR FAST FOOD NATION FAT ALBERT FEVER PITCH Fight Club, The FIREHOUSE DOG First $20 Million, The FIRST DAUGHTER FLICKA Flight 93 Flight of the Phoenix, The Fly, The FROM HELL Full Monty, The Garage Days GARDEN STATE GARFIELD GARFIELD A TAIL OF TWO KITTIES GRANDMA'S BOY Great Expectations (1998) HERE ON EARTH HIDE AND SEEK HIGH CRIMES 5 HILLS HAVE -

Os Simpsons: Representações Sociais Do Brasil Na Série Norte-Americana
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO ICSA – INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DECSO – DEP. DE CIÊNCIAS SOCIAIS, JORNALISMO E SERVIÇO SOCIAL CURSO DE JORNALISMO Ana Rafaela da Silva Os Simpsons: Representações sociais do Brasil na série norte-americana Mariana 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO ICSA – INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DECSO – DEP. DE CIÊNCIAS SOCIAIS, JORNALISMO E SERVIÇO SOCIAL CURSO DE JORNALISMO Ana Rafaela da Silva Os Simpsons: Representações sociais do Brasil na série norte-americana Monografia apresentada ao curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Jornalismo. Orientador: Prof. Dr. Claudio Rodrigues Coração Mariana 2017 RESUMO O presente trabalho articula os conceitos de representação, identidade, estigmas e estereótipos com a comédia de situação Os Simpsons. Busca compreender como questões sociais brasileiras são tematizadas em dois episódios da série, que têm o Brasil como destino: Blame It On Lisa e You don't have too live like a referee. O objetivo, portanto, é explorar o discurso sobre o Brasil, criado pelo desenho, relativo a essas quatro categorias de análise. Fazendo isso, estabelece a possibilidade de reflexão sobre o imaginário social brasileiro articulado pelo desenho. Palavras chave: Simpsons, comédia de situação, representações, estigmas, estereótipos ABSTRACT The present work articulates the concepts of representation, identity, stigma and stereotypes with the SitCom The Simpsons. It seeks to understand how Brazilian social issues are thematized in two episodes of the series, which have Brazil as a destination: Blame It On Lisa and You do not have too live like a referee. The goal, therefore, is to explore the discourse on Brazil, created by drawing, relative to these four categories of analysis. -

Universidade Federal De Mato Grosso Instituto De Linguagens Programa De Pós-Graduação Em Estudos De Cultura Contemporânea
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO INSTITUTO DE LINGUAGENS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE CULTURA CONTEMPORÂNEA SIMONE OLIVEIRA VIEIRA PERES OS SIMPSONS E O BRASIL: IMAGENS DE UM OLHAR ESTRANGEIRO EM “BLAME IT ON LISA” CUIABÁ - MT 2013 SIMONE OLIVEIRA VIEIRA PERES OS SIMPSONS E O BRASIL: IMAGENS DE UM OLHAR ESTRANGEIRO EM “BLAME IT ON LISA” Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso como requisito para a obtenção do título de Mestre em Estudos de Cultura Contemporânea na Área de Concentração Estudos Interdisciplinares de Cultura, Linha de Pesquisa Poéticas Contemporâneas. Orientador: Prof. Dr. Mário Cézar Silva Leite Cuiabá-MT Ano Para Renato, Guilherme e Glória. AGRADECIMENTOS A Deus. Ao professor Mário Cézar. Ao ECCO (professores, colegas e funcionários) por sempre encontrar ajuda quando precisei. À minha mãe, ao meu pai e aos meus irmãos por verem em mim além do que eu posso ver. Ao meu esposo pela admiração, paciência, compreensão e ânimo em tempo integral. Ao meu filho que é minha maior motivação. A todos que me ajudaram de alguma forma na concepção deste trabalho. Eu só boto bebop no meu samba Quando o Tio Sam tocar um tamborim Quando ele pegar No pandeiro e no zabumba. Quando ele aprender Que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana, E o meu samba vai ficar assim (...) (Jackson do Pandeiro / música “Chiclete com banana”) OS SIMPSONS E O BRASIL: IMAGENS DE UM OLHAR ESTRANGEIRO EM “BLAME IT ON LISA” RESUMO: Tendo como objeto de análise o episódio “Blame it on Lisa” do seriado norte-americano “Os Simpsons”, o presente estudo discute o processo de construção de imagens sobre o Brasil, a partir do olhar estrangeiro e das relações de identidade e alteridade, identificações e estranhamentos. -

The Simpsons “Do Diversity” in the Critical Media Literacy Classroom
“Peace and Chicken” The Simpsons “do diversity” in the critical media literacy classroom Emma Jane McGillivray Department of Integrated Studies in Education McGill University, Montreal January 2011 A thesis submitted to McGill University in partial fulfilment of the requirements of the degree of Masters of Arts © Emma Jane McGillivray 2011 Acknowledgments It is with the utmost gratitude that I extend a sincere thank-you to everyone that has in one way or another influenced and supported my learning over the last three years of my graduate studies. More specifically, there are pivotal players that have been invaluable throughout this writing process. To my Supervisor—Shirley Steinberg, thank you for answering so many of my questions and for helping me to understand that while The Simpsons might not be hyperreal, you can probably still find a time where they ‘did’ hyperreal. And for sharing your amazing brilliance and strength in everything that you do. Thank-You. To my partner in life—Scott McMichael- ‘I choo choo choose you’ -10 seasons in and a whole lot more to go. You have pushed and encouraged me everyday to do my best. I wouldn’t be here if it wasn’t for you. I love you. To my family— To my grandfather, Dr. Jim, you have made all of this obtainable and have been my hero throughout my life. It is your encouragement and advice that continues to push me to work hard at everything that I do. To my mother, Johanne McGillivray, you have taught me to have faith in the world and not to be afraid to wonder about the unimaginable. -
Tradução Cultural Em “Feitiço De Lisa” De Os Simpsons Em Aula De Inglês Como Língua Estrangeira
Tradução cultural em “Feitiço de Lisa” de Os Simpsons em aula de inglês como língua estrangeira Adelmário Vital Matos 1 Sílvia Maria G. Anastácio 2 Universidade Federal da Bahia (UFBA) Resumo Este trabalho propõe um estudo do episódio de Os Simpsons, Blame it on Lisa, traduzido como “Feitiço de Lisa”, que pertence a 13ª temporada e foi levado ao ar pela primeira vez no Brasil em 2002. Representações redutoras e estereotipadas do Brasil serão descritas e analisadas numa visão sistêmica, em que se pretende considerar a macro e a microestrutura da obra. Os questionamentos culturais que emergem no pólo receptor serão discutidos sob uma perspectiva cognitiva, acreditando-se que esse olhar comparativista entre culturas diversas em sala de aula ajuda a formar um aluno mais crítico e capaz de refletir sobre traços relevantes da cultura-alvo e da própria cultura em que se acha inserido. Palavras-chave : Os Simpsons , cultura, pólo receptor. Abstract This article proposes an analysis of The Simpsons’ episode Blame it on Lisa (Feitiço de Lisa) which was aired in Brazil for the first time in 2002. Stereotyped representations of Brazil are described and analyzed systematically, aiming at taking into consideration the macro and microstructures of the episode. The cultural questions which emerge in the reception pole are discussed under a cognitive perspective, assuming that such a comparative look of different cultures in a classroom helps in educating a more critical student who will be able to reflect on relevant aspects of both the target culture and the native culture in which he/she is inserted. Key words: The Simpsons, culture, reception pole. -

Melbourne Program Guide
MELBOURNE PROGRAM GUIDE Sunday 21st August 2011 06:00 am Jag (Rpt) PG Mixed Messages Some Violence Former f ighter pilot, Captain Harmon "Harm" Rabb, and his team of lawy ers are charged with the duty of inv estigating and litigating crimes committed by Nav y and Marine personnel. Starring: Dav id James Elliott, Catherine Bell, Tracey Needham, Zoe McLellan 07:00 am Macgyver (Rpt) PG Unfinished Business Mild Violence Armed with only a roll of duct tape and a Swiss Army knif e, super resourcef ul secret agent, Angus MacGy v er, can get himself out of any sticky situation by using his brains ov er brawn. Starring: Richard Dean Anderson, Dana Elcar 08:00 am The Brady Bunch (Rpt) G Try, Try Again Here's the story of a lov ely lady … y ou know how it goes! Carol married Mike, both hav e three children each, together with housekeeper, Alice, and dog, Tiger, they became the Brady Bunch. Starring: Robert Reed, Florence Henderson, Barry Williams, Maureen McCormick, Christopher Knight, Ev e Plumb, Mike Lookinland, Susan Olsen, Ann B Dav is 08:30 am Everybody Loves Raymond (Rpt) CC G Somebody Hates Raymond WS Ray 's f riend, Andy , gets a job booking guests f or a sports radio show, but can't book Ray because the presenter openly admits to hating him. This insults not only Ray but the entire Romano clan. Starring: Ray Romano, Patricia Heaton, Doris Roberts, Peter Boy le, Brad Garrett 09:00 am Touched By An Angel (Rpt) PG An Angel On The Roof Adult Themes Be inspired as Monica, Tess and Andrew bring messages of hope and lov e f rom God to the people who need His guidance the most.