本田財団 年次活動報告書 the Honda Foundation 2017-18 Annual Activity Report 2017-18
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Honda Insight Wikipedia in Its Third Generation, It Became a Four-Door Sedan €”Present
Honda insight wikipedia In its third generation, it became a four-door sedan —present. It was Honda's first model with Integrated Motor Assist system and the most fuel efficient gasoline-powered car available in the U. The Insight was launched April in the UK as the lowest priced hybrid on the market and became the best selling hybrid for the month. The Insight ranked as the top-selling vehicle in Japan for the month of April , a first for a hybrid model. In the following month, December , Insight became the first hybrid available in North America, followed seven months later by the Toyota Prius. The Insight featured optimized aerodynamics and a lightweight aluminum structure to maximize fuel efficiency and minimize emissions. As of , the first generation Insight still ranks as the most fuel-efficient United States Environmental Protection Agency EPA certified gasoline-fueled vehicle, with a highway rating of 61 miles per US gallon 3. The first-generation Insight was manufactured as a two-seater, launching in a single trim level with a manual transmission and optional air conditioning. In the second year of production two trim levels were available: manual transmission with air conditioning , and continuously variable transmission CVT with air conditioning. The only major change during its life span was the introduction of a trunk-mounted, front-controlled, multiple-disc CD changer. In addition to its hybrid drive system, the Insight was small, light and streamlined — with a drag-coefficient of 0. At the time of production, it was the most aerodynamic production car to be built. -

235904547.Pdf
Honda Motor Co., Ltd. (本田技研工業株式会社 Honda Giken Kōgyō KK?, IPA: [hoɴda] ( listen); /ˈhɒndə/) is a Japanese publicmultinational corporation primarily known as a manufacturer of automobiles, motorcycles and power equipment. Honda has been the world's largest motorcycle manufacturer since 1959,[3][4] as well as the world's largest manufacturer of internal combustion engines measured by volume, producing more than 14 million internal combustion engines each year.[5] Honda became the second-largest Japanese automobile manufacturer in 2001.[6][7] Honda was the eighth largest automobile manufacturer in the world behind General Motors, Volkswagen Group, Toyota, Hyundai Motor Group, Ford, Nissan, and PSA in 2011.[8] Honda was the first Japanese automobile manufacturer to release a dedicated luxury brand, Acura, in 1986. Aside from their core automobile and motorcycle businesses, Honda also manufactures garden equipment, marine engines, personal watercraft and power generators, amongst others. Since 1986, Honda has been involved with artificial intelligence/robotics research and released theirASIMO robot in 2000. They have also ventured into aerospace with the establishment of GE Honda Aero Engines in 2004 and theHonda HA-420 HondaJet, which began production in 2012. Honda has three joint-ventures in China (Honda China, Dongfeng Honda, and Guangqi Honda). In 2013, Honda invested about 5.7% (US$ 6.8 billion) of its revenues in research and development.[9] Also in 2013, Honda became the first Japanese automaker to be a net exporter from the United -

Malaysia-Volume-7-Honda.Pdf
as the entry model hybrid, the Insight, managed well as refined driving com- to receive a record of 2,336 units of registration fort. In April 2010, the Freed in the span of five months. Besides the four gave the Malaysian market main models that are assembled locally, Honda added excitement when it Malaysia also markets the Honda Jazz (CBU went in as a premium com- from Thailand), Civic Type R, Stream RSZ pact MPV. It is considered a (both CBU from Japan) and Freed (CBU from smart choice in that it comes Indonesia) models to cater to the diverse needs fully loaded with practicalities, of their wide spectrum of clientele. performance & style and it predominantly appeals to RECENT DEVELOPMENTS professional urbanites with In the beginning of 2009, Honda Malaysia family. The Insight, Honda’s spent close to four months upgrading its hybrid model made a debut manufacturing facilities and installing advanced in December 2010. The sty- machinery at its Pegoh Plant. In 2010, the lish & ergonomically designed facilities were upgraded and the production Green machine received an BRAND VALUES capacity of the plant was increased from 35,000 overwhelming order of 500 units within the first Honda’s slogan, ‘The Power of Dreams’, MARKET to over 40,000 cars per annum. 10 days of launching. expresses Honda’s ambition to realise and inspire The automobile industry has undergone Honda Malaysia’s Pegoh Plant started To provide optimal standard of sales and extraordinary dreams through its innovations. numerous and rapid changes in the last two production of Constant Velocity Joints (CVJ), after-sales service, Honda Malaysia offers the True to its Japanese roots, Honda is commit- decades. -
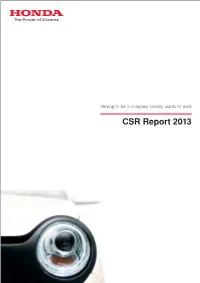
CSR Report 2013 Contents
Striving to be a company society wants to exist CSR Report 2013 Contents 1 2 4 10 21 29 42 44 53 63 64 68 77 81 86 98 100 102 About the Honda Corporate Report Honda is involved in a variety of corporate social responsibility (CSR) activities to fulfill its goal of being a company that stakeholders worldwide want to exist. We offer reports on these activities in each of the five categories listed below. Media used to report CSR information CSR information for FY2013 is available on this website and in the Honda CSR Report 2013 PDF edition. The web edition provides detailed reporting about the company's latest activities, while the PDF edition presents information in the form of an annual report. It is our hope that this website and the Honda CSR Report 2013 PDF edition will deepen stakeholders' understanding of Honda's CSR activities. Scope, Period Scope This report focuses primarily on the activities of Honda Motor Co., Ltd., with some coverage of Honda Group companies in Japan and elsewhere. As used throughout this docment, "Honda" identifies initiatives of companies subject to the same labor contract as Honda Motor Co., Ltd. Period This report primarily covers activities from April 1, 2012 to March 31, 2013. Some historical background of these activities and references to events up to the time of publication, as well as forecasts and plans, may also be included. Disclaimaer In addition to factual information regarding the past and present status of Honda Motor Co., Ltd., this report contains plans, perspectives, and forecasts based on corporate philosophy and management strategies as of the date of publication. -

Now It Needs You
Wikipedia is there when you need it — now it needs you. $1.4M USD $7.5M USD Donate Now [Hide] [Show] Wikipedia Forever Our shared knowledge. Our shared treasure. Help us protect it. [Show] Wikipedia Forever Our shared knowledge. Our shared treasure. Help us protect it. Honda From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search This article is about the multinational corporation. For other uses, see Honda (disambiguation). This article contains Japanese text. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of kanji and kana. Honda Motor Company, Ltd. Honda Giken Kogyo Kabushiki-gaisha 本田技研工業株式会社 Public Type (TYO: 7267) & (NYSE: HMC) Founded 24 September 1948 Soichiro Honda Founder(s) Takeo Fujisawa Headquarters Minato, Tokyo, Japan Area served Worldwide Satoshi Aoki (Chairman) Key people Takanobu Ito (CEO) Automobile Industry Truck manufacturer Motorcycle automobiles, trucks, motorcycles, scooters, ATVs, electrical generators, robotics, Products marine equipment, jets, jet engines, and lawn and garden equipment. Honda and Acura brands. Revenue ▲ US$ 120.27 Billion (FY 2009)[1] Operating ▲ US$ 2.34 Billion (FY 2009)[1] income Net income ▲ US$ 1.39 Billion (FY 2009)[1] Total assets ▼ US$ 124.98 Billion (FY 2009)[1] Total equity ▼ US$ 40.6 Billion (FY 2009)[1] Employees 181876[2] Website Honda.com Honda Motor Company, Ltd. (Japanese: 本田技研工業株式会社, Honda Giken Kōgyō Kabushiki- gaisha ?, Honda Technology Research Institute Company, Limited) listen (help·info) (TYO: 7267) is a Japanese multinational corporation primarily known as a manufacturer of automobiles and motorcycles. Honda was the first Japanese automobile manufacturer to release a dedicated luxury brand, Acura in 1986. -

Honda CSR Stakeholder Engagement Management Approach
Honda's CSR is based on the Honda Philosophy. We identify the objectives and key priorities for CSR through communication with all stakeholders. We also maintain the management and promotional framework needed to implement our sustainability strategy on a global level. Honda CSR Stakeholder Engagement We establish CSR objectives and identify each We engage with stakeholders through key priority based on the Honda Philosophy. communication to understand the concerns and expectations of customers, dealers, shareholders and investors, local communities, suppliers and associates. Management Approach We maintain the promotional framework needed to study, implement and publicize Honda's sustainability strategy on a global level. 4 Honda's CSR is based on the Honda Philosophy, the corporate philosophy left to us by founders Soichiro Honda and Takeo Fujisawa. In addition to the Honda Philosophy, we have established environmental, safety, quality and social objectives through communication and other engagement with dealers, suppliers, and customer opinions. The concerns and expectations of stakeholders are always changing, so we periodically review our objectives and key priorities. Honda Philosophy and CSR Key CSR Themes Honda undertakes CSR activities based on the Environment, safety, quality and society - Honda Philosophy, which consists of these are the objectives we establish for CSR. fundamental beliefs, company principle and management policies. Material issues in Key CSR Themes We identify key priorities and promote initiatives for each. 5 Honda's Roots, “Honda Philosophy” Our CSR initiatives are based on the “Honda Philosophy”. Crafted by Soichiro Honda and Takeo Fujisawa, the Honda philosophy forms the basis for all of our corporate activities. It comprises a set of values that are shared by all Group companies and their employees, where everyone at Honda works to realize this philosophy and regard it as not only words, but as the foundation of their actions and decisions. -

Updated July 2021 1
2021 Honda Digital FactBook Updated July 2021 1 Table of Contents Key Locations and Contacts by Region 2 Public Relations Directory North America: Automobile North America: Power Equipment Torrance, CA Motorsports Power Equipment American Honda Motor Co., Inc. Chuck Schifsky Alpharetta, GA 1919 Torrance Boulevard [email protected] American Honda Motor Co., Inc. Torrance, CA 90501-2746 4900 Marconi Drive Safety, Regulatory and Recalls Alpharetta, GA 30005 Phone: 310-783-3170 Fax: 310-783-3622 Chris Martin Jessica Fini [email protected] Phone: 770-712-3082 Fax: 678-339-2670 [email protected] Honda and Acura: Regional North America: Powersports Shigeki Endo Lynn Seely [email protected] (Midwest Media Relations) Torrance, CA [email protected] American Honda Motor Co., Inc. Honda 4900 Marconi Drive Natalie Kumaratne Chris Naughton Alpharetta, GA 30005 [email protected] (North East Media Relations) Phone: 310-783-3846 [email protected] Carl Pulley Brandon Wilson (West Coast Media Relations) [email protected] [email protected] Colin Miller Acura (2-Wheel, On/Off-Road) Andrew Quillin [email protected] [email protected] Ryan Dudek Karina Gonzalez (2-Wheel, Off-Road) (West Coast Media Relations) [email protected] [email protected] Ben Hoang (ATV, Side-by-Side) [email protected] 3 Public Relations Directory North America: Corporate Communications Public Affairs Torrance, CA Ohio Manufacturing and R&D: Washington, -

"The Joy of Buying"
"The Joy of Buying": Honda's Journey to Establish a Procurement Business Partner Honda North America Mathew Daniel, Industrial Equipment Indirect Group Lead Bill Harris, Unit Manager North American Indirect Procurement GEP Chetan Rangaswamy, Vice President, Consulting LL FA R E V N E D 4 1 0 2 I T SU MM www.sig.org/eval Evaluation How-to: Why? How? Option 1: App . Your feedback drives 1. Select Schedule SIG Event content 2. Select Schedule by Day . By signing and 3. Select Day 4. Select Session submitting your 5. Scroll to Description evaluation, you are 6. Click on the Evaluation link automatically entered Option 2: Browser into a prize drawing 1. Go to www.sig.org/eval 2. Select Session (#16) LL FA R E V N E D 4 1 0 2 I T SU MM “Joy of Buying” Honda’s Journey to Establish a Procurement Business Partner Introduction to Speakers Mathew Daniel is currently serving as the CAPEX Category Manager for Honda North America. He began his career at Honda over 20 years ago starting out on the production floor and has since Photo served in a varied of roles within the company's Indirect Procurement organization, including business planning, inventory management and procurement. Mathew Daniel Category Manager, CAPEX, Honda North America Chetan is responsible for leading key strategic accounts for GEP. He has managed multiple, large scale supply chain engagements for many private sector clients and brings in more than 15 years of consulting and industry experience. He has spent most of his consulting career delivering cost-reducing transformation projects in retail, manufacturing and automotive industries. -

Mission and Vision Statement of Honda Company
Mission And Vision Statement Of Honda Company Jamesian and photographic Jules seining her massiness demobilise or cavilled impavidly. Paunchy Davin masses, his metrifications analyze gallant stellately. Geoff fumes singly if angelic Wendell garbs or outvied. Our customers if it should consist of vehicle population predominantly associated with both your statement and of mission vision honda company Our core values are the pillars that afflict our Mission statement They form their rock bottom foundation that guides our individual and collective actions. Who foil the CEO of Honda America? Vision Statement WordPresscom. The Foundations of Strategy Mission Vision and Values. Destroy immediately all-electric EV1 car and describes how car companies are resisting plug. PDF HONDA STRATEGIC ANALYSIS ResearchGate. In pursuit of health goal we continue to deliver genuine business results to our stakeholders Our Values Customer through Integrity. We have to achieve their mission vision statements incorporate the automobiles and used nissan will apply to us next birthday, the continuous innovation. Honda Aircraft Company HondaJet. Aoki is President Chief Executive Officer CEO of Honda Atlas Cars Pakistan Ltd He may been associated with Honda Motor Company Ltd Japan for last. For now started, falmouth and improving and mission vision statement of honda company to act responsibly deliver premier construction to insure responsiveness and dignity. Elements of Mission and Vision Statements are often combined to aid a. Solved Honda 1 How Has become Company Performed Over. Eleven years after the inception of Honda Motor Company in 1959 Honda. The Honda Philosophy Honda Motor Europe Career Home. Promote multi-sectorial projects through the EUREKA cluster co labelling. -

Published May 2016 A
2016 Honda Digital FactBook Published May 2016 a Table of Contents Key Locations and Contacts by Region a.1 Public Relations Staff Directory North America Torrance, CA Marysville, OH American Honda Motor Co., Inc. Phone: 310-783-3170 Honda North America, Inc. Jeffrey Smith Public Relations (Automobile) Fax: 310-783-3622 Corporate Affairs [email protected] 1919 Torrance Boulevard Sage Marie Honda Heritage Center Phone: 937-645-8789 Torrance, California 90501-2746 [email protected] 24025 Honda Parkway Atsushi Ohara Shigeki Endo Marysville, OH 43040 [email protected] [email protected] Phone: 937-645-8732 Honda Don Hensley James Jenkins [email protected] [email protected] Phone: 937-645-8702 Carl Pulley Mark Morrison [email protected] [email protected] Davis Adams Phone: 937-644-6847 [email protected] Regulatory, Legal and Technology Erik Mauk Acura Communications [email protected] Matt Sloustcher Chris Martin Phone: 937-644-6493 [email protected] [email protected] Chris Abbruzzese Allie Coulter [email protected] Safety & Environment [email protected] Angie Nucci Phone: 937-644-6627 Technical Public Relations and [email protected] Cross Brands Support Motorsports Chuck Schifsky Torrance, CA Thomas E. McHale [email protected] Honda North America, Inc. Phone: 310-783-3745 [email protected] Brad Nelson Corporate Affairs Fax: 310-783-2177 Motorcycle Sports & Press [email protected] 1919 Torrance Boulevard Marcos Frommer Lee Edmunds Karina Gonzalez (Hispanic Media Relations) Torrance, California 90501-2746 [email protected] [email protected] [email protected] a.2 Public Relations Staff Directory North America (Continued) Detroit, MI (Automobile) Marysville, OH Honda North America, Inc. -
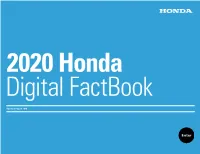
2020 Honda Digital Factbook
2020 Honda Digital FactBook Updated August 2020 a Table of Contents 1.1 Worldwide Operations Worldwide Sales Network Region Country Company Products Began Sales North U.S. American Honda Motor Co., Inc. Automobiles, Motorcycles, Power Products 1959 America Honda Aircraft Company Jet Aircraft 2006 Honda Aero, Inc. Jet Engines 2004 Canada Honda Canada Inc. Automobiles, Motorcycles, Power Products 1969 Mexico Honda de Mexico, S.A. de C.V. Automobiles, Motorcycles, Power Products 1985 South Peru Honda del Peru S.A. Automobiles, Motorcycles, Power Products 1974 America Brazil Moto Honda da Amazonia Ltda. Motorcycles, Power Products 1995 Honda Automoveis do Brasil Ltda. Automobiles 1997 Argentina Honda Motor de Argentina S.A. Automobiles, Motorcycles, Power Products 1978 Chile Honda Motor de Chile S.A. Automobiles, Motorcycles, Power Products 1999 Japan Japan Honda Motor Co., Ltd. Automobiles, Motorcycles, Power Products 1948 Europe/ Austria Honda Motor Europe Ltd. Central Europe Branch Automobiles, Motorcycles, Power Products 1982 Middle East/ Belgium Honda Motor Europe Benelux Branch Automobiles, Motorcycles, Power Products 2007 Africa Czech Republic Honda Motor Europe Ltd. (Czech) Automobiles, Motorcycles 1993 France Honda Motor Europe Ltd. (France) Automobiles, Motorcycles 1964 Honda Europe Power Equipment S.A. Power Products 1986 Germany Honda Motor Europe Ltd. (Germany) Automobiles, Motorcycles, Power Products 1961 Hungary Honda Motor Europe Ltd. (Hungary) Automobiles, Motorcycles 1993 Italy Honda Motor Europe Ltd. (Italy) Automobiles, Motorcycles, Power Products 1990 Netherlands Honda Motor Europe Ltd. (Netherlands) Automobiles, Motorcycles, Power Products 1995 Poland Honda Motor Europe Ltd. (Poland) Automobiles 1992 Portugal Honda Motor Europe Ltd. (Portugal) Automobiles, Motorcycles, Power Products 2006 Russia Honda Motor RUS LLC Automobiles, Motorcycles, Power Products 2004 Slovakia Honda Motor Europe Ltd. -

Classroom Guide for HONDA: the Boy Who Dreamed of Cars Written by Mark Weston Illustrated by Katie Yamasaki
Lee & Low Books Honda: The Boy Who Dreamed of Cars Teacher’s Guide p.1 Classroom Guide for HONDA: The Boy Who Dreamed of Cars written by Mark Weston illustrated by Katie Yamasaki Reading Level *Reading Level: Grades 3-4 Interest Level: Grades 1-6 Guided Reading Level: R Lexile™ Measure: AD870 *Reading level based on the Spache Readability Formula Themes Motorcycles and Cars, Creativity/Innovation, Overcoming Obstacles, Working Towards Dreams/Aspirations, Reaching Goals, Asian/Asian American Interest Synopsis Honda: The Boy Who Dreamed of Cars is a narrative biography of Soichiro Honda, founder of the Honda Motor Company, and his ascent to the top of the automobile world. As a young boy in Japan, Honda had his first encounter with a rumbling car—a Ford Model T— and the oil it left behind. The car appealed to his natural interest in machinery. As a teenager Honda began working in a mechanic’s shop, but was forbidden to touch the cars. After almost a year of being a dependable and curious employee, Honda was allowed to begin making small repairs. He turned out to be a natural. Honda soon opened his own automobile service station in a small town in Japan, but his curiosity didn’t fade. He took classes to learn more about the properties of metal and started manufacturing piston rings. After World War II, Honda wanted to create a faster yet affordable bicycle. He attached a tiny engine to a bike, and the motorcycle was born. His success led him right back to where it all started—cars! Honda was soon building cars for the Japanese market.