Earthquake Research Institute 東京大学地震研究所
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vaitoskirjascientific MASCULINITY and NATIONAL IMAGES IN
Faculty of Arts University of Helsinki, Finland SCIENTIFIC MASCULINITY AND NATIONAL IMAGES IN JAPANESE SPECULATIVE CINEMA Leena Eerolainen DOCTORAL DISSERTATION To be presented for public discussion with the permission of the Faculty of Arts of the University of Helsinki, in Room 230, Aurora Building, on the 20th of August, 2020 at 14 o’clock. Helsinki 2020 Supervisors Henry Bacon, University of Helsinki, Finland Bart Gaens, University of Helsinki, Finland Pre-examiners Dolores Martinez, SOAS, University of London, UK Rikke Schubart, University of Southern Denmark, Denmark Opponent Dolores Martinez, SOAS, University of London, UK Custos Henry Bacon, University of Helsinki, Finland Copyright © 2020 Leena Eerolainen ISBN 978-951-51-6273-1 (paperback) ISBN 978-951-51-6274-8 (PDF) Helsinki: Unigrafia, 2020 The Faculty of Arts uses the Urkund system (plagiarism recognition) to examine all doctoral dissertations. ABSTRACT Science and technology have been paramount features of any modernized nation. In Japan they played an important role in the modernization and militarization of the nation, as well as its democratization and subsequent economic growth. Science and technology highlight the promises of a better tomorrow and future utopia, but their application can also present ethical issues. In fiction, they have historically played a significant role. Fictions of science continue to exert power via important multimedia platforms for considerations of the role of science and technology in our world. And, because of their importance for the development, ideologies and policies of any nation, these considerations can be correlated with the deliberation of the role of a nation in the world, including its internal and external images and imaginings. -

JAWS Conference Istanbul 2015 Abstracts 1 List of Abstracts JAWS
JAWS Conference Istanbul 2015 Abstracts List of abstracts JAWS Conference 2015 September 2 9.00-10.30, Parallel Session 1 Panel: ‘Robot technology and elderly care in Japan’ Convenor: Cosima Wagner (Freie Universität Berlin) Technology and demographic change, with visions and concepts for future technology (e.g. a “robot-assisted society”) Martin Rathmann (Heidelberg University) Japan has the world's longest life expectation and highest proportion of older people in its population. As a result the delivery of old-age care is becoming of paramount concern as a problem of the welfare state but actual care giving in an industrial nation that for a long time has been adverse to immigration. Japanese technocrats are now increasingly investing in technology as a possible addition to traditional care-giving options. Within these plans robotics are supposed to play a central role as postulated by the policy papers of the Ministry of Economy, Trade and Industry. This study will examine the extent and limitations of the development of robotics in care-giving in Japan to understand whether one day these may also become a model to an aging world. The welfare system in Japan has been under stress with the Japanese state being one of the most indebted states in the world after a quarter century of lackluster economic growth and a population of baby boomers now nearing retirement. The current state of care-giving and their actual provisions will form an important backdrop to a further examination of the possible health-care needs and ranges of social acceptance of technology in daily life and old-age care. -
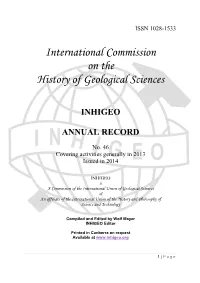
INHIGEO Annual Record No
ISSN 1028-1533 International Commission on the History of Geological Sciences INHIGEO ANNUAL RECORD I No. 46 Covering activitiesI generally in 2013 Issued in 2014 INHIGEO is A Commission of the International Union of Geological Sciences & An affiliate of the International Union of the History and Philosophy of Science and Technology Compiled and Edited by Wolf Mayer INHIGEO Editor Printed in Canberra on request Available at www.inhigeo.org 1 | Page 2 | Page CONTENTS INHIGEO Annual Record No. 46 (Published in May 2014 covering events generally in 2013) INHIGEO BOARD 7 MESSAGES TO MEMBERS President‘s Message: Kenneth L. Taylor 8 Secretary-General‘s Report: Barry Cooper 9 Editor’s Message: Wolf Mayer 10 INHIGEO 2014 – Asilomar, California, United States 12 INHIGEO 2015 – Beijing 13 INHIGEO 2016 – Cape Town 13 LATER INHIGEO CONFERENCES 14 OTHER INHIGEO BUSINESS NOTICES Liaison with other IUGS Commissions and Task Groups 14 INHIGEO Affiliated Association category 15 INHIGEO Virtual Bibliography 16 A message encouraging INHIGEO members to join HESS 18 INHIGEO CONFERENCE AND EXCURSION REPORTS Report on the INHIGEO Meeting, Manchester, United Kingdom, 22-27 July 2013 19 Pre-congress Field Trip: The Silurian of ‘Siluria’ and the Idea of a Palaeozoic Era 24 Intra-congress trip: Buxton Spar and Buxton Spa 28 Post-congress fieldtrip: Ruskin’s Geology 30 International Congress of the History of Science, Technology and Medicine – Manchester 2013 34 MANCHESTER MANIFESTO 36 3 | Page OTHER CONFERENCE REPORTS Past, present and future of human connections to the Antarctic 37 CONFERENCES OF INTEREST The BSHS Annual Conference, 6 July 2014, at the University of St Andrews. -
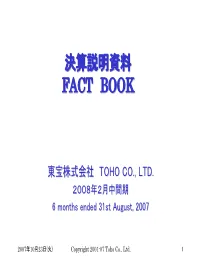
決算説明資料 Summary of Annual Report
決算説明資料決算説明資料 FACTFACT BOOKBOOK 東宝株式会社東宝株式会社 TOHOTOHO CO.,CO., LTD.LTD. 2008年2月中間期 6 months ended 31st August, 2007 2007年10月23日(火) Copyright 2001-07 Toho Co., Ltd. 1 目次 1 Contents 1 経営指標 Financial Highlights P. 5 経営指標(親会社) Financial Highlights (Parent company) P.13 連結の範囲に関する事項 Scope of consolidation P.21 持分法の適用に関する事項 Application of the equity method P.21 業績の概要 Outline of operating results セグメント情報 Segment information P.22 映画事業 Cinema business 業績の推移 Change of operating result P.28 主要な事業内容 Major business lines P.29 売上高内訳 Breakdown of sales P.29 売上高の推移 Change of sales P.30 映画営業 Movie production and distribution 主要な映画製作・配給子会社 Major production and distribution subsidiaries P.32 代表的な作品 Important films P.32 題名別興行収入 Box-office per title P.33 配給本数/製作本数 Number of films distributed / produced P.34 2006年(自然暦)興行収入シェアー Box-office market share in CY2006 P.35 会社別興行市場の推移 Change of box-office market P.36 興行市場の推移 Change of box-office market P.37 2006年(自然暦)邦洋興行収入シェアー Box-office share in CY2006 (Domestic films/foreign films) P.37 配給市場の推移 Change of film distribution market P.38 1999年12月現在国内洋画配給収入記録 Sales records of foreign film distribution in Japan as of Dec. 1999 P.39 1999年12月現在国内邦画配給収入記録 Sales records of domestic film distribution in Japan as of Dec. 1999 P.39 2006年12月現在国内洋画興行収入 Box-office receipts of foreign film in Japan as of Dec. 2006 P.40 2006年12月現在国内邦画興行収入 Box-office receipts of domestic film in Japan as of Dec. 2006 P.40 市場構造 Market structure P.41 2007年10月23日(火) Copyright 2001-07 Toho Co., Ltd. 2 目次 2 Contents 2 映画興行 Exhibition スクリーン数/入場者数 Number of -

International Commission on the History of Geological Sciences
ISSN 1028-1533 International Commission on the History of Geological Sciences INHIGEO ANNUAL RECORD I No. 46 Covering activitiesI generally in 2013 Issued in 2014 INHIGEO is A Commission of the International Union of Geological Sciences & An affiliate of the International Union of the History and Philosophy of Science and Technology Compiled and Edited by Wolf Mayer INHIGEO Editor Printed in Canberra on request Available at www.inhigeo.org 1 | P a g e INSIDE COVER (Please scroll down) 2 | P a g e CONTENTS INHIGEO Annual Record No. 46 (Published in May 2014 covering events generally in 2013) INHIGEO BOARD 7 MESSAGES TO MEMBERS President‘s Message: Kenneth L. Taylor 8 Secretary-General‘s Report: Barry Cooper 9 Editor’s Message: Wolf Mayer 10 INHIGEO 2014 – Asilomar, California, United States 12 INHIGEO 2015 – Beijing 13 INHIGEO 2016 – Cape Town 13 LATER INHIGEO CONFERENCES 14 OTHER INHIGEO BUSINESS NOTICES Liaison with other IUGS Commissions and Task Groups 14 INHIGEO Affiliated Association category 15 INHIGEO Virtual Bibliography 16 A message encouraging INHIGEO members to join HESS 18 INHIGEO CONFERENCE AND EXCURSION REPORTS Report on the INHIGEO Meeting, Manchester, United Kingdom, 22-27 July 2013 19 Pre-congress Field Trip: The Silurian of ‘Siluria’ and the Idea of a Palaeozoic Era 24 Intra-congress trip: Buxton Spar and Buxton Spa 28 Post-congress fieldtrip: Ruskin’s Geology 30 International Congress of the History of Science, Technology and Medicine – Manchester 2013 34 MANCHESTER MANIFESTO 36 3 | P a g e OTHER CONFERENCE REPORTS Past, present and future of human connections to the Antarctic 37 CONFERENCES OF INTEREST The BSHS Annual Conference, 6 July 2014, at the University of St Andrews. -

INSTRUMENT of SURRENDER We, Acting by Command of and in Behalf
INSTRUMENT OF SURRENDER We, acting by command of and in behalf of the Emperor of Japan, the Japanese Government and the Japanese Imperial General Headquarters, hereby accept the provisions set forth in the declaration issued by the heads of the Governments of the United States, China, and Great Britain on 26 July 1945 at Potsdam, and subsequently adhered to by the Union of Soviet Socialist Republics, which four powers are hereafter referred to as the Allied Powers. We hereby proclaim the unconditional surrender to the Allied Powers of the Japanese Imperial General Headquarters and of all Japanese armed forces and all armed forces under the Japanese control wherever situated. We hereby command all Japanese forces wherever situated and the Japanese people to cease hostilities forthwith, to preserve and save from damage all ships, aircraft, and military and civil property and to comply with all requirements which my be imposed by the Supreme Commander for the Allied Powers or by agencies of the Japanese Government at his direction. We hereby command the Japanese Imperial Headquarters to issue at once orders to the Commanders of all Japanese forces and all forces under Japanese control wherever situated to surrender unconditionally themselves and all forces under their control. We hereby command all civil, military and naval officials to obey and enforce all proclamations, and orders and directives deemed by the Supreme Commander for the Allied Powers to be proper to effectuate this surrender and issued by him or under his authority and we direct all such officials to remain at their posts and to continue to perform their non-combatant duties unless specifically relieved by him or under his authority. -

JAWS 2015 Program
FINAL Programme JAWS 2015 conference in Istanbul, 1-4 September 2015 1.9.2015 (Tuesday) Event 9 – 10 Arrival of participants 10 – 11 11 – 12 Supervision for graduate students (organized individually) 12 – 13 13 – 14 All four rooms reserved for the conference are located in the Faculty of Arts and Sciences. South Campus will be available for the tutorials. 14 – 15 Rooms and their respective capacities are: TB310 (120 seats), TB490 (50 seats), TB415 (30 seats) and TB240 (40 seats) 15 – 16 16 - 17 17 - 18 18 – 19 Reception for all participants 19 – 20 2.9.2015 (Wednesday) Parallel Session I - Room: TB310 Parallel Session II - Room: TB490 9:00 – 10:30 Panel ‘Robot technology and elderly care in Japan’ Panel ‘Considering Japanese Culture, Communities, and the Interface Organizer & Chair: Cosima Wagner, Freie Universität Berlin of Technology and Nature in Post 2011 (3.11) Disasters Japan’ Organizer & Chair: Millie Creighton, University of British Columbia Technology and demographic change, with visions and Modernity Emerging in the process of Reconstruction after Big concepts for future technology (e.g. a “robot-assisted Earthquake in Japan; The Complex Relationship between the society”) Community Resilience and the planning by city engineering Martin Rathmann, Heidelberg University Hiroki Okada, Kobe University Elderly Care, Robot-Technology and the Quest for a Wasuren! (We Won’t Forget!): Remembering, Rebuilding, Resiliency Japanese „Roboethics“ in Japan’s Disasters Affected Communities Confronting Post-3.11 Cosima Wagner, Freie Universität -

Sinking of Japan Dvdrip with English Subtitles
Sinking Of Japan DVDRip With English Subtitles 1 / 4 Sinking Of Japan DVDRip With English Subtitles 2 / 4 3 / 4 50e0b7e615 Sinking Of Japan DVDRip With English Subtitles DOWNLOAD LINK:. It was then I remembered that I had seen the English translation of Sakyo Komatsu's novel some years back. I got it, and it was quite good, as well as chillingly .... Sinking of Japan is a 2006 tokusatsu film directed by Shinji Higuchi. It is an adaptation of the ... Prior to the release of the film, TBS released The Encyclopedia of Sinking of Japan, a special one-hour DVD featuring interviews with the cast and .... Japan Sinks is a disaster novel by Japanese writer Sakyo Komatsu, published in 1973. ... However, the sinking Japanese archipelago complicates their escape. ... trying to communicate with her through Morse Code, provides him with an translation app and learns that he is Onodera, ... Download as PDF · Printable version .... Sep 3, 2013 - Watch Sinking of Japan online English subtitle full episodes for Free. ... Sinking of Japan | Watch Korean drama online, Korean drama English subtitle ... Download premium vector of Butterfly with white peonies and brown paper.. After catastrophic earthquakes devastate Japan, one family's resolve is tested on a journey of survival through the sinking archipelago. Starring:Reina Ueda, Tomo ... They escape with the owner, picking up an English hitchhiker along the way. Watch Illusion. Episode 5 of ... More Details. Watch offline. Available to download.. Download [EMBER] Japan Sinks: 2020 (Season 1) [1080p] [HEVC WEBRip] (Nihon Chinbotsu 2020) Anime Torrent. File size: 3.7 GiB .... It is a remake of the 1973 Toho film Submersion of Japan and, like its predecessor, adapts the disaster novel .. -

The Sinking of Japan
Volume 4 | Issue 8 | Article ID 2188 | Aug 14, 2006 The Asia-Pacific Journal | Japan Focus The Sinking of Japan Mark Schilling The Sinking of Japan By Mark Schilling The new disaster epic "Nippon Chinbotsu" (The Sinking of Japan) exploits one of those simple but brilliant ideas that has hacks everywhere slapping their foreheads with envy. The kernel - - Japan is mortally threatened by a powerful force seemingly beyond human control -- is that of dozens of monster and disaster pics, but in his eponymous 1973 novel, Sakyo Komatsu took it one step further: He imagined Japan, not stomped by giant lizards, but literally sinking as a collision of two tectonic plates causes the one supporting the archipelago to buckle under. The result is not only new oceanfront property, but a hellbroth of earthquakes and volcanos that kill millions and force the evacuation of the entire country. "Nippon Chinbotsu," which plugged into ancient and well-founded fears about the fragility of the natural order here ("as solid as the ground you walk on" is not a Japanese saying), became a monster bestseller. Not long after the novel's publication in March, 1973, Toho cranked out a "Nippon Chinbotsu" movie, spending a then-stupendous Y500 million. Released in time for the New Year's season, it grossed Y4 billion on 6.5 million admissions, the sort of numbers that put even Godzilla -- another Toho property -- in the shade. (Like the first Godzilla movie it was later released in the US in a butchered version, called "Tidal Wave," with a famous Hollywood face -- Lorne Green as 1 4 | 8 | 0 APJ | JF the US president -- inserted into the story.) raining down outside.