年 報 ⅰ 部門報告 国際プログラム部門 ・国際プログラム群(G30) ・交換留学受入プログラム(Nupace) ・短期日本語プログラム(Nustep) ・G30日本語教育 教育交流部門 アドバイジング部門 海外留学部門
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Singapore and Asian Schools Math Olympiad 2015
SINGAPORE AND ASIAN SCHOOLS MATH OLYMPIAD 2015 PRIMARY 3 (GRADE 3) RESULTS TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS: 4109 Global COUNTRY SCHOOL NAME AWARD Ranking 1 BULGARIA ST GEORGI PRIVATE SECONDARY SCHOOL MARIA NIKOLAEVA DRENCHEVA PERFECT SCORE 1 BULGARIA P. R. SLAVEYKOV PRIMARY SCHOOL MIHAIL PETKOV MIHOV PERFECT SCORE 1 SINGAPORE NORTH SPRING PRIMARY SCHOOL SIDDHAARTH DHARANI PERFECT SCORE 1 HONG KONG 聖公會青衣主恩小學 姚縉熹 PERFECT SCORE 1 HONG KONG 英華小學 [全日] 梁綽廷 PERFECT SCORE 6 BULGARIA 107 KHAN KRUM PRYMARY SCHOOL ALEKSANDAR ORLINOV GICHEV GOLD AWARD 6 BULGARIA ANGEL KANCEV PRIMARY SCHOOL YOANA RUMENOVA DONCHEVA GOLD AWARD 8 HONG KONG 嘉諾撒聖瑪利學校 [全日] 梁樂浠 GOLD AWARD 8 HONG KONG 香港培正小學 [全日] 楊栢喬 GOLD AWARD 8 HONG KONG 英華小學 [全日] 林一澤 GOLD AWARD 8 HONG KONG 農圃道官立小學 [全日] 歐陽張維 GOLD AWARD 12 CHINA DULWICH COLLEGE SHANGHAI JOSH YIU GOLD AWARD 12 SINGAPORE QIFA PRIMARY SCHOOL TAY YIWEI DAVID GOLD AWARD 12 HONG KONG 拔萃女小學 周芷悠 GOLD AWARD 12 HONG KONG 香港培正小學 陳善樂 GOLD AWARD 12 HONG KONG 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 黃卓琳 GOLD AWARD 12 HONG KONG 喇沙小學 賴煒諾 GOLD AWARD 12 HONG KONG 番禺會所華仁小學 麥題鑠 GOLD AWARD 12 HONG KONG 聖公會德田李兆強小學 吳禮匡 GOLD AWARD 20 HONG KONG 順德聯誼總會何日東小學 關頌軒 GOLD AWARD 21 HONG KONG 聖方濟各英文小學 [全日] 劉星言 GOLD AWARD 21 HONG KONG 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 [全日] 黃竣壕 GOLD AWARD 23 HONG KONG 嘉諾撒聖瑪利學校 [全日] 何晴晴 GOLD AWARD 23 HONG KONG 天主教石鐘山紀念小學 [全日] 劉浩浚 GOLD AWARD 23 PHILIPPINES SAINT JOSEPH CATHOLIC SCHOOL DY, OLIVER PAREDES GOLD AWARD 26 SINGAPORE ANGLO-CHINESE SCHOOL (JUNIOR) LIM ZHE XI, ZENNETH GOLD AWARD 26 SINGAPORE INNOVA PRIMARY SCHOOL TOH YU QI GOLD AWARD 26 HONG KONG 英華小學 [全日] 甘政霖 GOLD AWARD 26 HONG KONG 優才(楊殷有娣)書院 翁朗希 GOLD AWARD 26 HONG KONG 軒尼詩道官立小學 [上午] 顏宇恆 GOLD AWARD 26 HONG KONG 荔枝角天主教小學 [全日] 黃乙峯 GOLD AWARD 26 HONG KONG 聖公會田灣始南小學 [全日] 黃宇熙 GOLD AWARD 33 UZBEKISTAN LIDER SCHOOL GALPERIN ROMAN GOLD AWARD 33 HONG KONG 大埔舊墟公立學校 鄧信希 GOLD AWARD 33 HONG KONG 大角咀天主教小學 洪瑋鍵 GOLD AWARD 33 HONG KONG 英華小學 [全日] 黃梓鋒 GOLD AWARD 33 PHILIPPINES LA SALLE GREEN HILLS ABARA, THEODORE D. -
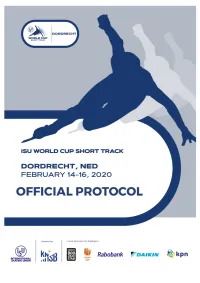
Result Protocol
Event Officials ISU Representative Sergio Anesi ITA TC Representative Nathalie Lambert CAN ISU Event Coordinator Hugo Herrnhof ITA Referee Peter Worth GBR 1st Assistant Referee Toshihiko Nitta JPN Assistant Referee Sarah Henderson GBR Assistant Referee Video Balázs Kövér HUN Starter Ladies Antal Novak HUN Starter Men Jan Bergmans NED Competitors Steward Hermann Filipic AUT Competitors Steward Daan Brand NED Apprentice Assistant Referee Video Alexandra Valach SVK Trainee Referee Jurre Krijgsheld NED Trainee Starter Piet van Hoeven NED Trainee Competitors Steward Martijn Brand NED Heatbox Steward Harold Janssen NED Organising Committee Head of LOC Mr. Niels Markensteijn Tournament Director Mr. Cees Juffermans Logistics Mr. Bas Middelkoop Competition Ms. Sandra Vrakking Accreditation Ms. Tanja Beukers Press Ms. Emilie Fokker Ms. Helma van Drie Volunteers / Local Judges Mr. Carel Thijsse Mr. Ruud de Groot Competition Secretary Ms. Gitta Hanrath Account Ms. Jose Holster Hospitality Ms. Jose Holster Accountant, Payments Ms. Gerda Lasschuit Accommodation Ms. Gitta Hanrath Airport, Transportation Mr. Joost Schilthuis Chief of Medical Team Mr. Alexander Veen List of Team Officials Australia Richard Nizielski Coach Austria Ivan Pandov Team Leader Belgium Corné Lepoeter Team Leader Steven Peeters Coach Pieter Gysel Coach Coremans Fabienne Physiotherapist Preat Philippe Physiotherapist Mathias Peeters Doctor Jeroen Straathof Equipment Technician Gunter Werner Equipment Technician Rob Veldhoven Video Specialist Belarus Ihar Osipau Team Leader Bulgaria -

United Nations Bluebook August 2018 Nº 307/Rev.5
ST/PLS/SER.A/307/Rev.5 Protocol and Liaison Service Permanent Missions to the United Nations Nº 307/Rev.5 August 2018 United Nations, New York Note: This publication is prepared by the Protocol and Liaison Service for information purposes only. The listings relating to the permanent missions are based on information communicated to the Protocol and Liaison Service by the permanent missions, and their publication is intended for the use of delegations and the Secretariat. They do not include all diplomatic and administrative staff exercising official functions in connection with the United Nations. Further information concerning names of members of permanent missions entitled to diplomatic privileges and immunities and other mission members registered with the United Nations can be obtained from: Protocol and Liaison Service Room S-0209 United Nations New York, NY, 10017 Telephone: 212-963-2938 Telefax: 212-963-1921 E-mail: [email protected] Website: http://protocol.un.org All changes and additions to this publication should be communicated to the above Service © 2018 United Nations Language: English United Nations Protocol and Liaison Service Address: Protocol and Liaison Service of the United Nations 405 East 42nd Street, Room S-0201 New York, NY 10017 Telephone: 212-963-7170, 212-963-7171 (General) 212-963-7181 (Accreditation) Telefax: 212-963-1921 E-mail: [email protected] Website: protocol.un.org 212-963-7175 Mr. Peter Van Laere [email protected] Chief of Protocol 917-367-4320 Ms. Nicole Bresson-Ondieki [email protected] Deputy Chief of Protocol 212-963-0720 Ms. Pilar Fuentes-Conte [email protected] Senior Protocol Officer 212-963-7177 Mr. -
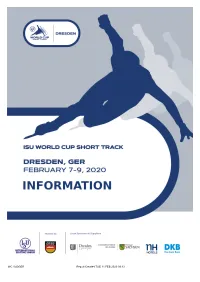
Result Protocol
WC1920GER Report Created TUE 11 FEB 2020 08:13 Event Officials ISU Representative : Mr. Roland Maillard Representative of the Short Track Speed Skating Technical Committee: Mr. Satoru Terao ISU Event coordinator: Mr. Hugo Herrnhof Referee: Mr. Alan Grefsheim, USA Assistant Referee: Mr. Yong Li, CHN Assistant Referee: Mr. Livio Mella, ITA Assistant Referee: Ms. Polona Peunik, SLO Assistant Referee Video *: Mr. Michel Dumont, CAN Starter: Mr. Jeroen Strijker, NED Mr. Luciano Dalbard, ITA Competitors Stewards: Mr. Stéphane Larrière, FRA Ms. Christel Petzschke, GER * Will act as 1st Assistant Referee in accordance with Rule 290, paragraphs 1.a) and 7.a) Heatbox Steward Mr. Maximilian Markgraf, GER Trainee Assistant Referee Video Ms. Sarah Henderson, GBR Apprentice Referee Mr. Tilo Michel, GER Apprentice Starter Mr. Jan Häupl, GER Apprentice Competitors Steward Ms. Gabriele Rietzke, GER Organizing Committee President of Organizing Committee Mr. Uwe Rietzke, GER Head of Organizing Committee Mr. Chistoph Zepernick, GER Head of Operations Ms. Marie Redecker, GER Head of Public relations Ms. Eva Wagner, GER Head of Logistics Mr. Jonas Trost, GER Head of Audio and Video Production Mr. Dennis Falkenberg, GER Head of Shuttle Service Mr. Christian Kischel, GER Head of Accreditation Ms. Antje Moser,GER List of Teamofficials Australia Richard NIZIELSKI Coach Austria Ivan PANDOV Team Leader Belgium Corné LEPOETER Team Leader Pieter GYSEL Coach Gunter WERNER Additional Belarus Ihar OSIPAU Team Leader Siarhei ZHYHALKA Coach Bulgaria Yulian ANGELOV Team -

Forslag Til Lov Om Indfødsrets Meddelelse
Udskriftsdato: 24. september 2021 2018/1 LSF 81 (Gældende) Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse Ministerium: Udlændinge og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge og Integrationsmin., j.nr. 2018 2373 Fremsat den 25. oktober 2018 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse § 1. Indfødsret meddeles: 1) Abdullah Ahmed Abdelkader, Aarhus. 2) Saceed Ali Abdi, København. 3) Yusuf Abdi, Struer. 4) Bujar Abdii, Rødovre. 5) Abdirisaq Abdulahi, København. 6) Kazhal Majeed Abdulla, Frederikssund. 7) Marat Abdullaev, København. 8) Shwan Fahed Abdullah, Horsens. 9) Sura Azhar Abdulmunem, Greve. 10) Ban Kamal Abdulrazaq, Halsnæs. 11) Hanan Abed, Aarhus. 12) Taysir Mohamad Abed-Allah, København. 13) Mirza Sultan Mahmood Abid, Brøndby. 14) Rachid Abourrida El Kadmiri, København. 15) Rania Abu Almeiza, Hjørring. 16) Abeer Rafat Kamel Abu-Khesha, Næstved. 17) Rasha Abul Jamous, Hvidovre, dog uden virkning for ansøgerens barn født i 2012. 18) Abdulfatah Sheikhbihi Adam, København. 19) Melat Ademas, Brøndby. 20) Ramesh Adhikari, Faxe. 21) Mehrdad Adili, Kolding. 22) Mehrshad Adili, Odense. 23) Rahma Siad Adow, Ishøj. 24) Soroush Afkhamimeybodi, Esbjerg. 25) Olga Caroline Agerskov, Lyngby-Taarbæk. 26) Sanaz Aghajani, København. 27) Mohammed Khaled Ahmed, Lyngby-Taarbæk. 28) Samir Muhamed Ahmed, København. 29) Saynab Saiid Ahmed, Aalborg. 30) Bajro Ahmic, Esbjerg. 31) Juan Alejandro Ahumada Montenegro, Randers. 32) Sampreethi Aipanjiguly, København. 33) Fahrudin Ajanovic, København. 34) Shahnaz Akhtar, Ballerup. 35) Ayesha Akter, København. 36) Martina Al Kharaz, Høje-Taastrup. 37) Muhanad Al Mari, Ballerup. 38) Ayeit Karim Al-Absawi, Frederiksberg. 39) Renata Al-Atrash, København. 2018/1 LSF 81 1 40) Khaled Bakeit Ibrahim Al-Badri, Gladsaxe. 41) Maria Victoria Lunde Alcon, Egedal. -

Maria Todorova, Imagining the Balkans.Pdf
Preface Imagining the Balkans This page intentionally left blank Imagining the Balkans Updated Edition Maria Todorova 1 2009 1 Oxford University Press, Inc., publishes works that further Oxford University’s objective of excellence in research, scholarship, and education. Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With Offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Copyright © 2009 by Oxford University Press, Inc. Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York 10016 www.oup.com Oxford is a registered trademark of Oxford University Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Oxford University Press. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Todorova, Maria Nikolaeva. Imagining the Balkans / Maria Todorova.—updated ed. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978- 0-19-538786-5 1. Balkan Peninsula—Historiography. I. title. DR34.T63 1997 96-7161 949.6—dc20 987654321 Printed in the United States of America on acid-free paper To my parents, from whom I learned to love the Balkans without the need to be proud or ashamed of them. This page intentionally left blank Preface The hope of an intellectual is not that he will have an effect on the world, but that someday, somewhere, someone will read what he wrote exactly as he wrote it. -

Permanent Missions to the United Nations
Permanent Missions to the United Nations ST/PLS/SER.A/308/Rev.1 Protocol and Liaison Service Permanent Missions to the United Nations Nº 308 Rev.1 July 2019 United Nations, New York Note: This publication is prepared by the Protocol and Liaison Service for information purposes only. The listings relating to the permanent missions are based on information communicated to the Protocol and Liaison Service by the permanent missions, and their publication is intended for the use of delegations and the Secretariat. They do not include all diplomatic and administrative staff exercising official functions in connection with the United Nations. Further information concerning names of members of permanent missions entitled to diplomatic privileges and immunities and other mission members registered with the United Nations can be obtained from: Protocol and Liaison Service Room S-0209 United Nations New York, NY, 10017 Telephone: 212-963-2938 Telefax: 212-963-1921 E-mail: [email protected] Website: http://protocol.un.org All changes and additions to this publication should be communicated to the above Service © 2019 United Nations Language: English United Nations Protocol and Liaison Service Address: Protocol and Liaison Service of the United Nations 405 East 42nd Street, Room S-0201 New York, NY 10017 Telephone: 212-963-7170, 212-963-7171 (General) 212-963-7181 (Accreditation) Telefax: 212-963-1921 E-mail: [email protected] Website: protocol.un.org 917-367-6166 Ms. Beatrix Kania [email protected] Chief of Protocol 917-367-4320 Ms. Nicole Bresson-Ondieki [email protected] Deputy Chief of Protocol 212-963-0720 Ms. -

New Bishop Lee Attends 45Th Anniversary of Saint Paul's School
ALLEGED THIEF CAUGHT VIETNAM: PM WITHDRAWS FROM AFTER TAKING ‘SELFIES’ CHAIN STORE CONTEST FOR PARTY CHIEF A domestic helper, who was Vietnam’s pro-business prime illegally residing in the territory, was ORIGINS minister has effectively withdrawn caught in a strange case involving from a contest to become the QUESTIONED theft and false statements Communist Party chief P5 CRIME P6 RETAIL P12 TUE.26 Jan 2016 T. 6º/ 13º C H. 45/ 90% Blackberry email service powered by CTM MOP 7.50 2485 N.º HKD 9.50 FOUNDER & PUBLISHER Kowie Geldenhuys EDITOR-IN-CHIEF Paulo Coutinho “ THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’ ” WORLD BRIEFS XINHUA COLD takES ITS TOLL CHINA-LAOS The prime minister of communist Laos assures US Secretary of State John Kerry that the small nation will help counter One died in China’s assertiveness in the South China Sea. More on p11 Macau, scores AP PHOTO in greater China P3 CHINA-VIETNAM Divided opinions within Vietnam’s Communist Party on how to relate to giant neighbor and one-time ally China are among key factors in play at an eight-day congress to choose new leadership. More on p12 THAILAND A Japanese rocket maker says a large piece of metal that washed up on a beach in Thailand is likely part of a rocket launched by Japan, not a missing Malaysian plane. The discovery of the metal sparked speculation that it might be from Malaysia Airlines Flight 370, which disappeared almost two years ago. More on p13 AP PHOTO MALAYSIA’s leader defended the country’s strict security laws, saying they are needed to fight terrorism as the Islamic State group warned of revenge over a crackdown on its members. -
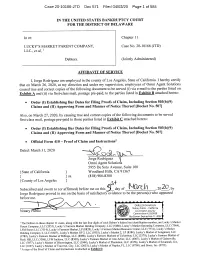
Case 20-10166-JTD Doc 571 Filed 04/03/20 Page 1 of 584 Case 20-10166-JTD Doc 571 Filed 04/03/20 Page 2 of 584
Case 20-10166-JTD Doc 571 Filed 04/03/20 Page 1 of 584 Case 20-10166-JTD Doc 571 Filed 04/03/20 Page 2 of 584 EXHIBIT A Case 20-10166-JTD Doc 571 Filed 04/03/20 Page 3 of 584 Lucky's Market Parent Company, LLC, et al. - Service List to e-mail Recipients Served 3/26/2020 ASHBY & GEDDES, PA ASHBY & GEDDES, PA BALLARD SPAHR LLP KATHARINA EARLE WILLIAM P. BOWDEN CRAIG SOLOMON GANZ [email protected] [email protected] [email protected] BALLARD SPAHR LLP BALLARD SPAHR LLP BALLARD SPAHR LLP DUSTIN P. BRANCH LAUREL ROGLEN LESLIE HEILMAN [email protected] [email protected] [email protected] BALLARD SPAHR LLP BALLARD SPAHR LLP BIELLI & KLAUDER, LLC MATTHEW G. SUMMERS STACY H. RUBIN DAVID M. KLAUDER [email protected] [email protected] [email protected] BROWNSTEIN HYATT FARBER SCHRECK, LLP BROWNSTEIN HYATT FARBER SCHRECK, LLP BUCHANAN INGERSOLL & ROONEY PC ANDREW J. ROTH-MOORE STEVEN E. ABELMAN MARY CALOWAY [email protected] [email protected] [email protected] CLARK HILL PLC COLE SCHOTZ PC COLE SCHOTZ PC KAREN M. GRIVNER J. KATE STICKLES JACOB S. FRUMKIN [email protected] [email protected] [email protected] DUANE MORRIS LLP ELLIOTT GREENLEAF, P.C. FAUSONE BOHN, LLP JARRET P. HITCHINGS SHELLEY A KINSELA CHRISTOPHER S. FRESCOLN [email protected] [email protected] [email protected] FROST BROWN TODD LLC FROST BROWN TODD LLC HAHN & HESSEN LLP A.J. WEBB RONALD E. GOLD EMMA FLEMING [email protected] [email protected] [email protected] HAHN & HESSEN LLP HAHN & HESSEN LLP HAHN & HESSEN LLP JEFFREY ZAWADZKI MARK S. -

Assembly to Hold Debate on Subsidy Cuts on Feb 9
SUBSCRIPTION WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016 RABI ALTHANI 17, 1437 AH www.kuwaittimes.net Govt mulling Pope urges Malaysia clears Djokovic, alternatives to Iran to act PM in scandal, Federer to meet cutting budget for peace in says Saudis in semis, Serena spending2 Middle East8 gave12 ‘donation’ thumps17 Sharapova Assembly to hold debate Min 03º on subsidy cuts on Feb 9 Max 13º High Tide 01:05 & 14:48 Deficit vs reserves discussed • Nod to monopoly, agencies law Low Tide 08:27 & 20:23 40 PAGES NO: 16768 150 FILS By B Izzak KUWAIT: The National Assembly yesterday agreed to hold a special debate on Feb 9 to discuss government plans to lift or reduce subsidies on public services and fuel. The government is expected to brief the Assembly with the recommendation of a study by an international consultant agency proposing raising the prices of petrol, electricity and water as part of a comprehensive reform program. Finance Minister Anas Al-Saleh told reporters the gov- ernment program deals with rationalization of subsidies and economic reforms to stimulate the private sector and national economy as a whole. The minister refused to say if the issue has been settled and the raising of charges is only a matter of time and is awaiting the debate in the Assembly, saying that the issue will be decided along with the Assembly. Saleh said that the difference between Kuwait and other Gulf states, which have taken decisions to raise prices to face the budget deficits, is that the Kuwaiti government has constitutional obligations. HH the Amir last week told editors of local dailies that the government will increase the price of petrol, electrici- ty and water. -

Asia in Undergraduate Education: Integration, Enhancement and Engagement
Asia in Undergraduate Education: Integration, Enhancement and Engagement 27th Annual Conference April 12 - 14, 2019 Kroc Institute for Peace & Justice University of San Diego Campus Welcome to San Diego!! ASIA IN UNDERGRADUATE EDUCATION: INTEGRATION, ENHANCEMENT, AND ENGAGEMENT The 2019 ASIANetwork Conference theme focuses on Asia in Undergraduate Education: Integration, Enhancement, and Engagement. As a consortium that strives to strengthen the roles of Asian Studies in the context of liberal arts education, integrating, enhancing and engaging Asia in the curriculum is the lynchpin of our work. This theme highlights range of methods, strategies, and initiatives that have been employed to integrate, enhance, and engage Asia in various disciplines and interdisciplinary works. This conference theme also provides directions in the efforts of integrating, enhancing, and engaging Asia in theopportunities curriculum. to reflect on the outcomes, challenges and future On behalf of the program committee, the Chair of the AN Board, Karen Kingsbury, and our Executive Director, Gary DeCoker, I wish you an enjoyable and productive experience at the conference! Siti Kusujiarti, Program Chair, ASIANetwork 2019 Conference Vice Chair, ASIANetwork Board of Directors Professor of Sociology, Warren Wilson College ____________________ USD Guest WiFi Instructions If you have a “eduroam” account, you can use it at USD. Others may access WiFi as a guest. If your device is searching for WiFi, select “usdguest” or go to: www.sandiego.edu/guest-wireless/. Click continue on the acknowl- edgement page to go to the log-in page. Log in with a social media account or register with an email address. When registering with an email address, you will be directed to a page with a five-minute timer. -

The World of Temperance in Bulgaria, 1890-1940
Research Collection Doctoral Thesis Sober contemporaries for a sober Future: The world of temperance in Bulgaria, 1890-1940 Author(s): Kamenov, Nikolay Publication Date: 2015 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-010875920 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Nikolay Kamenov SOBER CONTEMPORARIES FOR A SOBER FUTURE: THE WORLD OF TEMPERANCE IN BULGARIA, 1890-1940 DISS. ETH Nr. 22937 SOBER CONTEMPORARIES FOR A SOBER FUTURE: THE WORLD OF TEMPERANCE IN BULGARIA, 1890-1940 A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF SCIENCE OF ETH ZURICH (DR. SC. ETH ZURICH) presented by NIKOLAY GALINOV KAMENOV M.A., JACOBS UNIVERSITY BREMEN born on 30th May 1984 citizen of BULGARIA accepted on the recommendation of Prof. Dr. Harald Fischer-Tiné Prof. Dr. Nada Boškovska Prof. Dr. Sebastian Conrad 2017 The dissertation consists of a title page, i-xvii pages, 240 pages of main body, bibliography and 34 figures. Submitted to the Swiss Federal Institute Technology, Zurich. For the conferral of a PhD title. Presented by Nikolay Kamenov, MA, born 30.051984, Sofia, Bulgaria. Accepted on recommendation of: Prof. Dr. Harald Fischer-Tiné (ETH Zürich) Prof. Dr. Nada Boškovska (Universität Zürich) Prof. Dr. Sebastian Conrad (Freie Universität Berlin) The research for this dissertation has been made possible by a generous grant from the Swiss National Research Foundation in collaboration with the German Research Foundation. Apart from this 36 months of research stipend and the main portion of my travel budget, my research has been supported by the Swiss Federal Institute of Technology for another three months, while the chair for the History of the Modern World has kindly covered some of my travel expenses.